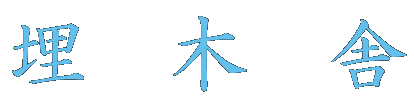安芸どのが、伺候した。何かの打開策を、協議中らしい。──
守備の軍勢は、こぞって、ささやき伝えていた。
「公卿は、頼りにもならぬが、安芸どのには、策もあろう。安芸どのの家人のことから、ひき起こされた事件でもあるし・・・・」
いまや、清盛の一進一退は、武者全体の注目の的だった。彼が、身に引き受けて、家之子の時忠や平六を、叡山へ渡さないとしていた態度が、鬱然
たる共感と支持の上にあることは確かである。
事件の生じない前からでも、清盛は、武者所の全員から、いつとはなく、安芸どのは話せる男と、敬愛を集めていた。といって、べつに彼になんの武勇も交友上の技巧もあるわけではないが、ただ、彼はよく人の貧乏に気がついて、人の貧乏の片棒をかついだ。
また、殿上に対して、彼ほど、ずけずけものの言える武者は他にいなかった。正直である一面、大ずぼらの抜けているところがあった。正盛、忠盛の二代にわたる忠勤を見ておられる現法皇は、清盛にも、特に目をかけておいでになる。さらに、もう一つの特徴は、彼の姿のあるところ、たちまち、彼の色、彼の雰囲気ふんいき
、彼の陽気に、くるまれてしまうという現象がある。
毛虫眉まゆ
、下がり眼じり、大きな鼻、大きな唇など、すべて大まかな顔の造作。わかて、いつも赤みのある若い頬ほお
やあごの、肉ししむら に、ぼてっとついている大きな耳。笑うと、揺れる耳たぶ。──
人びとは、この男を囲んでいると、なんとなく、陽気になり、生きている苦憂を、物ともしなくなるのだった。
── その顔の持ち主が、今、中門を出て、広間ひろま
へ歩いて来るのを見ると、たちまち、彼のまわりを、武者たちが、取り巻いた。
「伊勢どの。なんぞ、御評議で決まったのか。院宣いんぜん
も、降りそうか。どうあったの、御前のもようは」
矢つぎ早に、同じ問いが、口口から出た。清盛は、その中で、背にかけていた兜かぶと
を、さも暑そうにかぶって、緒お
を、あごの下で結んでいた。
「いや、そう、心配するな。すぐ祗園へ向かい、神輿へ、足止めを言い渡して来る」
「足止めを?」
「おお。まあ、安芸守に、委せておけ」
「でも、たださえ恐れを知らぬ荒法師ども、わけて、昨夜からは、われら武者輩むしゃばら
など、チリ芥あくた とも思わず、殺気だっていることであろうに。──
そこへ、安芸どのが、行かれたら、ただではすむまい ──」
「もちろん、ただではすむまい。── だから、時忠、平六に二人だけは連れて行く。気の毒だが、二人の身を、彼らの渡して、話をつけてくるつもりだ」
「えっ。では・・・・ついに、二人の身柄がらを、叡山へ引き渡すことになったのか」
「やむを得ない」
「・・・・ちいっ。なんたることだ。それではやはり、武者を犠牲にしての、院の御屈伏ではないか」
「足た
しにもならぬ嘆きなどはよしてくれ。しかし、その解決を、申し出たのは、かくいう清盛で、院のお旨でもないし、決して、院の御屈伏ではない。── いや、暇どって、彼らが先に、祗園からなだれ出したら防ぎがつかぬ。幸い、生きて還ったら、何か、みやげ話もあるだろう。おのおのは、ただ御守護に、怠りあるな」
清盛は、時忠、平六をうしろに連れて、馬上緩々かんかん
と、大路へ出て行った。
道は、白っぽく、乾かわ
ききっている。木の葉も草も、うなだれている陽ざかりである。人びとは、白昼の死影を見つめるように、遠ざかる三人を見送った。── まるで、唖蝉おしぜみ
みたいに、一語をももらす者もなかった。 |