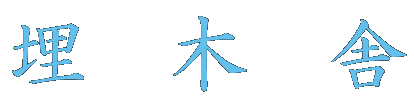朝。──
街の様相は、一変していた。
戸を開ける家もない。いつものような人通りもない。朝にして夜のままな、大路である。
おりおり、目につくのは、武者ばかりだった。十騎、二十騎。あるいは二、三騎が多くの郎党を連れたりして、すざく
から皇居十二門の方へ。── また、三条西ノ洞院へ急ぐのは、鳥羽院のかために参さん
じる人びとともみえる。
「安芸守あきのかみ
清盛に会いたい。自分は、平ノ忠正でおざる。・・・・清盛は、どこの守りに、立っておろうか」
院の八門は、甲冑かっちゅう
の武者で、埋まっていた。そのなかを、禁門の守備から抜けて来た兵部の忠正は、ただ一騎で、いま、訊き
きまわっていた。
北面の一人が、かれの教えた。
「安芸どのは、おそらく、ここには、参じておられますまい。── 叡山えい
の大衆は、安芸どののお住居を、先に、踏み潰してから、一院へ、襲よ
せるのであろうと、もっぱら言われておりますから」
「なるほど、院の守りよりは、わが家が危ういか。ありそうなことよ。では、六波羅へ行ってみよう」
彼はふたたび、駒こま
を、松原から五条の方へ飛ばして行った。── するとかなたから、ぶらんぶらんと、悠長ゆうちょう
なその人とともに、馬までが、尾を振り回しながら、のん気に、漫歩して来る一騎の武者があった。
「おうっ。──叔父上、どこへ」
矢のように、すれ違いかけた忠正を、清盛の方から、呼び止めた。
忠正は、あわてて、馬首をめぐらしながら
── 「やあ、清盛か。どこへという挨拶は心得ぬ」 と、近づくなり、頭から言った。 「強訴ごうそ
の山法師が、二千余人、日吉ひえ
山王の神輿を奉じて入洛 ── と知った時、やれやれ、そちが折角、長の貧乏から脱けて、近ごろ、普請したと聞く新屋敷も、あたら、これまでかと、胸を痛めたのも、叔父おじ
甥おい の仲なればこそだ。何とか、加勢もしよう、思案もかさんと、こう駆けつけて来たものを」
「それは、どうも・・・・」
清盛は、ひとごとみたいに、笑い流して、頭だけは、丁寧に下げた。
「ですが、叔父上。あいては、叡山の大衆、天子といえ、上皇といえ、頭ず
も上げられない神輿を押し立てて来るものを、だれが、御加勢くださろうと、どうなりましょう。 ── 踏み潰された清盛の住居のあとを、ご見物に来られたと申すなら分かりますが、仰せは、おかしく聞こえます。あははは・・・・御親切ではございましょうが」
「うム、読めた。夜明けとともに、刑部省で、忠盛どににも行き会うたが、忠盛どのの口吻こうふん
も、いま見るそちの容子ようす
も、一つものだ。父子おやこ して、はや、どうにでもなれというすてばちか」
「父は父、わたくしはわたくし、武者として、肚はら
をすえているだけで、別儀は何もありません。叔父上こそ、少し、どうかしておりませんか。山法師の強訴沙汰ざた
など、めずらしくもないことに」
「いうな、広言を吐ほ
ざくと、そちたち父子の、喪心そうしん
ぶりが、見えすくぞ」
忠正は、この甥の成長を、少しも認めようとしなかった。破れ直垂ひたたれ
一枚の、十年前の姿を、いつも、清盛の姿と決めて、頭ごなしが、癖だった。
清盛の方でもまた、父の弟と思えばこそ、何事も、こらえているが、このくらい虫の好かない人もない。ことに、ここ数年の間に、父は刑部卿となり、自分は安芸守と累進るいしん
しているのが、この叔父には、何か、気が気でないような、あせりを抱かせているらしい。
といって、忠正も、近来の武者の重用で、いまでは、禁門の左衛門尉である。決して、不遇に、置き去りをくっているわけでもないのに、ともによろこびを、よろこびとしないのだった。
「ま。・・・・降りろ、清盛。降りて、申し聞かせることがある」
「いや、院の守護に、参るところなので、道くさは、ちと、迷惑しますが」
「たれより先に、馳せ向かわねばならぬ者が、今ごろ、ぶらぶらと、足重たげに参りながら、何を、人なみな・・・・」
忠正は、先に、地へ降り立ってしまった。そして、清盛の具足の端を、下からつかんだ。
|