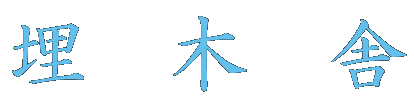世にいう、山門の強訴
とは、つまり山門大衆だいしゅ
の、示威運動にほかならない。
数千の荒法師や、神人じにん
が、隊伍たいご を組んで、入洛じゅらく
し、自己の要求を押しつけるため、朝廷や、摂関家へ、押しかけて行く。
この場合、南都 (奈良) の大衆だと、春日神木かすがしんぼく
と称する大榊さかき を、先頭に持ち出し、叡山えいざん
では、日吉山王の神輿しんよ をかつぎ出すのを、常套手段じょうとうしゅだん
としている。
で。── 南都のそれを “榊振さかきぶ
り” といい、延暦寺のそれを “神輿振みこしぶ
り” という。どっちも 「絶対なるもの」 の標識である。
これを、禁門に、振り込まれると、天皇すらも、階を下りて、地に、遥拝ようはい
しなければならない。公卿百官も、衣冠を低うして、下座げざ
につかねばならない。いわんや、武者どもは、弓を伏せ、かりそめの弦鳴つるな
りすらも、慎つつし まねばならない。──
というほど、絶対なものだった。
円融天皇の天元年間から、後奈良帝までの、約六百年ほどの間に、強訴の行われたことは、実に、二百回を越えたというから ──
その効果も、いかに覿面てきめん
であったかがわかる。
とはいえ。
これが、庶民のためだったことは、一度もない。ただ、時の社寺大衆という、一部の我意と、山の擁護に過ぎないのだ。
朝廷あり、政廟せいびょう
あるうえに、なぜまた、こんな超特権をおいてしまったものか。── おそらく、時の、あわれな庶民たちにも、わけが分からないことだったろうし、後世の社会にとっても、ちょっと、理解し難い、ふしぎな世態であったというしかない。
耶蘇やそ
紀元前の ── 五百五十八年前
ヒマラヤの峰を、青空に見る王家の子、悉達しった
太子は、
(人間は、なぜこう不幸なのか、いつも不安なのか)
ぽつねんと、思索のうちに、涙を流した。
ガンジスの大河を持つ広い熱帯の土の住民は、みな被征服者の子孫であり、人権の自覚なく、卑屈と懶惰らんだ
に慣れた民だった。
(それさえ、みじめな者であるうえに)
と、太子は、つねに、平等愛の眼をそれに注いだ。どんな、みじめな者、貧しい者でも、うけたる生と、この地上を、愛楽の庭として、生きあうことは、できないものかと。
ひとり、夜も、思い泣いた。
王城の綺羅きら
、太子の宝衣、すべて、かれには、憂いであった。
生きるため、人が、殺しあい、謀はか
りあい、人を陥おと して、生きた者が、つかのまに、また陥されて、たちどころに、白骨と化か
す、酸鼻さんび やら、淫猥いんわい
なる男女の、泡沫ほうまつ のような生命の消耗を
── またその余毒と余害とが、果てなく、不幸を、人間に約束づけてゆくおそろしさを観み
、
(人間の不幸は、人間が内に持つ欲情の魔毒にある。欲情の新しい解決の工夫くふう
。・・・・もし、それが成就じょうじゅ
したら)
と、ついに、宮廷を捨てて、山にかくれた。
彼は、みずからの若い肉体を、その問題の犠牲にえ
に供した。空想の哲学ではない。
人間官能の、感じうる限りの、苦行をとげ、やがて、雪山せつざん
を下りる日、旧教婆羅門ばらもん
にかわる新しい光明をもって、人間の辻つじ
に立った。
── 仏教の発祥はっしょう
である。 |