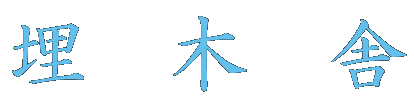(時忠と、郎党の平六とやらを、引き渡せ)
と、祗園側から、掛け合うことも、数度に及んだが、清盛は、いつもせせ笑って、てんで受け付けもしない。
刑部省へ、談じ込んでも、刑部卿
その者が、清盛の父忠盛である。らちはあかない。
で。── ついに、山門の名をもって、関白忠通ただみち
へも、鳥羽院へも、直々じきじき
に、抗議の使者をたて、清盛親子を糾弾きゅうだん
し、幾たびとなく、交渉を重ねたが、言を左右に託し、まったく、わが山門を軽蔑している。
言語道断の沙汰さた
。われらの堪忍も、今は、やぶれた。
そもそも近来、朝廷でも、鳥羽院でも、わが叡山の地位が、いかなるものかを、忘れかけている。かりそめにも、わが北嶺ほくれい
の大比叡小比叡は、皇城鬼門の鎮護として、また天皇本命の道場として、桓武かんむ
帝の勅を奉じ、開山伝教でんぎょう
大師が、山王二十一社の諸天に祈りをこめ、根本中堂こんぽんちゅうどう
には、末代安穏の法燈を照らしおかれたものではないか。
それゆにこそ ──
ひとたび、大衆だいしゅ
が、日吉ひえ 山王の神輿しんよ
を奉ほう じて、洛内らくない
にはいるときは、天皇たりとも、おんみずから、庭上に下りて、これを遥拝ようはい
して迎え遊ばすのが、古来からの例である。
天皇すでにしかり。── 公卿百官など、いうまでもない。
「さるを、なんぞや、不問に付しおく、一院の御態度も、関白家の対応も、けしからぬ。そもそも、古例を忘れ、われら北嶺の徒と
を、軽んずるものじゃ。一山の大衆よ。いかが、思わるるか」
事件の経過を、獅子吼ししく
してきた廻廊の大法師は、こぶしを振るって、こう結んだところだった。
大講堂の前の大衆は、黒々くろぐろ
と、表情の波を揺ゆ るぎたてた。──かれらは、興奮し、激発して、口々に、
「下山げざん
、下山」 とさけび、
「強訴ごうそ
よ、強訴よ。── 懲こ らしめたがいい」
と、沸くがごとく、わめいた。
わめくにも、すべて、覆面があるのに、鼻を手で隠して、声を変えて、いうのが、山法師の習性だった。
その日、ふたたび、下山鐘が、鳴り渡った。
山王二十一社の神人やちは、神輿をかついで、根本中堂の前に、奉安する。
神仏混淆しんぶつこんこう
というよりは、 “本地垂迹ほんちすいじゃく
” というむずかしい理論から、神社はみな、仏教色の中に、織り込まれていた時代なのだ。
本尊薬師如来、日光月光二菩薩ぼさつ
、梵天ぼんてん 、帝釈たいしゃく
、十二神将の宝前で、大護摩ごま
がたかれ、三綱さんごう の僧座そうざ
と、百僧の読経のうちに、強訴入洛じゅらく
の式があげられ、宣誓書が、読まれる。檄げき
が飛び、この附近 ── 毘沙門堂びしゃもんどう
、大師堂、戒壇院かいだんいん
のあたりまで、武装した学侶がくりょ
、学生がくしょう 、堂衆たちなどの僧兵は、いよいよふえて、地という地をうずめつくした。
「ここ久しく、一院、朝廷へも、見参けんざん
せぬ。おりには、神輿振りをお見舞い申しおかぬと、とかく、われらを、侮あな
ずることにもなる。── このたびの曲事こそ、天の与えた機。あわせて、小ざかしき武者どもの胆きも
をも、取りひしいでおかねばならぬ」
と、衆徒は、はるかな都心へ、眼を放って、豪語しあった。
六月の烈日が、中天に燃えかがやくころ、神輿をかつぐ一群を真ん中に、満山の蝉せみ
しぐれを進軍の歌として、強訴をはかる一山の大衆は、山つなみのように、下山し出した。 |