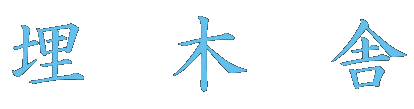文治二年
(1186) の初夏の頃、後白河院が密かに大原へ御幸
された。一行は鞍馬街道から小野、江文えぶみ
峠を越えて、ようやく寂光院にたどり着いた。いかにも質素ではあるが、心配りされた趣のある風情ふぜい
である。後白河院が 「誰か居らぬか」 と訪おとな
われると、しばらくしてから年老いた尼が出て来た。名を問われると、 「お忘れでございましょうか、亡き信西の娘でございます」 と言って、袖に顔を押し当て、忍び泣きをもらしている。
「そういえば、おまえは阿波内侍ではないか」 と、後白河院も涙をこらえることが出来ないご様子である。
阿波内侍は後白河院を庵室にお招きし、襖の奥に安置されている阿弥陀如来像や安徳天皇の肖像画などをお見せした。そこから少し離れた所に、女院の御製ぎょせい
らしきものが短冊にして掛けられていた。 |
| おもひきや み山のおくに すまぎして 雲ゐの月を よそに見んとは |
|
かって宮中で見た月をこんな奥深い山の中で見ようとは思いませんでした。
短冊のかたわらには、粗末な麻の衣や紙でつくった夜具が竹竿たけざお
に掛けられていた。かっては国母こくも
と仰がれ、この世の贅ぜい を尽くした衣裳を身にまとわれた方がと思うと、お供の公卿くぎょう
や殿上人でんじょうびと たちも涙をこらえることが出来なかった。
そうこうしているうちに、女院が裏山で岩つつじを手折たお
って戻って来られたが、後白河院のお忍びの御幸と知って驚き、ただ涙を流すばかりで、どうしてよいか分からぬありさまであった。女院が粗末な身なりを恥らいながらも御前に出られると、後白河院が
「誰か訪ねて来る者はおらぬのか」 と尋ねられた。 「かの隆房や信隆の北の方になっております妹たちが、ときおり便りを寄越しますが、昔はあの人たちの世話になるとは思いも寄りませんでした」
と、女院が涙ながらに申し上げれば、お側にいる女たちも涙で袖を濡らすばかりであった。
女院は涙を抑えられて、我が子である先帝を失った悲しみも悟りに導く機縁だったのですと言う。さらに、清盛の娘として天子の国母となり一天四海を思うがままに出来た境涯から、都を追われ、西国の八重の潮路をさまよい、ついには一門の滅亡と安徳天皇のあわれな最期を目の当たりにしたさまを語って、
「これは仏道に言う六道ろくどう
廻めぐ りに相違ありません」
と申し上げた。後白河院も 「異国の三蔵法師さんぞうほうし
も悟りの前に六道を見たと聞きましたが、あなたのように目の当たりにされたのは、何とも珍しいことです」 と、涙にむせれば、お供の人たちも涙にくれぬ者はなかった。
ひとしきりの話も終わって、夕陽が西に傾く頃、後白河院は寂光院を後にされた。一行の姿が遠くなると、女院は庵室の御本尊に向かわれて、 「先帝聖霊しょうりょう
、一門亡魂ぼうこん 、成等正覚じょうとうしょうがく
、頓証菩提とんしょうぼだい 」
(先帝の御霊と平家一門の亡魂が正しい悟りを得て速すみ
やかに成仏じょうぶつ されますように)
と、泣く泣くお祈りされた。また、寝所の襖にも次のような歌を書きつけられた。 |
| いにしへも 夢になりにし 事なれば 柴のあみ戸も ひさしからじな |
|
| 昔のことは全て夢になったのだから、柴しば
の編戸の生活も長くはないでしょう。この歌が詠まれたから数年後の建久けんきゅう
二年 (1191) 二月の中旬、建礼門院はその苦難に満ちた生涯を終えられた。だだし、その崩年には諸説あり、遅いものとしては貞応じょうおう
二年 (1223) とする説まである。御陵は寂光院の側そば
につくられた。 |