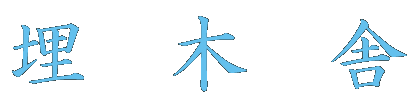廣瀬は明治三十五年一月十六日、ペテルブルグを汽車で発った。出発が十時だったために、廣瀬はアリアズナを訪ねて、最後の別れを告げることが出来た。
アリアズナは、別れの印だと言って、小さな銀時計を廣瀬に贈った。銀時計の蓋を開けると、「A」
の文字が刻んであった。アリアズナの 「A」 であり、AMOUR (愛) の 「A」 だった。
「どんなに短くても構いませんから、お手紙を下さい。これから先は毎日毎日、あなたのお手紙ばかりを待っています」
別れが辛いから、駅には見送りに行かないと言うアリアズナは、廣瀬の顔を真っ直ぐ見て言った。
「私、いつかきっと、日本に行けると思っています。そのうちに、きっと」
「運命が許すならば、その日が来ることを心から祈ります」
恋人に言うには無粋な言葉である。が、そう答えることが精一杯だった。四年五ヶ月に及ぶロシア滞在と国情研究、国際情勢を考え合わせれば、日露の開戦はもはや避け難い。ロシアは海軍力だけでも日本の三倍近い大国である。そんpロシアと、海軍士官として戦う廣瀬は死を覚悟している。二人が結ばれることは、よほどの幸運に恵まれない限りあり得ない。廣瀬はそう考えていたのである。
翌朝、廣瀬はモスクワに着いた。モスクワで一番大きいホテル
「スラヴィヤンスキー・バザール」 に一泊し、クルスキー駅からいよいよ、シベリア鉄道に乗り込んだ。その駅に、意外な人が見送りに来た。廣瀬が最初に親交を深めたペテルセン博士である。
ペテルセンは、息子、オスカルの手紙を持参していた。オスカルは、ペテルブルグで廣瀬を見送れなかったことが残念でならず、別れを心から惜しむ手紙を書いて、父親に託したのだという。
「寂しいね。雪が溶ける春になってからでも出発はいいのではないかね。なぜわざわざ、危険を冒して冬のシベリアに向かうのかね」
ペテルセンは、心底心配だと言う顔で、廣瀬を押し止めた。一般に、ロシア人ほど情けに厚い国民は少ないという。しかし、国としてのロシアほど強欲で狡猾な国も少ないというのが、当時の欧州での評価である。
「ご心配はありがたいが、もう戻れません。博士のご親切は生涯忘れません。どうかオスカルに、そしてマリアによろしく」
廣瀬は車上の人となった。 |