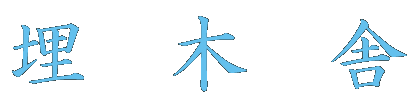ペテルブルグで廣瀬を迎えたのは八代六郎である。廣瀬が海軍兵学校在学中、校長の有地品之允の副官を務め、兵学校の柔道科設置に力添えしてくれた人物である。当時は大尉だったが、少佐に昇任して、今は在ロシア公使館付武官になっていた。
留学生・廣瀬は八代の自宅に同居した。六階建てアパートの三階にある一戸で、五室あり、留守番の老女や家事を頼む女性二人を雇っていたというから、当時の駐在武官がどの程度の期待を母国から担っていたかがよくわかる。
廣瀬は、ロシア語の教師としてスペランスカヤという女性を選んだ。彼女の教え子は四人いて、廣瀬の授業は毎日午前十時半からの一時間だった。三十歳目前にして初めて本格的にロシア語を学ぼうという廣瀬のために、スペランスカヤは授業を延長したり、自宅の夕食に招いたりと、熱心に教えてくれた。
その親切に何の不満もなかったが、ある日突然、不仲になる。八代と一緒に招かれた夕食の席で、彼女が何気なく言った言葉に、日本の皇室を軽んじる含みがあった。それを廣瀬が聞きとがめたのである。
スペランスカヤは謝り、八代も取り成したので、その場は収まったが、廣瀬の心にわだかまわりが残った。何日かして、廣瀬が八代に言った。
「どこか別のところでロシア語を習います。責めるのは酷だとわかっていても、顔を見ると思い出してだめです」
「そうか。君はそうだろうなあ。仕方があるまい」
兵学校の生徒時代からの付き合いで、廣瀬の性分を知り尽くし、無二の理解者とも言えた八代は苦笑いした。豪放磊落でさっぱりした性格の廣瀬だが、こと尊王の気持は何物にも代え難い価値観だった。それが廣瀬の行動を決定付けていたと言っても過言ではない。それを示す逸話である。
廣瀬はやがて、大蔵省官吏の家に同居して、その家の主婦にロシア語を習う。今ならさしずめ、大学にでも通うところだろうが、当時の留学生士官の勉学とはそういうものだった。
|
| (武夫事は別に異状なく、例により語学の研究に困められ居り候) |
|
家族に宛てた手紙には、三十の手習いに苦しむ廣瀬の姿がにじみ出ている。
ペテルブルグの季節は、九月末の廣瀬の到着から急速に冬に向かっていた。朝は八時まで暗く、午後は三時には灯火が要るという生活である。さすがの廣瀬も気が滅入る。が、こと食事に関しては、なかなかの手練れぶりを発揮するから面白い。ベルリンの山形に依頼して、味噌や醤油を送ってもらったのである。そうした日本食材が手に入るのが、日本が追いかける欧州だとすれば、ロシアはまだ、その域に達していなかった。
廣瀬はさっそく、味噌汁を作り、レモン味噌なる一品を調理した。柚子味噌にしたかったのだが、ペテルブルグではさすがに柚子が手に入らなかった。八代の自宅に持ち込んで、薩摩汁を振る舞ったりもした。 |
| (スマートで機転が利いて几帳面、負けじ魂これぞ船乗り) |
|
| 船員教育、海軍教育の一つの目的を示すものとして、こんな言葉がある。無骨なイメージの廣瀬が厨房に入り、薩摩汁を作る姿は想像し難いが、実際の海軍士官は身の回りのことは大抵、自分で出来た。それを叩き込まれるのが兵学校であり、艦上勤務である。軍務の大半は狭い艦内で生活するわけだから、一人で何でもこなせないと、それこそ使い物にならないのである。 |