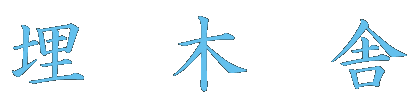悪
しき事は身に覚えて、博奕打ばくちうち
負けてもだまり、傾城けいせい
買取上かひとりあ げられてかしこ顔するものなり。喧嘩仕けんくわし
引けとる分ふん かくし、買置かひおき
の商人あきんど 損をつつみ、これ皆、闇くら
がりの犬の糞くそ なるべし。中にも、いたづら気質かたぎ
の女を持合もちあは す男の身にして、これ程情なさけ
なきものはなし。
「おさん事も死にければ、是非ぜひ
なし」 と、その通りに世間をすまし、年月の昔を思ひ出て、憎しといふ心にも、僧をまねきて亡な
き跡を弔とむら ひける。哀れや、物好きの小袖も、旦那寺だんなでら
の幡はた ・天蓋てんがい
となり、無常の風にひるがへし、さらに又、嘆きの種たね
となりぬ。 |
具合の悪い事は当人にはしみじみ感じられるものだが、博奕ばくち
打ちは負けた時は黙り、遊女狂いをした者は金を巻き上げられて利口ぶった顔をするものである。喧嘩師は負けた分を隠し、買置きの商人は損した事を包み隠す。これらはすべて諺ことわざ
にいう暗がりの犬の糞くそ の類たぐい
であろう。中でも浮気性の女房を持ち合わす事は、男の身としてこれ程情けないものはない。
「おさんのやつも、死んだからには仕方がない」 と、大経師だいきようじ
の家では死んだことにして世間のつとめを済まし、生きていた年月の事を思い出しては、憎いと思う心にも、やはり僧を招いて亡き跡を弔ったのであった。気の毒に、数寄すき
を凝こ らした小袖も、今は旦那だんな
寺の幡はた ・天蓋てんがい
となって、無常を知らせる風に翻り、改めてまた悲しみをそそる種となった。 |
|
| されば、世の人程大胆だいたん
なるものはなし。茂右衛門その律義りちぎ
さ、闇には門へも出ざりしが、いつとなく身の事忘れて、都ゆかしく思ひやりて、風俗いやしげになし、編笠あみがさ
深くかづき、おさんは里人さとびと
にあづけ置き、無用の京上のぼ
り、敵かたき 持つ身よりは、なほ恐ろしく行くに、程なく広沢ひろさは
のあたりより暮く れ暮ぐ
れになって、池に影ふたつの月にも、おさん事を思ひやりて、おろかなる泪なみだ
に袖をひたし、岩に数ちる白玉しらたま
は、鳴滝なるたき の山を跡あと
になし、御室おむろ 、北野きたの
の案内あんない 知るよしして急げば、町中に入りて、何とやら恐ろしげに、十七夜の影法師も、我ながら我を忘れて、折々胸をひやして、住み馴れし旦那殿だんなどの
の町に入りて、ひそかに様子を聞けば、江戸銀えどぎん
のおそきせんさく、若い者集まって頭あたま
つきの吟味、木綿着物もめんきるもの
の仕立てぎはを改めける。これも皆、色より起おこ
る男振りぞかし。 |
| ところで、世間の人程大胆なものはない。茂右衛門のきまじめなこと、闇夜には用心して門口にも出ない程であったが、いつとなく世を忍ぶ身の上を忘れ、遠い都を恋しく思って、身なりを卑しげに変奏し、編笠を目深にかぶり、おさんは村人に預けて、用事もないのに京へ上って行った。敵かたき
を持つ身より一層恐ろしく思いながら行くうちに、まもなく広沢の辺あた
りから日暮れになって、池に映る二つの月影を見るにつけても、おさんの事を思いやって、愚痴ぐち
の泪は袖を濡ぬ らし、谷川の波の白玉しらたま
が岩に砕ける鳴滝なるたき の山を後にして、御室おむろ
・北野きたの となると、もう勝手を知った所だというので急ぐと、京都の町の中に入って、何と恐ろしく、十七夜の月に映る影法師も、我ながらわが影であることを忘れて、時々胆を冷やしながら、住みなれた旦那だんな
殿の町に入った。そっと店に近づいて様子をうかがうと、江戸から為替かわせ
銀が遅いといって調べている。若い手代たちは集まって、髪の結いぶりを吟味し、木綿着物の仕立ての出来栄えを品評などしている。これらも皆色気から起こる男ぶりの沙汰さた
である。 |
|