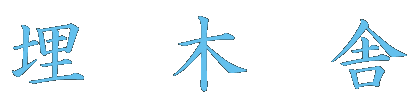「とかく世にながらへる程、つれなき事こそ増
れ、この湖みづうみ に身を投げて、永く仏国ほとけくに
の語らひ」 といひければ、茂右衛門も、 「惜しからぬは命ながら死んでの先は知らず。思ひつけたる事こそあれ。二人都への書置かきおき
残し、入水にふすい せしといはせて、この所を立退たちの
き、いかなる国里くにさと にも行きて、年月としつき
を送らん」 といへば、おさん喜び、 「我も宿を出しよりその心掛こころがけ
あり」 と、 「金子五百両、插箱はさみばこ
に入れ来きた りし」 と語れば、
「それこそ世を渡るたねなれ。いよいよここをしのべ」 と、それぞれに筆を残し、 「我々、悪心あくしん
起りて、よしなき語らひ、これ天命のがれず、身の置所おきどころ
もなく、今月今日こんげつこんにち
、浮世うきよ の別れ」 と肌の守りに一寸八分の如来によらい
に、黒髪の末すゑ を切り添へ、茂右衛門は差し馴れし一尺七寸の大脇差わきざし
、関和泉守せきのいづみのかみ
、銅あかがめ 拵こしら
へに、巻龍まきりよう の鉄鍔てつつば
、それぞれ人の見覚えしを跡に残し、二人が上着うはぎ
、女草履をんなぞうり 、男雪踏おとこせつた
、これにまで気を付けて、岸根きしね
の柳がもとに置捨おきす て、この浜の猟師調練てうれん
して、岩飛いはとび とて水入すい
りの男を、ひそかに二人やとひて、金銀取らせて、あらましを語れば、心やすく頼まれて、更ふけ
行く時待合まちあ はせける。
おさんも茂右衛門も、身拵ごしら
へして、借家かりいへ の笹戸ささど
明あけ 掛け、皆々をゆすり起こして、
「思ふ仔細しさい のあって、ただ今最期さいご
なるぞ」 とかけ出、あらけなき岩の上にして、念仏の声幽かす
かに聞えしが、二人ともに身を投げ給ふ水に音あり。 |
「ともかくこの世に生きながらえるほどつらい事がつのるばかり、いっそこの湖に身を投げて、極楽浄土で長く夫婦の語らいをしよう」
とおさん・・・ が言うと、茂右衛門も、
「惜しくない命とはいうものの、死んでの先はどうなるかわかりません。それについて私に考えついた事があります。二人とも都の家へ書置きを残して、身投げして死んだと思わせて、ここを立ち退き、どこか遠い田舎いなか
にでも行って年月を送りましょう」 と言うと、おさんは喜んで、 「私も家を出て来た時からそのつもりだった」 と言って、 「金子きんす
五百両插箱はさみばこ の中に入れてきた」
と話すと、 「それこそ暮らしの種でございます。いよいよここをこっそり落ちのびましょう」 と、両人それぞれ書置きを残し、 「私どもは、邪よこしま
な心を起し、とんでもない不義をいたしました。この事、天の咎とが
めを逃のが れる事が出来ず、身の置き所がないので、今月今日この世にお暇いとま
いたします」 と書いて、おさんは肌の守りに持っていた一寸八分の仏様に、黒髪の末を切り添え、茂右衛門は差しなれた一尺七寸の大脇差、関和泉守せきのいずみのかみ作の銅拵あかねごしら
えに、巻龍まきりゅう の鉄鍔つば
がついていて、これは茂右衛門の持ち物と人も見覚えているのを後に残し、二人の着物、女の草履ぞうり
、男の雪踏せった 、これにまで心を配って水際の柳の木の下に捨て置き、この浜の漁師が鍛錬して、岩飛びというダイビングの上手な男を、ひそかに二人雇い入れ、金銀を与えて、あらましの事情を話すと、簡単に引き受けてくれ、夜の更けてゆくのを待合わせたのであった。
おさんも茂右衛門も身支度をして、借りた家の枝折しおり
戸を開けておいて、寝ていた皆をゆすり起し、 「思うわかがあって、ただ今最期をとげる」 と言うなり外に走り出た。やがて険しい岩の上で念仏の声がかすかに聞えたが、続いて二人とも身投げをしたらしく、水の音が響いた。 |
|
いづれも泣き騒ぐうちに、茂右衛門、おさんを肩に掛けて、山本分けて、木深こぶか
き杉村すぎむら に立退たちの
けば、水練すいれん は波の下くぐりて、思ひもよらぬ汀みぎは
に上るける。
つきづきの者ども、手をうつてこれを嘆き、浦人を頼み、さまざまさがして甲斐かひ
なく、夜も明け行けば、泪なみだ
に形見色々いろいろ 巻込まきこ
め、京都に帰り、この事を語れば、人々、世間を思ひやりて、外へ知らさぬ内談ないだん
にすれども、耳せはしき世の中、この沙汰さた
つのりて、春慰はるなぐさみ みにいひ止や
む事なくて、是非ぜひ もなきいたづらの身や。 |
| お供の召使どもは驚き呆あき
れ、二人の身投げを嘆き、浜辺の人たちを頼んで、様々に捜したけれども、そのかいはなく、空しく夜も明けた。涙ながらに形見の品をあれこれと包み込んで京都に帰り、家人にこの事を報告すると、人々は世間をはばかり、外ほか
へもらさぬよう内々で相談をまとめたが、耳さとい世間の事、この噂うわさ
がぱっと広がって、正月の慰みの種に、いつまでも消えなかった。何とも仕方のない心得違いをした身の果てである。 |
|