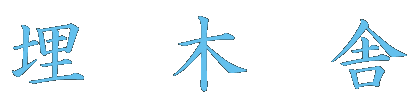身はかぎりあり、恋はつきせず、無常は我が手細工
の棺桶に覚え、世を渡る業わざ
とて、錐きり 鋸のこぎり
のせはしく、鉋屑かんなくづ の煙けむり
みじかく、難波なには の蘆あし
の屋や を借りて、天満てんま
といふ所がら住みなす男あり。 女も同じ片里かたさと
の者にはすぐれて、耳の根白く、足も土気つちけ
はなれて、十四の大晦日おほつごもり
に、親里の御年貢ねんぐ 三分ぶ
一銀ぎん にさしつまりて、棟むね
高き町屋まちや に腰元つかひして、月日を重ねしに、自然と才覚さいかく
に生れつき、御隠居きんきよ への心遣づか
ひ、奥様の気を取る事、それより末々すゑずゑ
の人にまで悪あ しからず思はれ、その後は、内蔵うちぐら
の出し入れをもまかされ、 「この家におせんといふ女なうては」 と、諸しよ
人に思ひつかれしは、その身かしこきゆゑぞかし。 |
| 人の生命には限りがあるが、恋の道は尽きることばない。世の無常は手ずから作る棺桶で悟り、世渡りの業として錐や鋸をせわしく使って、細々とした樽屋の暮らしを立て、粗末な家を借りて天満という場末の所柄にふさわしく住んでいる男がある。女も同じ片田舎の者だったが、それにしては器量よしで、耳の付け根も色白く、足も土気を離れて垢抜けていた。十四の年の大晦日に、両親がお年貢の三分一銀が払えず困ってしまったので、裕福なこの町屋に腰元奉公して、月日を重ねたのだが、自然と利口に生まれついて、ご隠居様へのよく心を配り、奥様の御機嫌を取り、それより下々の人たちにまでよく思われ、その後は、内蔵の品物の出し入れまで任され、
「この家におさんおせんという女がいなくては」 と、皆から思い込まれるようになったのは、本人が利発だからである。 |
|
されども、情なさけ
の道をわきまへず、一生枕ひとつにて、あたら夜よ
を明かしぬ。かりそめにたはぶれ、袖褄そでつま
引くにも、遠慮なく声高こわだか
にして、その男無首尾ぶしゆび
を悲しみ、後はこの女に物いふ人もなかりき。これを謗そし
れど、人たる人の小女こむすめ
はかくありたき物なり。
折節をりふし
は秋のはじめの七日、織女たなばた
に貸小袖かしこそで とて、いまだ仕立ててより、一度も召しもせぬを、色々七つ、雌鳥羽めんどりば
に重ね、梶かじ の葉にありふれたる歌をあそばし、祭り給へば、下々したじた
もそれぞれに、唐瓜からうり 、枝柿えだがき
かざる事のをかし。横町裏貸家かしや
まで、竈役かまどやく にかかつて、お家主殿いえぬしどのく
の井戸いど 替かへ
、今日ことに珍し。 |
けれども、この女は恋の道をわきまえず、これまでずっと、枕一つのひとり寝をして、せっかくの夜をむだに明かした。ちょっといたずらに袖や褄を引いても、遠慮なく大声を立てるので、その男は恥を掻いて悲しく思い、後にはこの女に物を言う男もなくなってしまった。これを謗る者もあったが、堅気の家の娘はこのようにありたいものである。
ちょうど時は秋の初めの七月七日、七夕に貸し小袖という行事があり、奥様は仕立ててから、まだ一度も着られた事のない小袖を、いろいろと七枚、雌鳥羽に重ね、梶の葉におきまりのありふれた古歌を書かれ、お祭りになると、召使の者どもそれぞれに、唐瓜や枝柿をお供えするのもおもしろい。横町や裏通りの貸家まで、一世帯一人の割当てで、お家主の井戸替えをするのだが、これも今日の珍しい行事である。 |
|