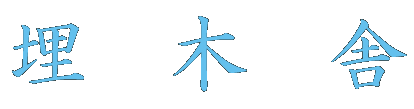| 六波羅には公卿僉議
あり。 「王事わうじ 脆もろ
き事なければ、逆臣ぎやくしん
誅伐ちゆうばつ 、時刻じこく
をや廻めぐ らすべき。たまたま新造しんざう
の皇居回禄くわいろく あらば、朝家てうか
の御大事なるべし。その期ご に臨のぞ
みて、官軍偽いつは りて退しりぞ
かば、凶徒きようと 定さだ
めて進すす み出い
でんずらん。その時、官軍入い
り替かは りて、内裏だいり
を守護しゆご し、火災くわさい
の難なん を止とど
めて、朝敵てうてき を中途ちゆうと
にたばかり出い だし、誅戮ちゆうりく
すべき」 由よし 宣下せんげ
せらる。 |
六波羅には公卿僉議があった。
「天皇の威勢は大いなるものがあるのだから、逆臣の誅伐は直ちに実行すべきである。万一皇居が火災になるかも知れず、それは朝廷にとっては大変なことである。その折、我らの軍勢が入り替わりに内裏に入り守護して、火災の難を防ぎ、朝敵をすばやくだまし討ちにして、殺害すべきこと」
の宣旨が下った。 |
|
| この勅定ちよくじやう
を承うけたまは りて、六波羅より向かふ大将軍だいしやうぐん
は、左衛門佐さえもんのすけ 重盛しげもり
、三河守みかわのかみ 頼盛よりもり
、常陸守ひたちのかみ 教盛のりもり
、三人なり。その勢ぜい 三千余騎よき
、六条河原ろくでうがはら へ打う
ち出い で、馬むま
の鼻はな を西にし
へ向けてぞ控ひか えたる。重盛、この勢を見廻みまは
して、 「今日の戦ひには、類たぐ
ひなく勝すぐ れぬと思おぼ
へ候ふぞ。今、年号も平治なり。都みやこ
も平なり。我等われら も平氏なり。三事さんじ
相応さうおう して、などか軍いくさ
に勝たざるべき」 と申されければ、兵ども、興きよう
に入い りて勇みあへり。この大勢たいぜい
、河原を上りに、近衛こんゑ 、中御門なかのみかど
、二つの大路おほぢ より、大宮面おほみやおもて
へ押し寄せて見れば、陽明やうめい
、待賢たいけん 、郁芳門いきほうもん
、三つの門をぞ開ひら きける。門の内を見入れたれば、承明じようめい
、建礼けんれい 両門を開いて、大庭おほにわ
には鞍置馬くらおきむま 百疋ぴき
ばかり引き立てたり。大宮の大路に鬨とき
の声三ヶ度聞こえければ、大内おほうち
にも鬨の声をぞ合はせける。紫宸殿ししんでん
の額がく の間ま
にありたりける右衛門督、気色けしき
・事柄ことがら 、もっての外ほか
に替か はりてぞ見えし。色いろ
は草くさ の葉は
のごとくなり。何の用よう に立つべしとも見えざりけり。人なみなみに、馬に乗らんと立ち上がりたれども、膝ひざ
振ふ るひて、歩あゆ
みもやらず。南面なんめん の階きざはし
を下お り煩わづら
ふ。馬の傍かたは らに寄りけれども、片鐙かたあぶみ
を踏ふ みたるばかりにて、草摺くさずり
の音の聞きこ ゆる程ほど
、振るひ出い でて、乗りえず。侍さむらひ
一人いちにん 、つと寄よ
りて、押し上げければ、弓手ゆんで
へ乗り越して、まつ逆さか さまにどうど落ちたりけるを、侍、つと寄よ
りて引き立てければ、顔に砂いさご
ひしと付きて、鼻の先さき 突つ
き欠か き、血ち
朱あけ に流れて、実まこと
におめかへりてぞ見えし。侍ども、あさましながら、をかしげに見るもあり。左馬頭、ただ一目ひとめ
見て、 「臆おく してけり」
と思ひければ、あまりの悪にく
さに、物も言はざりけるが、こらへかねて、 「大臆病だいおくびやう
の者もの 、かかる大事を思おも
ひ立た ちけるよ。ただ事にあらず。大天魔だいてんま
の入い り替か
はりたるを知らずして、与くみ
して憂う き名な
を流さん事よ」 と、つぶやきつぶやき、馬引き寄せて打ち乗り、日華門じつくわもん
へぞ向ひける。 |
この宣旨を承って、六波羅から向かった大将軍は、左衛門佐重盛、三河守頼盛、常陸守教盛の三人である。その勢は三千余騎、六条河原へ出て、馬の鼻を西の方に向けて控えていた。重盛はこの軍勢のさまを見まわして、
「今日の戦いには誠に以って大勢の軍勢が集まったものよ。今の年号も平治、都も平らかに治まっている。我等も平氏である。この三つが応じあって、どうして合戦に勝たないことがあろうか」
と言ったので、兵どもは喜び勇みあった。この大勢が河原を上がりに、近衛、中御門の二つの大路から大宮面に押し寄せたところ、陽明・建礼の二つの門が開いて、大庭には鞍置き馬が百匹ほど引き立てられていた。大宮の大路に合戦合図の声が三度あがったので、大内でもそれに声を合わせた。紫宸殿の額の間にいた右衛門督のご様子はすっかり変わりはてて見えた。顔色はまるで草の葉のようであった。もはや何も出来ないような様子であった。人並みに馬に乗ろうと立ち上がったが、この右衛門督は膝が震えて歩くことさえままならない風情である。南面の階段をおりるのさえむずかしそうであった。馬の傍らに寄ったが、鎧の片方に足をかけただけで、鎧の草摺りの触れ合う音が聞こえるほど身をゆるがしたが、馬にまたがることが出来ない。侍一人がつと寄って、押し上げたところ、向うの左側に乗り越して、まっさかさまにどうと地面にたたきつけられたところを、素早く寄りかかって、引き起こしたところ、顔に砂がびっしりと付いて、鼻の先端が傷つき欠けて、血が真っ赤に流れ出し、顔かたちはすっかり変ってしまっていた。侍どもも、何とも気の毒なこととは思いながら、おかしそうに見ている者もいた。
左馬頭は右衛門督をただ一目見て、おじけづいているのを見てとって、あまりの憎らしさに言葉もかけなかったが、さすがこらえかねて、
「大臆病者めが、こんな大事件をよくも引き起こしたものだ。ただごとではない。大天魔が入れ替わったことに気付かず、こんな大事件に加担して、愚か者の名を流すことよ」
とつぶやきながら、馬を引き寄せて乗りかかり、日華門へ向かった。 |
|
| 『将門記・陸奥話記・保元物語・平治物語』 発行所:小学館 ヨ
リ |