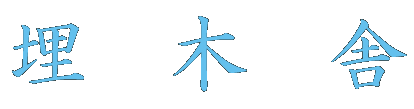に二月十日の曙のころなので、余寒なおきびしく、音羽川の流れも凍ったまま、峰吹く嵐も寒々と吹き渡り、道の氷もまだとけない。またあたり一面薄暗く降る雪のため、どこをどう歩いているのかもわからなかった。子供は母に言われて仕方なく歩くのだけれども、足は腫れあがり、血が出て倒れ伏し、泣き悲しむ、母は、
「ああ、どうしたものか」 と心の中で言うしか何も出来ない。子供の泣く声が高いときは、誰かに聞かれたらと恐れおののき、行き会う人が同情してくれても、何を考えて親切にしてくれるのやらと疑い、心配の種は尽きない。常葉はあまりにもの悲しさに、子供の手を引いて、人家の辺りで暫く休んで、また、足の向かうに任せてさ迷った。あまり、人が通らない時を見はからって、八歳の長子の耳にささやいて、
「どうしてお前たちは聞き分けが悪いの。ここは敵の本拠、六波羅という所よ。泣き出すと人に怪しまれ、左馬頭の子供として捕らえられて、首を斬られてしまうのですよ。命が惜しかったら、泣いてはいけませんよ。たとい腹の中にいる時でも、立派な子供はお母さんの言う事を聞くというのじゃないの。まして、お前たちは七つ、八つになるのですよ。どういてこれぐらいのことがわからないの」
と泣き泣き諭したところ、八歳になる子はさすが大人びて聞き分けがよく、母に諫められた後は、涙はかわかずに流しても、声を出して泣くことはしなかった。しかし、六歳の子はもと通り、倒れ込んでは
「寒い、冷たい」 と泣き悲しんだ。常葉は二歳の幼児を懐中に抱いていることとて、六歳の子を抱くわけにはいかない。しかたなく、手をつないで、ともかく歩き出した。夫左馬頭が討たれたと聞いて以来、湯水さえも口にしなくなったので、蜻蛉のように衰えてしまって心配続きで、それに、子供を連れての逃避行の歎きが加わり、命終わるかに思われた。しかし、子供の行く末が気がかりでどうにか気を取り直し、春の日は長いといっても、この一日をどう過ごしたかうつろなまま、夕刻、入相の鐘を聞く時刻に伏見の里に着いた。
日は暮れ果て、夜に入っても、立ち寄ることのできそうな家はない。山陰の道の辺に、人家が見えるが、
「敵の家だろうか」 「この家も六波羅の家人などが住んでいるのだろうか」 と心配し出すと、宿を借りることも出来ない。 「思うに任せない幼い子の母となったばかりに、こんな歎きに遭わねばならないとは」
と泣くよりほかなかった。そこで、野山にも恐ろしい者が多いということなので、道の辺の棘の下で、親子四人は手を取り合って、お互い体を寄せあって泣いていた。 |