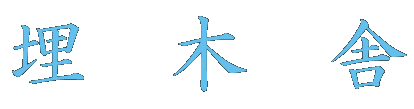| 近付
ならぬ人さへ、忌日きにち 々々きにち
に樒しきみ 折立おりた
て、この女を弔と ひけるに、その契ちぎ
りを込めし若衆わかしゆ は、いかにして、最後を尋ね問はざる事の不思議と、諸人沙汰さが
し侍はべ る折節をりふし
、吉三郎は、この女に心地悩みて前後を弁わきま
へず、憂世うきよ の限りと見えて便り少なく、現うつつ
のごとくなれば、人々の心得にて、この事を知らせなば、よもや命もあるべきか、 「常々申せし言葉の末、身の取置とりおき
までして、最後さいご の程を待ち居しに、思へば人の命や」
と、首尾しゆび よしなに申しなして、
「今日けふ 明日あす
の内には、その人ここにましまして、思ふままなる御見」 などいひけるにぞ、一入ひとしほ
心を取り直し、与へる薬を外ほか
になして、 「君よ恋し、その人まだか」 と、そぞろ言ごと
いふ程こそあれ、 「知らずや、今日は、はや三十五日」 と、吉三郎にはかくして、その女弔とむら
ひける。それより四十九日の餅盛もちもり
など、お七親類、御寺みてら に参りて、
「せめてその恋人を見せ給へ」 と嘆きぬ。 |
何の縁もない人でさえ、忌日ごとに樒しきみを折り立てて、お七を弔ったのに、その身も心も許した相手の若衆は、どうしてお七の臨終を見とどけ、亡き跡を弔とむら
わないのか、不思議なことだと世間で噂うわさ
をした。ちょうどそのころ、吉三郎は、お七を思いつめて病気になり、前後不覚の有様、これで命も終りかと見えて心細く、まるで夢うつつの状態だったので、付き添いの人々の配慮から、お七の死を知らせたら、とても命はあるまい。
「常々口にする言葉のはしばしにも覚悟のほどは知られ、身のまわりの始末までして処刑を待っていたが、ふとしたことでお七殿は助かった。人の命というものはわからぬものだ」
と、うまく言いつくろい、 「今日明日のうちにはお七殿がここにいらっしゃって、思うままにご対面ができましょう」 と言ったので、一段と心を取り直し、与える薬はほかにして、
「お七殿が恋しい。あの方はまだ来られぬか」 と、譫言うわごと
をいうのだが、 「知らぬことはしかたがない。今日はもうお七の三十五日だ」 と、吉三郎には隠してその人を弔ったのであった。それから四十九日の餅盛もちもり
りなどして、お七の親類はお寺に参り、 「せめて一目、お七の恋人をお見せください」 と嘆願した。 |
|
| 様子を語りて、
「又もあはれを見給ふなれば、よしよしその通りに」 と、道理を責せ
めければ、 「石流さすが 人たる人なれば、この事聞きながら、よもやながらへ給ふまじ。深くつつみて、病気も恙つつが
なき身の折節をりふし 、お七が申し残せし事どもを語り慰めて、我が子の形見に、それなりとも思ひはらしに」
と、卒塔婆そとば 書き立てて、手向たむ
けの水も泪なみだ に乾かぬ石こそ、亡き人の姿かと、跡に残りし親の身、無常むじやう
の習ひとて、これ逆さまの世や。 |
寺では吉三郎の様子を話して、
「お会いになると、再び悲しい思いをされねばなりません。まあまあどうぞこのままにして会わずにおいて下さい」 と、道理を尽くして話したので、 「吉三郎殿もさすがに立派な育ちの方であるから、このことを聞かれたら、まさか生きてはござるまい。今は深く隠しておいて、元気になられたその折に、お七が申し残していった事など、お話して慰めましょう。では、我が子の形見に、これなりとも立てて、親の思いを晴らすたねにいたしましょう」
と、卒塔婆そとば を書いて立て、手向たむ
けの水を泣く泣く供え、その泪に濡ぬ
れて乾かぬ墓石こそ、今は亡な
き娘の面影かと思うと、後に残った親の身の悲しさ、老少ろうしょう
不定ふじょう は世の習いとて、親が子を弔うとはまったくさかさまの世であった。
| | 『井原西鶴集 一』 佼注・訳者;暉峻
康隆・相賀 徹夫 発行所:小学館 ヨリ |
|