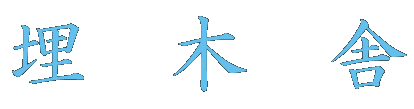| やうやう更
け過ぎて、人皆おのづから寝入りて、鼾いびき
は軒のき の玉水たまみづ
の音をあらそひ、雨戸あまど の隙間すきま
より、月の光もありなしに静かなる折節おりふし
、客殿きやくでん を忍び出けるに、身にふるひ出て足元あしもと
も定めかね、枕ゆたかに臥ふ したる人の腰骨こしぼね
を踏みて、魂消ゆるがごとく、胸痛く上気じやうき
して、物いはれず、手を合あは
して拝みしに、この者我われ を咎とが
めざるを不思議と、心をとめて詠なが
めけるに、食めし 炊た
かせける女の梅といふ下子げす
なり。 |
しだいに夜も更けてゆき、皆いつの間にか眠ってしまって、人々の鼾いびき
は軒の雨だれと音を争い、雨戸の隙間からさす月の光もあるかなしに、あたりが静かになったころ、お七は客間を忍び出たが、身震いがしてきて足元も定まらず、気持ちよく寝込んでいる人の腰骨を踏みつけて、魂も消えるばかり驚いた。胸がどきどきのぼせてしまってお詫わ
びの言葉も出ず、ただ手を合わせて拝んだところ、先方では何も咎とが
めないので不思議だと、よく注意して見ると、それは、飯めし
炊た きの梅という下女であった。
|
|
それを乗のり
越こ えて行くを、この女、裾すそ
を引留ひきとど めける程に、又、胸むね
騒ぎして、 「我留われとど むるか」
と思へば、さになあらず、小半紙一折ひとおり
手に渡しける。 「さてもさても、いたづら仕付しつ
けて、かかるいそがしき折柄おりがら
も気の付きたる女ぞ」 とうれしく、方丈はうぢやう
に行きて見れども、かの児人せうじん
の寝姿ねすがた 見えねば、悲しくなって台所に出ければ、姥うば
目覚さま し、 「今宵こよひ
鼠ねずみ めは」 とつぶやく片手に、椎茸しひたけ
の煮しめ・揚あ げ麩ふ
・葛袋くずぶくろ など取とり
置お くもをかし。
しばしあって我われ
を見付けて、 「吉三郎殿の寝所ねどころ
は、そのその小こ 坊主ばうず
とひとつに三畳敷さんでふじき
に」 と、肩たたいて小話ささや
きける。思ひの外ほか なる情なさけ
知り、 「寺には惜しや」 と、いとしくなりて、してある紫むらさき
鹿か の子こ
の帯ときて取らし、姥が教へるにまかせ行くに、夜よ
や八や つ頃なるべし、常香盤じたうかうばん
の鈴落ちて、響き渡る事しばらくなり。 |
その女の上をまたいで行こうとすると、この女は裾すそ
を引っ張ってとめるので、また胸がどきどきして、 「自分を引き留めようとするのか」 と思うと、そうではなくて、小半紙を一折手渡ししてくれた。 「さてもさても色事をしなれているので、こんな気ぜわしい場合にも、よく気のつく女だ」
と、うれしく思いながら、方丈へ行ってみたけれども、かの若衆の寝姿が見えないので、悲しくなって台所に出て行ったところ、姥うば
が目を覚まして、 「今夜は鼠ねずみ
のやつがうるさくて」 とつぶやきながら、椎茸しいたけ
の煮しめ、揚あ げ麩ふ
・葛袋くずぶくろ などを取りかたづけるのもおかしかった。
しばらくして自分を見つけ、 「吉三郎殿の寝所は、それあそこの、小坊主とひとつに三畳敷に」 と、肩をたたいてささやいた。これは思いのほかの情け知り、
「寺などに置くのは惜しいもの」 と、かわいくなって、しめていた紫鹿か
の子こ の帯を解いて与え、姥が教えたとおりに行くと、もう夜は八つ
(午前二時) ごろであろう。常香盤じょうこうばん
の鈴が落ちて、その音がしばらく響き渡った。 | | 『井原西鶴集
一』 佼注・訳者;暉峻 康隆・相賀 徹夫 発行所:小学館 ヨリ |
|