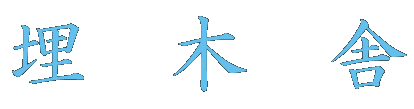| 春の雨、玉にもぬける柳原
のあたりより参りけるのよし、十五日の夜半やはん
に、外門そともん あらけなく叩たた
くにぞ、僧中そうぢゆう 夢驚かし聞きけるに、
「米屋こめや の八左衛門長病ちやうびやう
なりしが、今宵こよひ 相あひ
果は て申されしに、思ひまうけし死人しにん
なれば、夜のうちに野辺のべ へ送り申したき」
との使つかひ なり。 |
春の雨が柳の枝に玉を貫いたように見える正月十五日の夜半に、柳原やなぎはら
のあたりから参りましたと言って、吉祥寺の外門を乱暴に叩く者があったので、寺じゅうの僧が皆目を覚まして聞いたところ、 「米屋の八左衛門が長らく病気でしたが、今夜あい果てました。かねてから覚悟していた死人のことですから、夜の明けぬうちに野辺の送りをいたしとうございます」
という使いであった。 |
|
| 出家しゆつけ
の役なれば、あまたの法師召し連れられ、晴間はれま
を待たず、傘からかさ をとりどりに、御寺みてら
を出いで て行き給ひし跡は、七十に余りし庫裏くり
姥うば ひとり。十二、三なる新しん
発意ばち 一人いちにん
、赤犬ばかり、残る物とて松の風淋しく、虫出の神鳴かみなり
響き渡り、いづれも驚きて、姥は年越としこし
の夜の煎いり 大豆まめ
出すなど、天井てんじやう のある小座敷たづねて身をひそめける。 |
これは僧侶の役目なので、長老様は大勢の法師たちを引連れられて、雨の晴れ間も待たず、手の手に傘かさ
を持って出て行かれたあとは、七十を越えた庫裡くり
姥うば 一人、十二、三歳の新しん
発意ぼち 一人と赤犬ばかり、そのほかに残るものとては松の風が寂さび
しく吹いているだけであった。その折、虫出しの雷が鳴り響いたので、皆々びっくりして目を覚まし、姥は雷除よ
けに節分の夜の煎い り豆を取り出したり、人々は天井のある小座敷を捜して身をひそめたりした。 |
|
| 母の親、子を思う道に迷ひ、我われ
をいたはり、夜着よぎ の下へ引寄ひきよ
せ、きびしく鳴る時は、 「耳ふさげ」 など心を付け給ひける。女の身なれば、恐ろしさ限りもなかりき。されども 「吉三郎に会ふべき首尾しゆび
、今宵こよひ ならでは」 と思ふ下心したごころ
ありて、 「さても浮世うきよ
の人、何とて鳴神なるかみ を恐れけるぞ。捨ててから命、少しも我は恐ろしからず」
と、女の強がらずしてよき事に、無用の言葉、末々すえずえ
の女どもまでこれを謗そし りける。
|
お七の母親は、子を思う親心のあまり、娘をいたわって、自分の夜着の下に引き寄せ、ひどく鳴る時は、
「耳をふさぎなさい」 などと気をつけてやられた。お七も女の身であるから、恐ろしくてたまらなかったけれども、 「吉三郎に会う機会は今宵こよい
を逃してはない」 と内心で思っているので、 「さてさて世間の人は、どうして雷など恐れるのでしょう。捨てたところでたかが命一つ、わたしはちっともこわくない」
と、女が強がる必要もないことに、余計なことを言ったので、下々の女どもまで陰口をきいて謗そし
るのであった | | 『井原西鶴集
一』 佼注・訳者;暉峻 康隆・相賀 徹夫 発行所:小学館 ヨリ |
|