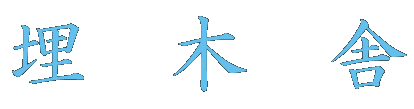お夏は見ずして、独
り幕に残りて、虫歯の痛むなど、少しなやむ風情ふぜい
に、袖枕そでまくら 取乱とりみだ
して、帯はしやらほどけをそのままに、あまたのぬぎ替かへ
小袖こそで を、つみ重ねたる物陰に、うつつなき空鼾そらいびき
心にくし。 「かかる時、早業はやわざ
の首尾しゆび もがな」 と気のつく事、町女房はまたあるまじき粹様すいさま
なり。
清十郎、お夏ばかり残りおはしけるに心を付け、松むら松むらとしげき後道うしろみち
よりまはりければ、お夏まねきて、結髪ゆひがみ
のほどくるもかまはず、物もいはず、両人鼻息せはしく、胸ばかりをどらして、幕の人見ひとみ
より目をはなさず、兄嫁こはく、跡あと
の方かた へは心もつかず、起きさまに見れば、柴しば
人、一荷いつか を下して鎌を握りしめ、ふんどし動かし、
「あれは」 といふやうなる顔かほ
つきして、心地よげに見て居るとも知らず、誠に頭かしら
かくしてや尻とかや。 |
ところでお夏は、その獅子舞にも興味を示さず、ひとり幕の内に残り、虫歯が痛むと称してつらそうな風情をして、着替え用の小袖をつみ重ねた袖枕をしていた。帯はしどけなく解けかかり、うつつなき空鼾をたてるのも心にくいが、こういうどさくさのまぎれに早わざの情事が出来ぬものかと、思いつくあたりは、素人の町娘にめったに見られない粹人ぶりである。
清十郎もまた、お夏だけが残っているのに気づき、松の生い茂るうしろの道を迂回して姿をあらわした。はっとしたお夏が清十郎を手招きする。
「やっと二人きりになれた」
と両人ともに同じ思いであるものの、口には出さず、ひしと抱き合って鼻息せわしく、唇をあわせるのも夢のうちのあわただしさだった。というのは、兄嫁に見つかることを怖れて、幕の人見穴から目を離さなかったからで、相擁しつつも胸がどきどきして落ち着かない逢瀬であった。
ところがさて、髪のあまりの乱れが気になってお夏がふと身を起こすと、幕のむこうの端に木こりがいて、荷をおろして鎌をにぎりしめ、にやにやしてこちらを眺めているではないか。清十郎が立って行って、その木こりを追い払いをしたものの、
「頭かくして尻かくさず」 の成り行きではあった。 |
|
この獅子舞、清十郎の中より出しを見て、かんじんのおもしろい半ばにて止めけるを、見物興覚きようさ
めて、残り多きこと山々に霞深く、夕日かたぶけば、よろづを仕舞しま
うて姫路ひめぢ に帰る。思ひなしか、はやお夏、腰つきひらたくなりぬ。
清十郎、跡あと
に下さ がりて、獅子舞の役人に、
「今日は、お陰かげ お陰」 といへるを聞けば、この大神楽だいかぐら
は作り物にして、手管てくだ のために出しけるとは、かしこき神も知らせ給ふまじ。ましてや、走り知恵なる兄嫁なんどが何として知るべし。 |
一方、賑やかな獅子舞の芸人たちは、清十郎が幕の内より出て来たのを見ると、曲芸が面白い最中であるにもかかわらず、やめてしまった。見物人はがっかりと興ざめして四散し、心残りも山々だったが、やがて見渡すほんものの山々にも夕霞が深くたなびき、日が傾いたので、但馬屋一行はそそくさと片づけものをして、姫路への帰途についた。
なにくわぬ顔をしているけれど。思いなしかお夏の腰つきは早くも平たくなったようだ。そして、清十郎があとに残って、獅子舞の芸人たちに
「今日はご苦労さん。ありがとうよ」 というところを見ると、この大神楽興行は清十郎が仕組んだものらしい。
神様さえ神楽興行が密会の手段として用いられるのをご存知ないのだから、まして浅知恵の兄嫁が気づくはずはなかった。 | | 『現代訳
西鶴名作選』 訳者:福島忠利 発行所:古川書房 ヨ リ |
|