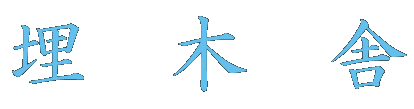春の海しづかに、宝舟の波枕
、室津むろつ
は、にぎはえる大湊みなと
なり。
ここに酒つくれる商人ばいにん
に、和泉いづみ
清左衛門といふあり。家栄えて、よろづに不足なし。しかも、男子に清十郎とて、自然と生まれつきて、昔男をうつし絵にも増まさ
り、そのさまうるはしく、女の好す
きぬる風俗、十四の秋より色道しきだう
に身をなし、この津の遊女八十七人ありしを、いづれか会はざるはなし。誓紙せいし
千束ちづか
につもり、爪は手箱にあまり、切らせし黒髪は大綱おほづな
になはせける。これには悋気りんき
深き女もつながるべし。毎日の届文とどけぶみ
ひとつの山をなし、紋付もんつき
の送り小袖そのままに重ね捨てし。三途さんづ
川の姥うば
も、これを見たらば欲を離れ、高麗橋かうらいばし
の古手屋も、ねうちはなるまじ。浮世蔵うきよぐら
と、戸前とまへ
に書付かきつ
けてつめ置きける。
「このたはけ、いつの世にあがりを請う
くべし、追付おつつ
け勘当かんがう
帳に付けてしまふべし」
と、見る人これを嘆きしに、止や
めがたきはこの道、その頃は、皆川といへる女郎に相あひ
馴な
れ、大方おほかた
ならず命に掛けて、人の謗そし
り、世の取とり
沙汰さた
なんとも思はず、月夜に挑灯てうちん
を昼ともさせ、座敷の立具たてぐ
さし籠め、昼のない国をして遊ぶ所に、こざかしき太鼓たいこ
持も
ちをあまた集めて、番太が拍子木ひやうしぎ
、蝙蝠かうふり
の鳴きまね、遣手やりて
に門茶かどちや
を焼かせて、歌念仏を申し、死にもせぬ久五郎がためとて、尊霊そんりやう
の棚たな
を祭り、楊枝やうじ
燃やして送り火の影、夜よる
するほどの事をしつくして後は、世界の図づ
にある裸島はだかじま
とて、家内やうち
のこらず、女郎はいやがれど、無理に帷子かたびら
ぬがせて、肌の見ゆるを恥ぢける。中にも、吉崎よしさき
といへる十五かこひ
女郎、年月かくし来きた
りし腰骨の白なまづ見付けて、
「生きながらの弁財天べんざいてん
様」 と、座中拝おが
みて興覚さ
めける。その外ほか
、気をつくる程見苦しく、後は次第にしらけてをかしからず。 |