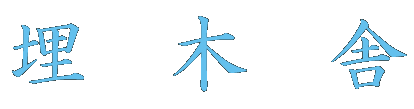その後、鳥羽院の北面
なりける紀伊守きいのかみ 範通のりみち
と云い ひし者、道心だうしん
を発おこ し、出家しゆつけ
遁世とんぜい して、蓮誉れんよ
と名乗りて、諸国一見しよこくいつけん
の聖ひじり となりたりけるが、在俗ざいぞく
の時は、陪従べいじゆう にて、内侍所ないじどころ
の御み 神楽かぐら
に参りけるに、それかそれにあらざるほどにて、御目にかかるまではなれけれども、新院の御事こと
伝へ承りて、哀あは れにゆかしく思おぼ
えければ、遥々はるばる と八重やへ
の塩路しほぢ に赴き、讃岐に訪ね参りたり。
御所の体てい
見奉れば、目も当てられず、あさましげなる御有様ありさま
なり。 「蛮夷ばんい 宮門きゆうもん
を守まも り、荊棘けいきよく
道を塞ふさ げり。花鳥かてう
風月ふうげつ の興あるべき所ならねば、何事にかは御心を慰なぐさ
ませたまふべき。雪の朝あした
、雨の夜よ 、哀れをも、誰たれ
かは訪とぶら ひ参まゐ
るべき」 と、思ひ続けて、藤ふぢ
の衣ころも の袖そで
萎しを れ終は
ててぞ立てりける。。相あひ 構かま
へて、御所の内へ入らんと伺うかが
ひけれども、門守護もんしゆご
の兵士ひやうじ きびしかりければ、空しく御所のあたりを立ち舞ひ立ち舞ひしけれども、
「あはれ」 とだにも云ふ人もなし。僅わづ
かに音する物とては、岸きし 打う
つ浪なみ 、松まつ
吹ふ く風、沖の鴎かもめ
の誘さそ ふ声、うらやましくぞおぼえける。日暮く
れ、夜よ に入るままに、いとど心も澄み渡りければ、笛吹き、朗詠らうえい
して、泣く泣く心を慰みけり。 |
| 幽思いうし
窮きは まらず、巷ちまた
に人無き処ところ 、愁腸しうちやう
断た たんと欲す、閑窓かんさう
月ある時 |
|
| 月の出潮でしほ
の浪の音、孤客こかく の棹さお
のいづくをこそとは知らねども、浦吹く風に類たぐ
ひ来き て、心細さは限りもなし。 |
その後、鳥羽院の北面の武士であった紀伊守範通という者が、道心を起こし、出家遁世して、蓮誉と名乗り、諸国遍歴の聖となったが、在俗の時は、陪従で、内侍所の御神楽に従事したが、とりたてていうほどの身分ではないので、お目にかかることはなかったが、新院のことを承って、悲しく慕わしく思い、はるばると海路旅を重ね、讃岐まで訪ねてきた。御所の様子をうかがって見ると、目もあてられぬ、嘆かわしいたたずまいであった。
「あらあらしい武士が門を守り、いばらが道を塞いでいる。花鳥風月の趣ある所でもなく、御心を慰めるようなものは何もない。雪の朝、雨の夜、尋ねて来る者は誰もいないことだろう」
と思い続けて、着ている粗末な衣服を涙で濡らした。どうにかして御所の中へ入ろうとしたが、武士が門をきびしく守護していたので、むなしく御所の辺りをうろうろするだけだが、
「どうした」 とさえ、声をかけてくれる人はいない。わずかに、岸打つ波、松吹く風、沖の鴎の声が聞こえて来るだけである。日も暮れ果てて、夜に入って、ますます寂しくなり、笛を吹き、朗詠をして、泣く泣く心をなぐさめた。 | | | との詩にある通り、波の音や、棹の音がどこからともなく浦吹く風とともに聞こえて来て、心細さは言いようもない。 |
|
| 夜よ
の更ふ け行ゆ
くままに、月傾かたぶ き、風冷すず
しかりけれども、ただつくづくと立ちて、袖そで
を絞しぼ りける処ところ
に、黒ばんだる水干すいかん 打う
ち掛か けたる人、月に誘さそ
はれけるにや、御所の内より立た
ち出い でたり。蓮誉、嬉うれ
しく 思おぼ えて、事の心を歎なげ
きければ、この人、愍あはれ みて、連つ
れて紛まぎ れ入りにけり。蓮誉、御所へ参るべきならねば、板に一首の歌を書きて、
「これ天聴てんちやう に達してたまはらん」
と云ひければ、この人、情けありけるにや、この由を奏する程に、新院しんいん
叡覧えいらん なりけるに、一首の歌をぞ書きたりける。 |
| 『朝倉あさくら
や 木き の丸殿まろどの
に入りながら 君に知られで 帰る悲しさ』 |
|
| 院もあはれに思おぼ
し召め しければ、 「御前近う召されて、都の事をも聞きこ
し召し、昔のゆかしさをもたづねばや」 と思し召せれけれども、それもさすがにて、ただ御返事ぺんじ
ばかりぞありける。 |
| 『朝倉や ただいたづらに 返すとも 釣つ
りする海士あま の 音ね
をのみぞ泣く』 |
|
| 蓮誉、これを賜たま
はりて、屓おひ の底に納め、泣く泣く都へ上りけり。 |
| 夜も更けて、月も傾き、風は冷たくなったが、ただ心寂しく立ち尽くして、悲しみの涙に濡れているところに、黒ばんだ水干をまとった人が、月の美しさに誘われ出したものか、御所から出て来た。蓮誉はうれしく思い、事情を訴えたところ、この人はあわれがって、御所に連れて紛れ込ませてくれた。蓮誉は、さすが新院に直にお会いすることもならず、板に一首の和歌を書き付けて、
「これを新院のご覧に入れて下さい」 と願ったところ、この人は情けある人で、新院に伝えてくれた。新院がこれをご覧になったところ、和歌が一首書かれていた。 | | 『せっかく新院の寂しいお住まい所を尋ねながら、お会いすることもかなわず帰らねばならないことの悲しさよ』 |
| | 院もかわいそうに思われ、
「御前近く召し寄せて、都のことも聞きたく、また、昔の思い出話もしたいものだ」 と心が動いたが、さすがにそれははばかられて、ただ、お返事だけが伝えられた。 | | 『会うこともならず、せっかくの来訪を無駄にしてしまったが、そなたの厚意は身にしみてうれしく、ただ泣くばかり』 |
| | 蓮誉はこの御歌をいただいて、笈の底深く大事に納めて、泣く泣く都に上った。 |
|
| その後、新院、あまりに島の御籠居ろうきよ
を御歎きありければ、国司・官人くわんにん
等が計らひとして、志度しど の道場の辺へん
、鼓つづみ の岡おか
といふ所に、御所しつろうて、渡し奉る。かくて明あか
し暮させたまう程に、いやしき賤しづ
の男お ・賤しづ
の女め めに至るまで、外ほか
にて哀れはかけ進まゐ らせけれども、世に恐れをなして、参まゐ
り付つ く者もなし。さるにつけては、
「近く召し仕つか へ、昵むつま
じく 思おぼ し 召め
されし人々、せめて一両輩いちりやうはい
もあらましかば」 と思し召されし折々の御遊ぎよいう
も、所々の御幸ごかう 、花の朝あした
、月の夜よ 、詩歌管絃しいかくわんげん
の御遊あそび 、五節御賀ごせちのおんが
、豊明とよのあかり 、かように興ありし事ども、只今のやうに思おぼ
し召め し出い
でられて、とにもかくにも、ただ御涙の暇ひま
もなくぞ思し召されける。 |
| その後、新院がこの島の御籠居をお嘆きになるので、国司や官人らが取り計らって、志度の道場の辺、鼓の岡という所に新しく御所を準備して、お移りになった。ここでお過ごしになる間、下々の賤の男、賤の女に至るまで、御所の外では敬意を表することはあっても、世間をはばかって御所にうかがう者はいない。それにつけても、
「そば近くに仕えて、親しく接することのできる者が一人二人でもいたら」 と願うもののかなわず、都での折々の御遊、所々の御幸、花の朝、月の夜、あるいは詩歌管絃の御遊、五節の御賀、豊明など、これら楽しかったことを、つい今のように思い出されて、ともかく、ただただ涙がちになる。 |
|
| 『将門記・陸奥話記・保元物語・平治物語』 発行所:小学館 ヨ
リ |