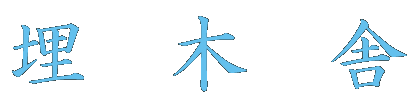その日、徳大寺
公能 の家へ臨んでいた伊通
、 基実 、清盛
の三人の客は、やがて牛車
をつらねて、門を出て来た。
陽
はまだ高く、秋 更
けた空に、赤とんぼが黒い塵埃
みたいに見える。
街の人びとは、このごろよく見かけtる大官たちの頻繁
な往来に、また政変か、戦乱の前ぶれでもないかと、すぐ不安な眼をそばだてた。
伊通、基実は、まっすぐに、宮門へ向かって帰ったが、清盛の牛車だけは、途中でわかれた。かれはその足で、八条堀川の仮御所におられる後白河上皇をお訪ねしていた。
「清盛。どう在
せられたぞ。ここ数日も、ぶさたではなかったか」
上皇は、御座
近々 と、かれを招き入れて、あいそをいわれた。ほかの伺候者と比べれば、格別なお親しさの表示である。
清盛も、ひとりの場合に限っては、上皇のおくつろぎに応じて、ほどよく儀礼も略し、肩のこらないお相手となることに、きめていた。
「いやもう、ほとほと多忙なのです。一参議のわたくしに過ぎぬはずなのに、何分、軍に関した政務といえば、各省からみな持って来ますし、去年、兵燹
にかかった三条の仙洞
御所 も、年内には、
渡御 を仰がれるまでに、工事も進めたいやらで」
「おことの身はいま幾つあっても足りまい。さあれ、 滋子
が淋 しそうな。── 滋子のためにも、身二つとなるまでは、おりおり、姿を見せてやるがよい」
「そうですか。初のお妊娠
なので、女御 にも、お気が張るのでございましょう。・・・・が、御順調に、月を追うておられますか」
「しごく健
やかには見ゆる。奥へ通って、会うてやられるか」
「いえ、きょうは」
と、清盛は、あわてて御辞退した。
そして、ほかに帯びている緊急な秘命を、このうるわしいごきげんにたいして、どう口を切ったものかと、ちょっと思案顔であった。
上皇と清盛との間は、ここ一年足らずのうちに、君臣以上な密度をもって、急速な親しみを加えていた。
もともと、後白河は、少納言信西
の政治的手腕を高く買っておられたので、その信西と厚かった清盛も、自然、前々から、よく見てはおられた。
けれど、なんといっても、上皇の御信任が、特に清盛へ傾いて来たのは、平治の乱が境である。あの直後からといっていい。
「信西の亡
き後は、この者こそ」
となすお心のものが、清盛にも、映
っていた。
当時。── 三条烏丸の仙洞御所は焼失してしまったので、御造営の成るまで、上皇は、八条堀川を仮の御所としておられた。しかし、ここは、藤
顕家 の館で、何かにつけて、御不便はいうまでもない。一時的ではあったが、あの戦乱前後、極度な狼狽
ぶりに、人びとは自分自分もことだけしか考えられなかった。後でこそ、おかしいようなものだが、上皇の御身辺さえ、朝夕、侍者
の手を欠くほどだった。
そのころ、滋子
は、上皇の御給仕に、上がったのである。
彼女は、清盛の妻時子の、いちばん末の妹であった。清盛のはからいによるのはいうまでもない。
その滋子が、いつか上皇のおん胤
を宿して、産み月は十一月ごろと想定されているのである。おん帯の御式
を前に、女御 のに昇せられ、いまはかくれもない後白河の寵姫
として、内にも表にも、重んぜられている身であった。
はからずも、このことは、上皇にとっても、
(清盛と結び、清盛の武力を用うるに、よい方便)
というかねてのお考えに合致していたし、また、清盛にとっても、
(思わざる吉事よ。一門の倖せ、これに過ぐるはない)
と、ひそかに、大祝して、自然、
“隴 ヲ得テ蜀
ヲ望ム” の心を抱いたであろうことも、察するに難くない。
いったい、後白河は、天性、政治がお好きであった。信西入道をお用いになっていたころから、よく信西の言を容
れ、地方制度や、中央の古制に、改革の新味を示されたことは事実である。
その点、かっての仙洞、── 院政初期における白河法皇の御性格と、どこか似かようておいでだった。
現
仙洞の後白河もまた、院政政治に ── というよりも今の御地位に ── その嗜好
と自信を多分にお持ちになっていた。ということは、権勢欲にお強いろも言えるのである。
信西は亡
くも、将来は清盛を用いて、おおいにその御抱負を振わんとしておられる御容子が常にうかがわれる。
しかし、今のところ、院はまだ仮御所の状態だし、また信西始め、信西系の諸公卿は、ことごとく、あえなく果てたり流罪になったりdr、上皇の御身辺は、はなはだお
淋 しい。── 二条朝廷による諸政の進行や人事の裁断などを、見られるにつけ、何か、おだやかでない御心だった。
そうしたわびしいお気持から、上皇には、館
の桟敷 へ出られて、よく、街
の往来など見物しては、無聊
を慰めておられたりしたものだった。
── と、それをすぐ、例の惟方
や経宗が、朝廷に告げ口して、二条天皇のおん名をかり、勅諚
と称して、御 桟敷
を鎖 してしまった。
このときの御立腹はひどかった、すぐ、清盛を召して、実相を糺
された。そして惟方、経宗を捕らえさせ、即日、二人を遠国へ追放したのであった。それでやっと事件は一応済んだように、その時は見えもした。けれど以来、二条天皇と後白河とのいん仲は、ことごとにおもしろくない対立を示して来た。
朝廷でよく用いられる者は、院からは排され、上皇が信任される臣は、朝廷へ出ると白眼視された。 |