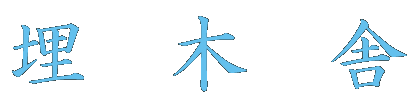こういう御不和のかもされている時に ──この春以来
── さらにまた、べつな難しい問題が、内在して来た。
例の ── 天皇二条が、お人もあろうに、太皇太后
の多子を恋されて、なんとしても、入内
を求めてやまない
── あの、やっかい極まる問題が、なお、未解決のまま、秋も暮れんとしていたのである。
「いけない」
上皇は、初めから、お耳も、かされなかった。
「先々帝の后
を、今上の皇后として、入内せしめるなどという例が、異朝
は知らず、わが朝
にあったか」
という御意見である。
当然、重臣すべての、考えも、同じであった。──
そういう畸形
な恋愛や結婚は、下層庶民のあいだにも、おそらく、不倫
として、顰蹙
されるにきまっている。 「いわんや、天子たるお方においておや」 というのが、上卿
すべての者の憂慮するところでもあった。
けれど、天皇は、頑
として、おあきらめにならない。
どうしても!
と仰せられる。
果ては、直々
、多子の父、大徳寺公能
を召されて、
「多子を、入内させよ」
と、おせがみになる。
いや、おことばは、勅である。
しかし、公能も、
「こればかりは・・・・」
と、世上の非難も恐れて、再三、固辞した。春も夏もこの秋も、門を閉じて一切顔を見せないほど、公能は、拝辞し通して来たのだった。
が、天皇は、お聞きわけなさらない。
十八歳という御年齢でもあるし、また
「およそ “勅” として、行われぬ事のあるべきや」 という強い先天的な御信念もおありなのだ。
「おことたちは、朕
のこの悩み、劫火
の苦しみを、ただ見ておるのか。朕をして、懊悩
に、死なしむるのか」
こういう仰せまで受けては、上卿たちも、いたずらに額を寄せて、密議と溜息ばかりを繰り返してもいられなかった。
今日。──
太政大臣伊通
、左大臣基実
、参議清盛の三人が、牛車を連ねて、物々しくも、大炊
御門
の大徳寺家を訪うたのも、じつに、その最後の 「勅」 を秘めて、
「まず、あなたから、うんと、御承諾してください。そして、父たるあなたから、多子の君も、説きつけていただきたい」
と、ひざ詰めの交渉に行ったものであった。
その結果、公能もついに、
「勅なれば、これ以上、お断りしようもない。自分としては、お受けいたすが・・・・?」
というところまで、交渉は、進んだ。
「──
けれどなお、多子は、何と言うかわかりません。それと、上皇の御意
も、いかがあろうや、これもはなはだ事むずかしく思われますが」
と、公能は、なおいい濁した。
そのさい、伊通と基実は、
「上皇のお許しを得るには、六波羅殿のほかにお人はいない。なんとか、御心の解けるように、あなたから、内奏していただきたいが」
と、清盛は、切に頼まれた。
事実、清盛自身も、いま、上皇に対して、それの言えるような者は、自分以外にないと思っている。
──
で、伊通、基実に別れた足で、ただちに、八条堀川へ来たわけであった。そして夜にはいるまで、その問題について、上皇へお話ししてみた。
「いや、清盛。せっかく、おことたちも、心をくだいて、案じてくれているが、この儀だけは、いかに主上の仰せでも、かなうまい。──
世上の聞こえ、人倫のうえにも、いかがあろうぞ。── 天子の父としてこれが許せようか」
上皇はいつになく冷静だった。ご機嫌も決して悪くはない。けれど、太皇太后
の后返
り
── 二代の后
たることだけは ── 依然お聞き入れのもようもない。
そしてすぐ話は、滋子
のことに移り、また滋子の近く産む御子
が、女子か男子か、などということの方へ、反れがちであった。
それもまた、御無理ではない。
後白河御自身とて、御年はまだ三十八。ほんとの、壮年期でいらっしゃる。
(・・・・・はて、弱った)
という清盛の顔つきだった。──
しかし上皇のお気持もまたよくわかる。この壮年の父君が、まだいと若いお子に対し ── 主上とあがめられていられるにしても ── 骨肉の父として、不倫な恋愛を、人いちばい、不快に感じられるのは、当然である。他人には想像も及ばないほど、肉親のそういう行為には、自分を除外した妙な潔癖の出るものである。
多くの子を持ち、また、父の子でもあった清盛には、理を超
えた、そういう感情も身にひきくらべて、理解された。
で、かれは、むなしく、退出しようときめた。けれど退
がるまぎわに、もう一度、かれはこう奏して立ち帰った。
「何せい、主上は、御純情なのです。それは、われらの世俗流な者から見れば、びっくりするほど、御自身を偽らない、天真爛漫な呼吸を遊ばしている御生命なのです。決して、お庇
いしていうのではありません。・・・・それだけに、いとど、このごろのおん窶
れは、世の人の恋
痩
せなどとも違って、ほんとに、お可哀そうに拝されまする。・・・・なお、清盛からも、お諫
めはしてみますが、あわれ、玉体をそこね給うて、御一命にもかかわりはしまいか・・・・と、それだけが、なんとも、お案じ申されてなりませぬ」
|