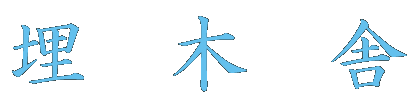一介
の公卿儒官から、にわかに、朝権の中心に立った少納言信西入道には、当然な、敵があった。
しかし少納言の局
の片隅 で、長年のあいだ、一事務官吏におかれたまま、根気よく無為無能な顔をして、よく隠忍を続けてきたかれだけに、ひとたび、
(乃公
、出 づ)
と、自負して出ると、まるで面目を違えていた。快刀
乱麻 という、趣
があった。その政治的才腕は、むしろ、斬
れすぎた。
保元の戦後処理も、思いのまま片づけ終わった。大内裏の造営も成し遂げた。そのほか地方税制の改革やら、古礼の復古やら、都内の武器携行禁止やら、彼の意中から出た政令刷新は、枚挙
にいとまがない。人材の抜擢、大臣の更迭、また賞罰の振り当てにいたるまで、じつに明快は明快だが、余りにも堰を切ったようで、果断のきらいがないでもない。いや、その独裁ぶりに、もう非難の声が出始めていた。
独裁者が乱を呼ぶのか、乱が独裁者を作るのか、とにかく、保元以前にはなかった型の覇権
的人物が、一夜に出来た地殻
異変 の山のように、忽然
と、政権に立って、この荒治療をし出したものである。
新院の遠流
。為義、忠正などの斬刑、そして新院方の百名ぢかい公卿武将をも、捕
まえては斬らせ、捕まえては斬らせ、寸情の仮借
をしなかったのもかれのさしずといわれている。
当時。── その恐怖政治を見て、栂
ノ尾 の文覚
は、信西入道の館へ、献言に行ったが、結果は、信西に面会を避けられて、いたずらに、大声
疾呼 し、文覚大暴
れの一場面を演じて帰ったに過ぎなかった。
もとより信西も、他人の脅迫などで、所信を曲げる男ではない。
むしろ、かれのやり口は、以後いよいよ辛辣
を加え、
(かれは敵、かれは、自分の支持者)
と、はっきり、見分けをつけて廟
へ臨んだ。政敵は政敵として、正面から反目し、相手を屈服させずには措
かないとする概がある。
もちろん、かれが、いかに時を得たにしても、単なる政治的な手腕だけでは、こうまで、振舞えるわけのものではない。信西入道をして、この自負心を持たせたものは、やはり武力であった。平家の惣領清盛と、陰に、手を握っていたことにある。
両者の関係は、久しい仲だし、信西の妻伊ノ局と、清盛の妻時子との交わりも変わりがない。──
保元の論功行賞は、それの覿面
な現われでもあった。清盛には厚く、源氏の義朝には薄かった。
その時でさえ、義朝が、左馬頭に叙されたのに較べて、清盛の播磨守は、実質的に格段の優位だといわれていたのに、清盛のみは、その後もまた、大宰大弐
(大宰府の次官) に昇官されていた。いや、清盛に限らず、六
波羅 の一族は、経盛、頼盛、教盛などを始め、みな、何かの役名についたり、昇官したりしている。
半面、秋風の寂寥
に、肩をせばめていたのは、源氏の人びとだった。
義朝の心事であった。
その義朝を中心として、信西政策への不平と、六波羅一族への対立感は、深刻に、上限以後の、源氏武者の骨身に、沁
みていた。
深草の信頼一派の反信西と、義朝一党との不平とは、こうして、まったく、別な立場、別な対立感情から出た燻
りであった。 |