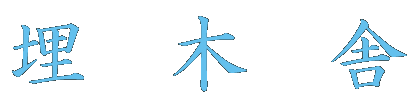──
初め、保元の乱の直後、例の、夕顔
ノ三位
は。
(これは、信西と信頼を、親しくさせておくに限る。自分にも将来の利益となろう。時勢は、信西入道の手腕に未来を約している)
かれ一流の敏な先見のもとに、そのころは、そう二人の提携を
── そしてその仲介の労に、ずいぶん骨を折ったものであった。
ところが、信西入道は、てんで、青くさい信頼などを、まともに、相手にしようとしない。
信頼の家の家系は、摂家
に次ぐ名門ですとか、後白河上皇が、特におん目をかけている寵臣
ですなどと
── いくら経宗が、そばから紹介の弁に努
めても、信西は、
(ははあ、そうですか。・・・・じゃあ、伊予三位中隆
どのの御
公達
か。なるほど、似ていらっしゃる)
ぐらいに軽く受けていたり、また、
(──
おふたりとも、蹴鞠には、御練達だそうだの。後白河の君にも、おひまさえあると、鞠の懸
へよくお立ち寄りになられるそうな。ま、せいぜい上皇のお守
をたのみますよ。・・・・鞠は健康のためにも、よろしいからな。そのうちに、信西も、政務に閑
を得たら、御教授をねがいましょうかの。はははは)
といった塩梅
である。どう、水を向けても、政治上の話などは、おくびにも、触れてこない。
──
けれど、経宗が、信頼を連れて、信西を訪い、二人を接近させた効は、大いにあった。
それまでは、皇后宮
権太夫
であった権中納信頼に、さらに右衛門
督
という重職が与えられたのである。
(話せるやつよ。信西という男は)
急に、信頼は、かれを賞
めだした。
欲には、限りがなく、その後、かれはなお、
(近衛大将になりたい)
という野望を抱いた。──
そして、信西入道も、自分に好意を持っているはずだから、成功疑いなしと思い込み、これを何かのおり、上皇へ、直々
に、お願いしてみた。
後白河上皇は、事実、信頼を愛しておられたので、これを信西に諮
られた。
すると、信西は、苦
りきって、こうお答えした。
「およそ、叙位
除目
をみだりにすることは、乱階
の初めです。いかに、御
寵愛
の臣でも、まだ二十七、八の信頼どのには、現在の官位でも過分といえましょう。──
近衛大将などとは、思いもよりません。それも、優れた人物とでもいうならばですが、文にもあらぬ武にもあらぬ ── あの程度の乳臭児
を」
後に。── これをたれかが、そのまま信頼へ、告げ口したらしい。
信頼は、怒った。ひどく信西を恨んだ。
信西に対するかれのふくみは、信西がじつは自分をあしらっていたのだと気づいた時に始まったと言えよう。と、言っても、あらわに、かれと覇
を争うほどな実力はない。ただ陰性な反抗と陰口につきていた。
上皇の御首尾も、その後は、なんとなく、おもしろくない。信頼は、理由も明らかにせず、深草の別荘へ、引き籠
ってしまった。
(あんなものです。今どきのわがまま公達は
──。なんと他愛のない近衛大将でしょうが)
と、信西が、御前で一笑したということも、かれの耳へ聞こえていた。
信頼は、侮辱を感じた。唇
をかんで、がらにもなく、
(いまにみよ、今に)
と、報復の念にふるえた。
後に、信西に容
れられない不平の徒は、自分のほかにも、想像以上に多いのを知って、かれは、慰まれてきた。これらの不平分子は、信頼の心火に、薪
や油を持ち寄って、
(あなたが起つなら、われらとて、身命を惜しむ者ではありません。信西を憎む声は、ちまたにも満ちている)
と、おだてあげた。
不平組みが寄れば、
「信西討つべし」 の理由はいくらでも数えられた。信頼も、かって経宗とともに、信西を初めてその居館に訪問した日、おりふし、中門に突っ立って、信西の悪政を、口を極めて怒罵
していた僧文覚の言葉を思い出した。
(そうだ、あれがちまたの声だ。人をもって言わせた天の声だ。思い切って起てば、世はあげて、自分を支持するにちがいない)
かれは、私的な感情の動機を、次第に、公的な名分へ結びつけて、勝手な錯覚をいよいよ堅めていた。藤氏の門、人多しといえども、宮門の大奸
を除き、この時弊
を粛清する者は、われを措
いてたれがあろうかと、思いあがった。そうした間に、かれと、源義朝とは、いつか同病の知己となった。いくたびか、密会もし、盟約も結んだ。
その手引きをした者が、夕顔ノ三位経宗であることは、いうまでもない。
源氏党の鬱々
たる異端の気と、自己一身の不平とを、胸いっぱいにもっていた義朝と
── 信頼らの不平貴族の一部とは、ここにおいて、完全な一つのもにになった。
信頼は、心に誇
った。自分も敵方とひとしく、今や背後に、武力を持った。──
信西に、平氏の輩
があれば、自分には、源氏の義朝一党がある。── 六波羅、姉小路、何かあらん、と豪語し出した。 |