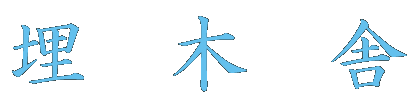まだ、法皇の喪
が、発せられない、その日の、寸前のこと。
時なるかな、仙洞の中軸も、今は、失
せ給うらしい ── と、街にも聞こえわたった日である。
「法皇、御危篤・・・・」
との報に、その御養生殿 ── 鳥羽の安楽寿院へと、駆けつけてゆく輿、馬、牛車などの数は、ひきもきらない。
その中を、これはまた、あわただしげに、牛飼いの童、舎人、随身まで、眼じりをあげて、急いでゆく、一両の牛車があった。
新院崇徳の、悲痛なおん顔が、ゆれ騒ぐ、御簾
のうちに仰がれた。
新院には、つい昨夜まで、この急変を、御存じなく、今朝、鳥羽の田中殿
の舎人からの早馬で、初めて、
「さは、にわかに・・・・?」
と、おどろからたものだった。
さすがに、御父子の情。すぐに、御車
を命ぜられ、田中殿で御装束がえもなさらず、そのまま安楽寿院へ向かわれた。
門の内外は、牛車で、いっぱいだった。
広前にも、すきまない程、供待ちの、輿や、牛車がおかれている。
しかも、離宮の奥深くまで、一抹
の悲しい静寂 が、墨のように刷
いていて、新院の御車を、お迎えに出る者もない。
「たれぞ、あらぬや、新院のわたらせ給うに」
随身の者は、声をそろえて、車寄せや、あたりの廂
へ、呼ばわった。
そのまに、もう、新院は、待ちきれないお気持に急
かれて、おみずから、簾をあげて、
「── 降ろせ、降ろせ」
と、烈しいお声を、何度も、牛飼の者の背へ、浴びせておられた。
すでに、門を入るとき、金堂
、三塔などの、祈祷 の鐘が、ハタとやみ、そこらにいた諸家の従者や侍たちも、ひとしく、ある、一瞬を感じて、
「・・・・おお、御閉眼とみゆる」
「御臨終・・・・ぞ」
と、一せいに、地へ伏してしまったり、また、御堂のあたりへ、わらわら集まって、合掌しあっているのを見ておられた。
(さては、この世のおん息を、ひきとらせ給う今か。あわれ、御生前に、ひと目なりとも)
と、新院のお胸は、岩をかむ飛沫
のように、鳴り騒いだ。五臓といわず、体じゅうの、指の先までが、わままき、痛み、悲しみ ── そして毛孔のすべてまでが、何かを、一言でも、さけびたがって、肌
に粟 つぶを、よだてていた。
この血の中で、新院が、必死にあがき求めておられたのは、もう、法皇ではない。ただの父である。
── 自分も上皇ではない、ただの子である。
父が死ぬ ── 子が、駆けつけて来たのだ。
すぐ、眼と鼻の先の、同じ都の中に、何十年もいながら、親しく父とも呼べず、子とも仰ってもらえなかった父子
。
たくさんな、誤解もある。
厭まれもした子であるが、お恨みもある。
おそらくは、父なるあなたも、この悔いの子を、ひと目、見て下すったら
── 人間としての、ひとすじのおん涙を ── 垂れていただけるに違いない。
お会いしたい。どうしても、御意識のあるうちに。
子よ。父よ。 ──
と心の中だけのことでよい。
一すじの、涙が、二個の、愚かな肉塊を、一つに還元してくれるに相違ない。 ── それを抱いて、なお、生き残って、人間の業
をつづけてゆく玩愚 なる子の、せめてもの生きがいとしましょう。人間が、動物ではない、動物になってはならない
“護符 ” としたい。
── 凡下の子なら、何をか、こんな悶
えを持とう。お父さんっ、と呼べばよい。抱きつけばよい。どうして、それが出来ないのか。
「降ろせというに、何をさは、惑い騒ぐぞ。かしこへ、着けよ。・・・・早くっ」
新院は、ふたたび、叱咤
された。
すさまじい御声に、随身や牛飼は、いよいようろたえて、にわかに、車をまわし、むりに、押し通って、車寄せの大廂
へ近づこうとしたため、そこに据えてあった輿の一つが、車の輪に触れて、ばりばりと壊れかけた。
「あな。狼藉
っ」
と、武者所の親範
。また範家 の子の源ノ勘解由
など、四、五名が、駆けて来て、やにわに、御車
の轅 を、左右から抑えた。
すわと、新院方の随身も、いきまいて、
「無礼すな、眼
はないか。これは、上皇の御車なるを、何は、阻むぞ」
と、叱りとばした。
すると、親範や勘解由たちは、かえって、威
猛高 を増して、
「おうよ。新院の参入と見奉ればこそ、こうは、仕
るなれ。無下 に、入り給わんとて、やは、ここを通し参らすべき。戻られい、戻られい」
「な、なにを、下臈
どもの、血狂うて ──」 と、新院は思わず、御車の端まで、身をのり出して、
「朕にとっては、かりそめにも、父なる法皇の、おん臨終
に、急ぎまかるに、案内
もあらず、かえって、武者ばらをもって、阻むとは、心得ね。 ── そも、なんじらは、たれの命によってか、かかる無体を働くぞ」
「仰せには候えど、これは、右少弁惟方卿
が、御内旨を奉じての、仰せ付けにて候う。たとえ、上皇たりといえ、武者には武者の務めの候う。ここ一歩たりと、お通しはささじ」
「なんの、なんじらの、関
ずらうことかは」
と、新院は、身をふるわせて、御車から降りかけた。武者たちは、力をあわせて、車を押し返し、随身たちは、武者たちを、突き退け、突き飛ばして、もみ合った。
その弾
みに、新院がお手を掛けていた御簾が切れて、あなと、叫ぶまに、轅
の外へ、転 び落ちられた。そして、ばらばらになった御簾の竹の端が、武者親範の瞼
をやぶって、血を出した。 |