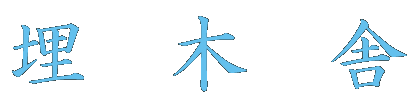振りまわしていたのは、弓であった。もちろん、弦
は、跳ねてしまう。
清盛は、横なぐりに、三、四人はそれで、殴りたおした、あとの行動は、無意識の阿修羅
である。
だが、目にあまる法師群には、笑うべき抵抗だった。ましてかれらの手には、長柄
、薙刀 などの有利な武器も持たれている。
「殺すな。つかまえろ」
衆徒は、ただひとりの清盛を、狩場
の猪 みたいに見て、なぶり合った。
「捕
って伏 せろ。生かして、叡山
へ、ひいて帰れ」
「生け捕りにこそ。生かしてこそ」
実相坊か、如空坊か、声をからして、言っている。
かれらの首脳たちが、清盛をここで殺すまいとするのは、慈悲ではない。後日、鳥羽院へする掛合いのためであり、また、信仰の大叛逆人清盛と謳
って、世人の前で極刑にすることの方が、叡山の威を示すゆえんであると考えたからである。
しかし、勢いは、意のままには、うごかない。
狂せる大衆と、死を思わない一個との、咬
みあいだ。
清盛は、敵の長柄を奪って、いよいよ荒れまわった。
かれのすねや小手にも、血しおが見え、地上にも、死者、怪我人が六、七人は、たおれはじめた。
一方、やや離れて、ここと同じ死地にある時忠と、平六も、戦い戦い、つむじ風のように、清盛のほうへ、移動して来ながら、ひたすら、清盛を、案じているらしく、
「わ、若殿っ・・・・」
と、かなたで叫び、
「兄者人
っ・・・・あ、あんじゃひと!」
と、断
れ断 れな叫びを送って来る。
清盛も呼び交わした。
「時忠あっ。平六っ・・・・怯
むな。気をのまれるな。おれたちの上にも、日輪はあるぞ」
終わりの言葉は、自分へ言っているのであろう。
そして、すべては、一瞬間の出来事だったが、──
騒動は、これだけに、止
まらなかった。
騒ぎを聞き伝えた附近の細民たちは、いつのまにか、真っ黒に、ここを遠巻きにしていた。何か、わんわん言っていたが、
「叡山の狼
に、食い殺させるな」
と、ひとりが、小石を持ったのを見 ──
「外道の弟子め」
「法師面
よ」
「強欲の、悪僧ばらを、やっつけろ」
と、口々から、日ごろの感情を吐き出した。
次には、われもわれもと、小石を拾って、投げはじめたのだ。野次
馬 的な心理とするには、余りに、忿懣
のうなりが聞こえる。突如、降ってきた天譴
の石の雨と、いえないこともない。
これと時を一にして、祗園の木々の間から、黒煙
を、ふき出していた。
一ヶ所や二ヶ所ではない。感神院の境内や、八坂、小松谷、黒谷あたりにも、煙が見える。
法師勢が、秩序も強がりも失って、乱れ立ったのは、このためだった。
── 伏兵がある。敵の伏勢が立ちまわったぞ、と口走りながら、にわかに、潰走
しはじめた。
逃げ足となっては、神輿といえども精彩がない。崩れゆく衆徒の上に舞う砂ほこりに、輿
の屋根を傾 がせ、金色
の鳳凰 を横ざまにしながら、見ぎたなく、粟田口
方面へと、立ち退いて行くのだった。
「やあ、むなしく退いて行くわ。これは、奇妙だ」
清盛は、東山の一角に立ち、はるかを見て、笑っていた。よろいの黒革胴
を、そばに脱ぎ捨てて、半裸の姿で、大汗をふいている。
実に、おかしい。笑わざるを得ない。
二千余の大衆よりも、逃げたのは、もちろん、こっちが先なのだ。
一矢
を、神輿に射たら、すぐ、脱兎
の如く、逃げるつもりで、初めから、心に計っていたのである。
(犬死するな。見得を思わず、逃げ落ちろ)
とは、とかく死にたがっている時忠や平六にも、前もって、かたく、言い含めていたことである。落ち合う場所も、清水寺のうしろの峰
── 霊山 の岩鼻と、きめておいたものだった。
それなのに、あの驕慢
な山法師の大群が、何に慌てて、さきに潰走
しだしたのか。
石の雨にも、驚いたのだろうが、諸所に揚がった黒煙
に、すわと、疑心暗鬼に追われたものにちがいない。
「しかし、何の煙だろうか」
清盛にも分らなかった。余煙はなお、太陽を鈍赤
くしている。清盛は瞳孔
がひらいたような眼を向けていた。そこへ、時忠ひとりが、登って来た。
「あ。御無事でしたか」
「やあ、来たか。時忠。 ── 平六はどうした、平六は」
「平六も、血路を開いて、逃げました」
「あとから、来るのか」
「とどろき橋の下で、出会いましたが、あちこちの煙を見て、これはきっと、父の木工助家貞が、何か謀ったことにちがいない。
── 見とどけて来るといって、八坂の方へ、駆け去りました。やがて、参るにちがいありません」
「そうか。・・・・いや、そう申せば、六波羅
の家に、むなしく留守している木工助でもない。じじめが、何か、敵の裏をかいた火の手かも知れぬのう・・・・」 |