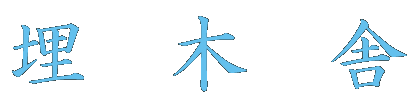「── 因
は、祗園 の喧嘩
であった。神も身よ、仏も、耳の穴をほじって聞け。理非いずれは、双方、酒のうえのこと、喧嘩は両成敗と、むかしからの慣
わしにも聞く。 ── 清盛の愛する二名の家人を、忍んで、叡山へ渡すからには、叡山の主
たる、日吉 山王の神輿へも、安芸守清盛が、物申さでは、さし措たれぬ」
「あはははっ。・・・・あははは。やよ見ろ、安芸守清盛は、気が狂うたのだ。──
気が狂うて、来たとみゆるぞ」
「だまって聞け。法師どもっ」
清盛は、声を張るのに、満身を揺すった。まるで、熱鉄の上の水玉のように、頬
、あご、耳のうらから、汗の玉が、散るのだった。
「狂気か、正気かは、気をしずめて、なお、おれの言うところを聞いてからにしろ。 ── 日吉山王の神輿も聞けよかし。およそ、神だろうが、仏だろうが、人を、悩ませ、惑わせ、苦しませる神やある仏やある。あらば外道
の用具に相違ない。叡山の凶徒にかつがれ、白昼の大道を推し歩く、なんじ、日吉山王の神輿こそ、怪
しからぬ。幾世、人を晦
まし、迷わせて来つらんも、この清盛を、たぶらかすことは出来ぬぞ。 ── 喧嘩は両成敗ぞ。覚悟せよ、邪神の輿っ」
あ? ── と、うろたえの表情が、無数の面上をかすめたとき、もう清盛は、弓に矢をつがえ、キ、キ、キ・・・・と、満をしぼって、神輿へ鏃
を向けていた。
横川ノ実相坊は、おどり上がって、頭から火を出すような、大喝
を放った。
「あな、無法者っ、罰当たりめっ。── 血へど吐いて、死ぬのも知らぬか」
「血へど? 吐いてみたい!」
びゅんと、一線の弦
鳴 りが、虚空
に、聞こえたとき。 ── 矢は、サッと、風を切り、神輿の真ん中に、突き刺さっていた。
── とたんに、狂せるような諸声
が、二千余の荒法師の口から揚がった。白丁の神人たちも、とび上がって、何やら口々にいった。哭
くが如き声、怒る声、傷
む声、戸まどいの声、放心の声、悲しむ声、吠
える獣のような声。声、声、声の一つ一つに生きもものの感情がどぎつくほとばしっていた。
古来。
どんなことがあっても、神輿に、矢の当たった例
しはない。また、神輿の大威徳を冒
して、矢を向けるばかもないが ── もしあれば、矢は地に落ち、射手は立ち所に、血へどを吐いて、即死する。
── こう、かたく、信じられていた。
ところが、矢は、神輿に刺さった。
清盛は、血ヘドも吐かず、なお、立っている。
迷信は、白日
に破れた。それは迷信利用の中に、生活の根拠と、伝統の特権をもっていた山門大衆が、赤裸にされたことでもあった。かれらは、狼狽
と、おどろきの底へ、たたきこまれた。
しかし、祈祷
のきかないことを、誰よりも知っていたのは、祈祷する者たちであった。 ── 大衆を指揮する大法師たちは、大衆の幻滅と狼狽を、すぐかれらの怒気へ誘って、
「やあ、稀代な痴
れ者っ。そこな外道 を、取り逃がすな」
と、暴力を、けしかけた。
うわっ・・・・と、襲いかかる荒法師の長柄
の光や、土ほこりや、神人たちの棒の雨の中に、清盛の姿は、たちまち蔽
いつつまれて見えもしなくなった。
乱闘の渦は、別な所にも起こった。同じように、時忠、平六の二人も、取り囲まれてしまったとみえる。 |