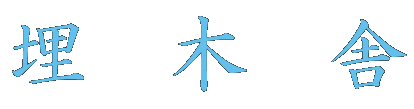秋になりました。季節の初風が涼しく吹き始めて、古歌にも、<わが背子
が衣ころも の裾の裏>
も、秋風に吹かれて淋しいと歌われている季節なので、源氏の君はうら淋しさのつのる心をこらえきれなくなられます。しきりに西の対たい
にお出かけになり、終日過ごされて、姫君に和琴などをお教えになっていらっしゃいます。
五、六日頃の夕月が早くから西の山に沈み、うす曇っている空の風情や、秋に鳴る荻おぎ
の葉ずれの音も、次第に身にいみる頃になっていました。源氏の君は、お琴を枕にして、玉鬘の姫君と御一緒に寄り添って横になっていらっしゃいます。こうまで馴れ睦むつ
んで、なお清らかな仲という、不思議な男女の関係がまたとあろうかと、ともすれば溜息ももれはちに、悩ましく夜を更かしていらっしゃいました。それでも女房がおかしいと疑うかも知れないと気になりますので、お帰りになろうとなさいます。
お庭先の篝火かがりび
が少し消えかかっていましたので、お供の右近うこん
の大夫たいふ をお呼びになって、篝火を明るく焚たく
くようにお命じになります。
たいそう涼しそうな遣水やりみず
のほとりに、枝ぶりが風情よく広がり、低く地を這は
うように見える檀まゆみ の木があります。その下に、松の割り木をほどよく積んで置いて、お部屋の前から遠ざけて焚きつけましたので、お部屋のほうは、たいそう涼しく、趣のある炎の光に、女君のお姿がほときわ引き立って見映えがしています。
源氏の君のお掌て
に愛撫される姫君のお髪ぐし の手ざわりなど、身にしみるほどひえびえとして、何とも言えず上品な感じがします。恥ずかしくてたまらないように、ぎこちなく身じろぎもされない姫君のつつましい御様子が、たいそう可愛らしく見えます。源氏の君は帰りづらいお気持になって、ためらっていらっしゃいます。
「始終誰かがついていて、火を炊きつけているように。夏の月のない夜は、庭に灯影がないと、何だか気味が悪く心細いものだから」
とおっしゃいます。
|
篝火に
たちそふ恋の 煙けぶり こそ 世には絶えせぬ
炎ほのほ なりけれ
(あの篝火の炎につれて
立ち上る恋の煙こそ この世にいつまでも 燃え尽きることのない わたしの恋の熱い炎なのです) |
|
「いつまで待てというのですか。人目のつかぬようさりげなくしていても、蚊遣火ではないけれど、わたしの苦しい恋はずっと下燃えに燃えつづけていたのですよ」
とおっしゃいます。女君も、何という怪しげな源氏の君の御態度かと思われて、 |
行方ゆくへ
なき 空に消け ちてよ 篝火の たよりにたぐふ
煙けぶり とならば
(果てしない大空に
どうか消して下さい 篝火につれて立ちのぼる 恋の煙とおっしゃるなら 煙りは空に消えゆくものを) |
|
「人が怪しいと思うことでしょう」
と、困りきっていらっしゃいますので、源氏の君は、
「ほらごらん」
こうしておとなしく帰るじゃないかというように、お出になりますと、ちょうどその時、花散里はなちるさと
の君きみ の東の対たい
から、笛と筝そう の合奏する美しい音色が聞こえて来ました。
「夕霧の中将が、例のいつもの連中と、遊んでいるらしい。あの笛は柏木かしわぎ
の頭の中将にちがいない。こちらに聞かせたいのだろう。うまいものだ、ほんとうにすばらしい音色じゃないか」
とおっしゃって、お立ち止まりになりました。
お使いをやられて、
「今、こちらにいます。たいそう涼しい篝火の火影に引きとめられてしまって」
とお誘いになりますと、連れ立って三人でこちらへいらっしゃいました。
「秋風楽しゅうふうらく
の笛の音が、秋になったと聞こえて来たので、このままではすまされなくなって」
と、源氏の君は和琴を取り出されて、心が惹ひ
きこまれるようにやさしくお弾きになります。夕霧の中将は盤渉調ばんしきちょう
でじつに愉たの しく笛を吹きました。
柏木の頭の中将は、姫君に心惹かれているので気もそぞろで、謡いだしにくそうにぐずぐずしていらっしゃいます。
源氏の君が
「早く」 と、おせかしになるので、弟の弁の中将が笏拍子しゃくびょうし
を打って小声で謡うのが、鈴虫と聞き間違えそうな美声でした。二度ばかり繰り返しお謡わせになり、源氏の君は和琴を頭の中将にお譲りになりました。たしかにわの和琴の名手として高名な父内大臣のお弾きになる爪音に少しも劣らず、はなやかですばらしい音色です。源氏の君は、
「御簾みす
の中に、音楽の音色の分かる方がいらっしゃるようです。今夜はお酒も慎みましょう。わたしのような年寄は、酔い泣きのついでに、つい、言ってはならぬことまで口走りそうだから」
とおっしゃるのを、御簾の中の玉鬘の姫君も、しみじみとせつない気持でお聞きになります。
切っても切れぬ血のつながった姉弟の御縁は、あだおろそかなものでないからでしょうか、姫君は、この公達きんだち
方を人知れず目にも耳にもお留めになっていらっしゃるのですけれど、弟君たちは、よもや姫君が実の姉だとはお気づきになりません。わけても柏木の頭の中将は、ただもう心の限りに姫君を恋い慕っていらっしゃるので、こうした機会にも、自分の恋心を忍び切れないような感情がこみ上げてきます。それでも表面は、さりげなく取りつくろって、決して気をゆるして弾き続けるようなことはなさいませんでした。 |