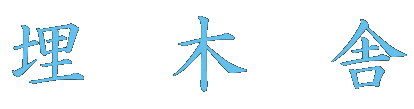すでに何人かの妻もあり、その子たちもあった。姻戚関係でもあったせいで、宣孝は早くから紫式部を知っていただろう。式部の少女時代、姉と二人で寝ている所へ、方違
えに来ていた宣孝が明け方しのんできて、 「なまおぼおぼしきことありて帰りけるに翌朝つとめて
」 という詞書ことばがき のある歌を紫式部は詠んで、朝顔の花に添えて、自分から宣孝に贈ったと、書き残している。
「なまおぼおぼしき」
というのは、曖昧なはっきりしない、情事という意味だが、姉と妹のどちらに、そのことがあったかもはっきりしない。
「おぼつかな それかあらぬか 明あけ
ぐれの 空おぼれする 朝顔の花」
という歌は、 「あなたの顔を見てしまったわよ、とぼけたって」 というほどの意味だから、やはり紫式部の身に起こったことと解していいだろう。娘時代の紫式部は、なかなか積極的でおきゃんだったのかも知れない。
宣孝は、地味な為時とはちがって、相当派手な自己顕示欲の強い男であったらしい。清少納言の
「枕草子」 に、金峯山きんぷせん
詣もう での時、宣孝が非常識にきらびやかな服装をして人々を驚かせたという逸話が載っている。職務怠慢で勅勘を受けた話なども伝わっている。女にかけても自信家で実績も挙げていたのだろう。
おそらく紫式部は、この未婚時代から、あるいは十三、四歳から、もう物語りに筆を染めていたのではないだろうか。紫式部ほどの天才は、早熟と決まっていて、そうした才能は、早々と芽を出すものだからである。
当時は印刷術はまだなく、物語類は全部手写しであった。姉や友達が面白がって写し、読者となってくれ、それが口コミで伝わり、写す人が多くなり、評判を高めるというパターンで、紫式部の文才は、まわりでは相当認められていたと想像出来る。
好色で多情な宣孝は、こういう変り種の紫式部を、自分の恋の蒐集品の一つにと望んだのではなかっただろうか。
ともかく紫式部は宣孝との間に、一人の女の子賢子けんし
を産み、宣孝は、その子を紫式部に与えると間もなく病死してしまった。結婚生活はわずか三年余りであった。長保三年 (1001)
のことである。
それから四、五年、紫式部は未亡人として家に引き籠っていた。その間、誘惑が全くなかったわけでもなさそうだが、誰も寄せ付けていない。おそらくその四、五年に、夫を失った淋しさと心の空虚を満たすのは、物語を書くことが、最適だったのではなかろうか。
藤原道長の野望は、この時すでに達成されていた。政敵兄道隆一家を失脚させ、関白になり、娘彰子しょうし
を一条天皇の中宮として入内させてもいた。政治権力者として最高の立場に君臨していた。
中宮彰子があまりに若く、一条天皇の愛が、先に入内していた姪の皇后定子の方に強いことが、唯一気がかりであった。定子のまわりには才女の清少納言や、美しくて天才的歌人でもある和泉式部などがいて、文化的な趣味の高い一条天皇の気持を惹きつけている。定子のサロンに負けないため、道長はより魅力的な彰子のサロンをつくる必要があった。
そこで紫式部に白羽の矢を立てたと思われる。つまり、それほど、すでに紫式部の書く物語は、人々の間で評判になっていたのだ。それはおそらくすでに
「源氏物語」 であっただろう。どの程度進んでいたかは知れないが、それを持参することを条件として、紫式部の宮仕えが決まったと思われる。
同じ女房でも、特別の局を与えられ、高価な紙や筆硯も充分に支給され、参考書も思いのままに揃えられたであろう。道長の権力を以ってすれば、すべて可能でる。
こうして、道長という何よりも強力なパトロンを持って、紫式部は心おきなく
「源氏物語」 の執筆に没頭する。
最高の読者は、一条天皇と中宮彰子である。道長の計企は的を射て、一条天皇は源氏物語のつづきが知りたく、彰子の部屋を訪れることが前より多くなる。声の美しい女房が読みあげるのを天皇と中宮と、そのまわりの女房たちが聞く、片隅に紫式部は出来るだけ目立たぬように控えて、人々の反応に神経を鋭とが
らせ、観察している。作者としての満悦は頂点に達する。
当時、物語の鑑賞法は、声に出して読むのを聞くのが常であった。こうして 「源氏物語」 は寛弘三、四年から後宮にもてはやされ、執筆と並行して読まれていったのである。
週刊誌や月刊誌の連載小説の形をとっていて、読者の反響や、希望を紫式部は参考にしながら、物語をふくらませたり、筋を造り直したりしていったと想像される。
紫式部びとって最高の読者である一条天皇は、文学趣味が高く、物語の観賞眼も女房たちの比ではなかった。
作者にとってはこんな晴れがましい光栄がまたとあるだろうか。至高の国家君主と、政治権力者に支えられているという自信と誇りがこの大長編を書き上げる紫式部の焦熱の根源にあったと思われる。 |