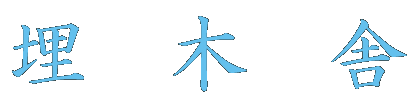参謀長の加藤友三郎は、
(妙なやつだ)
と、真之の挙動を見て、にがにがしく思わざるを得なった。
真之のやることは、どう見ても軍人らしくなかった。第一、戦闘終了後に加藤にひとことも口をきいていない。机に向かって何か書きつづけているのはいいとしても、従兵が食事を運んでくると、食器類を書類のわきに引き寄せ、物を食いながら筆を動かした。
やがて仕事を終えると、加藤に挨拶もせず、ぷいと自分の部屋へ引っ込んだ。
真之は仰臥した。相変らず靴をはいたままであった。疲れ切っていたが、神経が変にたかぶって、眠れそうになかった。彼はこのときすでに、作戦家でも軍人でもなくなっていたといえるかもしれない。
(このいくさ
が終われば)
と、そのことを考え、それを考えることで自分の神経のたかぶりを鎮めようとしていた。この状態ではとうてい明日再び艦橋に立つというような自信はなかった。かれがこの時懸命に自分に言いきかせていたのは、この戦争が終われば軍人をやめるということだった。
じつは真之は艦橋から降りたあと、艦内を一巡してしまったのである。
いたるところに弾痕があり、あの軽やかな濃灰色で装われた艦体は砲火と爆煙にさらされたためにひどく薄汚い姿になっていた。
負傷者が充満している上甲板は、真之が子供のころに母親から聞かされておびえた地獄の光景そのままだった。どの負傷者も大きな砲弾の弾片でやられているために負傷というよりこわれ・・・
もので、ある者は両脚をもぎ取られ、ある者は腕が付け根から無く、ある者は背を大きく割られていた。どの人間も、母親のお貞が彼をおびえさせた地獄の亡者の形容よりすさまじかった。
彼は、昼間、艦橋から見た敵のオスラービアが、艦体をことごとく炎にしてのたうちまわっていた姿の凄さを同時に思い出した。真之はあの光景を見たとき、このことばかりはたれにもいえないことであったが、体中の骨が慄ふる
えだしたような衝撃を覚えた。
(どうせ、やめる、坊主になる)
と、みずから懸命に言いきかせ、これを呪文じゅもん
のように唱えつづけることによって、その異常な感情をかろうじてなだめようとした。真之は自分が軍人に向かない男だということを、この夜、ベッドの上で泣きたいような思いで思った。兄の好古よしふる
はいま満州の奉天付近にいるはずであった。その好古へのうらみが、鉄の壁にさえぎられた暗く狭い空間の中で灯ったり消えたりした。
秋山真之という、日本海軍がそののちまで天才という賞讃を送りつづけた男には、いわばそういう脾弱ひよわ
さがあった。彼は戦後、実際に僧になるつもりで行動を開始した。
しかし小笠原長生ら彼の友人が懸命に押しとどめたためようやく思いとどまりはしたものの、結局、戦後に出生した長男の大ひろし
を僧にすべくしつっこく教育し、真之が大正七年に病没するときこの長男にかたくそのことを遺言した。大は成人後、無宗派の僧としてすごした。この海戦による被害者は敵味方の死傷者だけでなく真之自身もそうであったし、まだ未生のその長男の生活もこの日から出発してといえる。
|