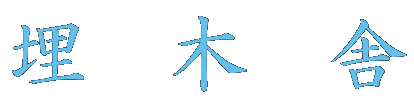「奥さん、お待ちください」
棟居の声の調子が改まった。恭子はまだこの上に言うことがあるのかというような顔を向けた。
「奥さんは麦わら帽子の詩をご存じですね?」
「麦わら帽子?
この間もたしかそんなことをおっしゃっていましたわね。私、そんな詩なんか知りません。詩は嫌いじゃありませんけれど、警察から押しつけられたくありませんわ」
「奥さんは、必ずその詩を知っておられるはずです」
「あまた、どうかしてんんじゃないの?
私は知らないと言っているのよ」
「幼いころの夏の日、子は母に連れられて、霧積へ行った。母に手を引かれて渓
に沿った道を歩いていると、いきなり吹いてきた強い風にさらわれて、幼児のかぶっていた麦わら帽子が渓の底へ落ちてしまったのです。子はその麦わら帽子に託して、母親に切々たる思慕の情を詩うた
った。その詩が、霧積へ行った三人の親子連れの目にとまった。
おそらく生涯に一度だけの親子いっしょの旅立ったのでしょう。渓谷は緑に燃え、母は若く美しく、優しかった。子の胸にその時の思い出が焼き付いてしまった。その子のその後の苛酷な人生の中で、たった一つの宝石のような想い出だった。父親も、その旅行でいっしょだった。家族は旅行の後に離散した。もしかすると、その旅行は、一家が離散する前の最後の想い出のための旅行だったかも知れない」
「やめてください。そんなお話、私には関係ありません」
恭子は言ったが、立ち去ろうとしなかった。なにものかが意志に反してその場に彼女を縛りつけているようであった。
「一家は、その旅行の後で別れた。子は父に連れられて、父の本国アメリカへ、母は日本に残った。そこにどんな事情があったのか、私は知りません。だが、子には霧積の想い出が、母の思い出として深く刻まれた。霧積の想い出をうたった西条八十の麦わら帽子の詩が、自分のことのように印象されてしまった。たぶん、その詩は、そのとき母が子に話して聞かせたものでしょう。
父に連れられてアメリカへ帰った子は、母への想いに耐え切れなくなって、日本へやって来た。父はその子のために老い先短い身体を自ら車に当てて、その補償で旅費をつくってやった。父の死が母への想いの堰を切ったのかもしれない。父も子に託して、かつての
『日本の妻』 に会いたかったのでしょう。緑の霧積を背景にした母のおもかげが、子の瞼まぶた
で揺れている。底辺の差別の生活の中で、母だけが子の救いだった。辛いとき、悲しいとき、母のおもかげが、いつも子を柔らかく救ってくれた」
八杉恭子は黙ってしまった。面は無表情で鎧よろ
っているが、肩先が少し震えている。
「子は一目でいいから母に会いたいと思った。自分のたった一つの宝石である霧積の想い出を噛かみ
みしめたかった。母が新たな結婚をして、別の家庭を営んでいることは知っていたかも知れない。母の生活を乱すつもりはなかった。ただ一目でいいから会いたい。親子の情とはそんなものではないでしょうか。その点において血を分けた仲というものは、性的な男女関係とは本質的に違う。
だがその子を母は決定的の拒んだ。母は成功し、社会的な地位もあり、名声もあった。安定した家庭と子どもがあった。それらのすべてを、すでにその存在すら忘れていた黒い隠し子が突然現れて、根本から破壊しようとしている。母は自衛のために子の一人を犠牲にしようとしたのだ。しかしはるばる日本へ父の命で購あがな
った旅費によって、おもかげの母を訪ねて来た子は、母の文字どおりの致命的な拒絶にあってどんな思いだっらろうか。たった一つの宝石はみじんに砕かれてしまった。絶望の瞳ひとみ
に、麦わら帽子がうつった。花やかなイルミネーションに縁取られた夜空に浮かぶ麦わら帽子だった。ロイヤルホテルのスカイレストランは、夜眺めると麦わら帽子の形に見えることを御存じですか。そこへジョニー・ヘイワードは最後の気力を振り絞って這は
い上がって行ったのです。
彼は母の致命的な拒絶にあいながらも、なお、母を信じつづけていたのです。あそこに母がいる。自分を優しく迎ええてくれる母親がいるに違いないと。一歩一歩よろめき歩いて行った後ろには血の痕あと
がしたたっていた。それは母に抉えぐ
られた傷口からしたたり落ちた血の痕です。奥さん、この帽子をおぼえていますか」
棟居はこの時のために用意しておいた麦わら帽子を恭子の前に差し出した。材質も不明なほどに古びて、触さわ
ればぼろぼろに崩れてしまいそうである。清水谷公園で発見されたあの麦わら帽子であった。 |