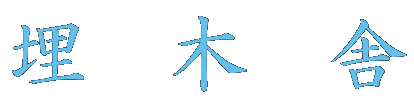旗艦スワロフは、燃えている。しかしその指令塔のみはまだ外形を保っていた。指令塔は当然ながらつよい防弾能力をもっていた。
傘型
の頑丈な屋根がこれを覆おお って落下弾を防いでいるのである。まるい壁は厚さ十インチもある鋼板で出来上がっていて、艦隊の首脳たちの生命を守っていた。外界を見るには細い隙間からのぞかねばならない。ちょうど人間の目の高さにそれがあった。ロジェストウェンスキーもその幕僚も海戦中ずっとしに隙間をのぞきつづけていた。
三笠が午後二時四十五分変針したとき、典型的な貴族である参謀長のコロン大佐は、この期ご
にいたっても遠慮ぶかげに、
「閣下、ミカサです。こちらへ接近しています」
と、ロジェストウェンスキーの注意をうながした。提督は背をかがめて隙間をのぞきこみつつ
「わかっている」 とどなった。しかしすぐには、異変に即応する命令は出さなかった。この独裁者は、幕僚の助言を雑音程度にしか思っていなかった。彼は自分の頭脳にのみ信頼をおいていた。しかしこの錯綜さくそう
した戦闘場面での指揮においては頭脳が占める部分は寡少であった。それよりも勇気が行動を決定すべきであった。が、ロジェストウェンスキーに不足しているものはそれであったかもしれない。
この時期、驚くべきことにスワロフと三笠の距離は、わずか二千四百メートルにまでちぢまっていたのである。この戦闘中、東郷とロジェストウェンスキーがもっとも接近した瞬間であり、ほとんど主将同士の一騎討ちで刺し違えるというような形勢を出現した。三笠の艦橋で動いている人影まで見えた。ロジェストウェンスキーは昂奮した。そのあまり、
「トーゴーを殺せ」
とまで、思った。
彼がいかに昂奮していたかということは提督みずからが一介の砲術長
(中佐か少佐級) のようになってじかに射撃命令を下したことでもわかる。
彼は砲まで指定した。砲は前部左舷六インチ砲であった。目標はむろん東郷である。
「三笠を沈めよ」
という信号は、ロジェストウェンスキーはこの戦闘中のある時期すでに掲げていた。
いまこそその好機であった。スワロフの前部左舷の六インチ砲は轟然と火を噴き、黒煙をあげ、徹甲弾を発射した。艦隊の各艦はそれにならった。
三笠の前後左右に無数の水煙があがり、艦形を水で覆ったが、ロジェストウェンスキーがふりかざした一刀は不幸にも外そ
れた。弾は三笠に命中しなかった。ロシアは、射撃理論において日本より甚だしく遅れていた。日本の加藤寛治が開発した射撃指揮法のようなものは持っていなかった。ロシア側の各砲は勝手に射った。このため三笠付近に水煙が林立してもどの水煙が自分の砲の水煙かわからず、近いのか遠いのか、照準の修正も出来なかったのである。
一方、三笠たちの砲は、変針運動中は沈黙しつづけていた。運動が終了したとき、厳密にはロシア側に射たれてから二分後に、轟然と火蓋を切ったのである。むろん日本式の射撃法によっていた。つまり最初に三笠の各砲のうち一門だけが試射をする。その水煙を見、その弾着を確かめて、三笠の艦橋上にいる安保清種が各砲台に距離を知らせるのである。この合理的方法が、整然たる統制のもとに行われた。
三笠が敵に対する射距離をつかみ得たころ、天も海も晦冥かいめい
した。各艦から猛烈な射撃が行われたのである。もはや射撃というよりも砲弾の大集団が嵐をまきおこしているようなものであった。
この火と煙の嵐は敵の旗艦スワロフにのみ殺到した。 |