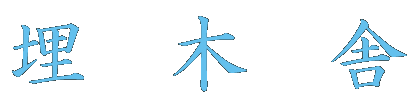やがて、市九郎は、雨露をしのぐために、絶壁に近く木小屋を立てた。朝は、山国川の流れが、星の光を写すころから起き出で、夕は瀬鳴
の音が静寂の天地に澄みかえるころまでも、やめなかった。が、行路の人々は、なお嗤笑の言葉をやめなかった。
「身のほどを知らぬたわけじゃ」 と、市九郎の努力を眼中におかなかった。
が、市九郎は一心不乱に槌を振るった。槌を振るっていさえすれば、彼の心にはあんんお雑念も起こらなかった。人を殺した悔恨も、そこになかった。極楽に生まれようという、欣求ごんぐ
もなかった。ただそこに、晴々した精進の心があるばかりであった。彼は出家して以来、夜ごとの寝覚めに、身を苦しめた自分の悪業の記憶が、日に薄らいでゆくのを感じた。彼はますます勇猛の心を振るいおこして、一向いっこう
専念に槌を振るった。
新しい年が来た。春が来て夏が来て早くも一年が経った。
市九郎の努力は、空しくはなかった。大絶壁の一端に、深さ一丈に近い洞窟がうがたれていた。それは、ホンの小さい洞窟ではあったが、市九郎の強い意志は最初の爪痕そうこん
を明らかにとどめていた。
が、近郷の人々はまた市九郎を笑った。
「あれ見られい! 狂人坊主きちがいぼうず
が、あれだけ掘りおった。一年の間、もがいて、たったあれだけじゃ・・・・」 と笑った。が、市九郎は自分の掘りうがった穴を見ると涙の出るほどうれしかった。それはいかに浅くとも、自分が精進の力の、如実に現れているものに、相違なかった。
市九郎は年を重ねて、またさらに振い立った。夜は如法にょほう
の闇に、昼もなお薄暗い洞窟のうちに端坐たんざ
して、ただ右の腕のみを、狂気の如く振っていた。市九郎にとって、右の腕を振ることのみが、彼の宗教的生活のすべてになってしまった。
洞窟の外には、日が輝き月が照り、雨が降り嵐あらし
がすさんだ。が、洞窟の中には、間断なき槌の音のみがあった。
二年の終わりにも里人はなお嗤笑をやめなかった。が、それはもう、声にまでは出てこなかった。ただ、市九郎の姿を見たあと、顔を見合わせて、互いに笑い合うだけであった。が、さらに一年経った。市九郎の槌の音は山国川の水声と同じく、不断に響いていた。村の人たちは、もうなんともいわなかった。彼らが、嗤笑の表情はいつの間にか、驚異のそれに変わっていた。
市九郎は、梳くしけず
らざれば頭髪はいつの間にか、伸びて双肩をおおい、浴ゆあみ
せざれば垢あか づきて、人間とも見えなかった。が、彼は自分が掘りうがった洞窟のうちに、獣のごとくうごめきながら、狂気のごとくその槌を振るいつづけていたのである。
里人の驚異はいつの間にか、同情に変わっていた。市九郎がしばしの暇をぬすんで、托鉢の行脚あんぎゃ
に出かけようとすると、洞窟の出口に思いがけなく、一椀の斎とき
を見いだすことが、多くなった。市九郎はそのために、托鉢に費やすべき時間を、さらに絶壁に向かうことが出来た。
四年目の終わりが来た。市九郎の掘りうがった洞窟は、もはや五丈の深さに達していた。が、その三町をこゆる絶壁に比べれば、そこになお、亡羊ぼうよう
の嘆があった。里人は市九郎の熱心に驚いたものの、いまだ、かくばかり見えすいた徒労に合力する者は、一人もなかった。
市九郎は、ただ一人その努力をつづけねばならなかった。が、もう掘りうがった仕事において、三昧さんまい
に入っていた市九郎は、ただ槌を振るうほかはなんの存念もなかった。 ただ土鼠もぐら
のように、命のある限り、掘りうがって行くほかには、なんの他念もなかった。彼は、ただ一人拮々きつきつ
として掘り進んだ。
洞窟の外は春去って秋来り、四時の風物が変わったが、洞窟の中には不断の槌の音のみが響いた。 |