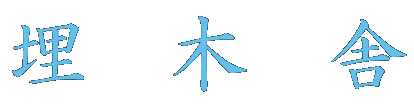旅順攻撃は、維新後近代化を急いだ日本人にとって、初めて
「近代」 というもののおそろしさに接した最初の体験であったかもしれない。要塞そのものが 「近代」 を象徴していた。それを知ることを、日本人は血であながった。
陸軍にとって宿命的なことは、
「旅順にはさわらない」
ということが、開戦前、数年の間対露戦研究に全力をあげていた陸軍参謀本部の基本的な考え方であった。
「敵は城
(要塞) に籠っている。相手にする必要があるものか」
と、考えていた。これはこれで、正しかった。日本軍としては大連湾に上陸し、背後の旅順要塞などにかまわず北進し、野戦において連戦連勝してゆけば、旅順要塞は結局は立ち腐れてしまう。捨てておくほうがよいのである。もとも、
「かといって、旅順要塞から敵兵が出て来て、北進する日本の野戦軍の背後を脅かしたら、どうする」
という設問が、当然出た。
「そてに対する手当ての兵力を残しておくだけでいい」
と、たれもが考えた。これも、正しいといわねばならない。開戦直前に参謀本部次長だった児玉源太郎さえ、対露大作戦計画の青写真を作るに当って、旅順から兵が出て来るという可能性の問題については、
「竹矢来でも組んでおけばいいよ」
といったほどである。竹矢来というのは、日本の戦国時代に敵兵の来襲を防ぐための臨時の簡易障害物で、江戸時代では立入り禁止の場所などによくこれが組まれた。児玉が言う竹矢来は例え話である。
「まあ、その程度の手当でいい」
というほどの意味であった。
ところが、開戦ぎりぎりの段階になってから海軍側が、
「旅順を陸から攻めてほしい」
と言って来たのである。
これも、強引な申し入れではなかった。もし海軍が、緒戦において旅順艦隊を一隻残らず沈めることが出来れば
(空想にちかい期待だが) もう陸からの攻撃は不要である。海軍としては、出来るだけ独力で旅順艦隊を全艦沈めようとしてかっかた。ところが旅順艦隊が出て来ないためにどうにもならず、封鎖だけを続けた。
その間、一度出て来た。東郷艦隊はそれを追って黄海海戦を演じたのだが、討ち洩らした艦が多く、それらがまた旅順港深く逃げ込んでしまった。そのためまたまた海軍は全力をあげて封鎖を続けざるを得なかった。敵艦はもう、怯え切って出て来ない。
このため陸上から陸軍に攻めてもらわざるを得なかったのである。海軍としては港内の艦隊を沈めればいい。そのためには弾着観測兵wp置ける
(結局それが二〇三高地なのだが) 山を陸軍に占領してもらい、陸軍砲をもって港内の敵艦を沈める。それだけでよかった。それで日露戦争における旅順の始末はついてしまうべきはずであった。ところが乃木軍が要塞をすっかり退治しれしまおうと思ったところに、この戦史上空前の惨事
(戦争というよりも) が起こるのである。 |