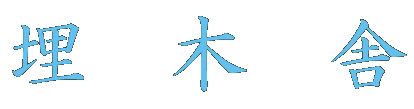上根岸の子規庵のあたりは路地奥だし、家も狭いし、会葬者の数は子規自身も二、三十人が限度だと見ていたが、新聞の死亡欄などで知ったひとたちが百五十人も集まって来た。
「空想だった」
と、碧梧桐が、虚子にささやいた。子規の遺言でもあり、葬儀はできるだけ質素にしようということを両人で話し合っていたのである。それが、あやしくなった。空想だった
とう言葉は、この当時の書生のはやりことばだった。
書生といえば、子規は生涯書生のつもりでいた。虚子も碧梧桐も、正真正銘の書生である。
── 書生が書生の葬式を出すのだ。
というつもりだった。それが、ひとなみに百人をこえる会葬者が来た。
しかし葬儀そのものは、質素だった。午前九時すぎ、通りいっぺんの読経がすむと、柩が家を出た。
「そうだ、ロンドンの夏目さんにも知らせておかなければいけない」
と、虚子が碧梧桐にささやいた。
「夏目さんといえば、秋山の淳さんは来なかったな」
と、碧梧桐は言う。
「淳さんは軍艦に乗っているのではないか」
「いいや」
碧梧桐は、郷党の消息通だった。
「海軍大学校というものにいるはずだ」
「ああ、居士こじ
もそう言っていた」
と言ったとき、葬列の向こうから小柄な男が、肩をいからせてやって来る。丸坊主で、まるで書生のように羽織を着ず、袴はかま
をすそみじかに穿は き、手には丸太のように太いステッキをつき、大またでやって来る。
「あれは、淳さんではあるまいか」
といううち、目鼻がはっきりしてきて、真之であることがわかった。
真之は、すこし遅れた。近づいて来て虚子らを見、目をそらし、すぐ柩のそばへ寄った。柩をにらみつけるように見ていたが、やがてぺこりと頭を下げた。
そのまま、立っている。葬列は進んで行くのだが、ついてゆこうとしない。
葬列が過ぎ去ったあと、人気ひとけ
のない路地で真之だけが立っていた。
(升さん、人はみな死ぬのだ)
おれもいずれは死ぬ、ということを、つぶやいた。真之にすれば、それが彼の念仏のつもりであった。
そのあと、家のほうへ行った。お八重、お律、それに陸くが
夫人などが、柩の行ってしまった座敷に、ぼんやりすわっている。
真之は黙って上がり、両手をついてくやみを述べようとしたが、うまく言葉にならずやむなく黙り、そのまま香炉の前ににじり寄って、抹香まっこう
をつまんだ。
そのまま、去った。
子規を土葬すべき寺の方にも行かなかった。寺は、このころ滝野川村といわれた田端たばた
の大竜寺である。 |