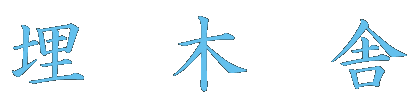平泉の中尊寺
にある弁慶堂は、月見坂の左手に当たる。もとは愛宕堂だったが、山麓の弁慶堂が朽ちはてたために、弁慶と義経の像をここへ移して以後、弁慶堂と呼ばれるようになった。
弁慶が針ねずみのように矢を射られて、壮烈な立往生たちおうじょう
を遂げたところは、衣川ころもがわ
が北上川に合流するあたりの一角だと言われるが、現在では月見坂の登り口にその墓がある。土地の言い伝えによると、立ち往生した弁慶は、実は七つ道具を背負った藁人形で、盛岡の郷士舞踊の剣舞はそれを形取かたど
ったといわれる。たしかに弁慶がそこで立ち往生してしまったのでは、蝦夷地への生脱説話は成り立たない。東北の田舎では、竹籠の中に藁束を入れ、川魚などを串に通してそれに差し込み、焼く風習があるが、この藁束をベンケイと呼ぶのは、弁慶の立ち往生に由来するとも聞いた。
義経の判官館は高館たかだち
と呼ばれる。藤原ふじわら 清衡きよひら
の時代には絶好の要害地とされていたらしいが、現在では北上川に浸食されて狭くなり、義経堂も切り立った断崖の上に位置している。しかしそこからの眺望はみごとで、北を流れる衣川の上流は、前九年の役、後三年の役で知られた古戦場でもある。
芭蕉が
「奥の細道」 紀行で平泉へ入ったのは元禄二年五月十三日のことだ。高館に足をとめ、時の移るのを忘れて歴史の興亡を思いやった。陽暦に直せば六月二十九日、もう夏である。 |