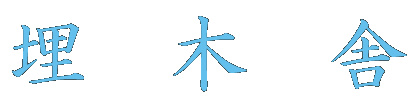堺や九州のあちこちに、南蛮船がやって来るということは、ただ、船が来たという現象だけと考えてよいことではなかった。
船をよこすだけの力のある者が、彼らの背後に控えている・・・・
少なくとも世界の海を乗りまわそうというのだ。その背後の勢力は想像以上に強力なものに違いない。
(そうした時に、まだ小田原では・・・・)
また、茶屋四郎次郎が口を開いた。
「本阿弥どのは、彼ら南蛮人の目的が、交易や布教だけではないようじゃと、こう申すのでござりまする」
「なるほど」
「と言って、国中が一つにまとまってありさえすれば怖れることはなく、そのまとめ役に、関白殿下と肩を並べるほどのお方が欲しい。それがこれからの日本国の運不運を決めるであろうと・・・・」
「いや、お待ち下さい茶屋どの」
光悦はテレた様子で四郎次郎をさえぎった。
「せっかく、信長公以来のご苦心が実って、とにかく戦乱はおわりかけた。その仕合わせを外から突き崩されては意味がない。そこでどこまでも内から立正
の実をあげなばならぬ・・・・と、こう申すのでござりまする」
「ただのまとめ役ではなく、立正の心を奉じたお人・・・・と、こう言われるのじゃな?」
「その立正が、まとめ役・・・・それ以外にはまとめ役はない・・・・と、こう存じますので」
家康はうなずきはしたが、改めて質問はしなかった。
家康自身の眼もすでに光悦と同じところを見つめている。あえて他を語るまでもなく、家康自身の経て来た過去が、そのまま
「平和」 の尊さを示す鏡でさえあった。
祖父の清康は二十五歳で陣没した。
父の広忠もまた二十四歳で、家臣に刺された傷が原因で果てている。
正妻の築山
御前のみじめな最期も、嫡子
信康 の哀れな生涯も、みな乱世の求めた犠牲であった。
いや、それよりもさらに哀れに想い出されるのは、祖母の華陽院
の生涯だったと言える・・・・
(いったい彼女の一生のどこに光があったであろうか・・・・?)
しかも、その不運の糸はまだ完全には断
ち切れず、家康の二女の督姫
はいま、小田原の氏直に嫁いで戦乱の風の匂いにおののいている。
督姫だけではない。現に家康が、聚楽第へ伴って来ている朝日御前など、関白の妹に生まれていながら、すでに生ける屍
ではなかったか。
(ここらで乱世の糸を断
たねば・・・・)
断ってくれと、祖父も、祖母も、父も、妻子も、みなひとしく家康に迫っている・・・・
「光悦」
「はいッ」
「今宵はよい心の糧
を得た」
「お恥ずかしゅうござりまする」
「わしも、こなたの言う、立正を心掛けよう。こなたもその心を市井
のうちにひろめてくりゃれ」
「ありがたき仰せ、光悦心に刻んで努めまする」
「茶屋、造作
をかけたのう。では学者のこと、頼んでおくぞ」
家康が起ちかけると、小栗大六が、あわてて立って供揃
えを命じてゆく。
光悦は平伏したまま、また刺すような眼になってじっと家康の後ろ姿をみつめていた。 |