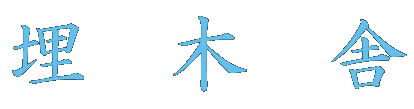竜馬は床ノ間の佩刀
陸奥守吉行を取ろうとし、すばやく背後へ身をひねった。
この一動作を、刺客は見逃さない。竜馬の左手が刀の鞘をつかんだとき、さらに二ノ太刀を加えた。左肩先から左背骨にかけて、骨を断つ斬撃を竜馬は受けた。
が、この瞬間、この若者の生命がもっとも高揚した。竜馬は跳
ねるように立ち上がった。同時に刀を鞘ぐるみのまま、左手でつか
を握り、右手で鞘をつかみ、鞘を上へ払いとばそうとしたが、火が散り、鉄が飛んだ。
驚くべき事であった。敵の斬撃のすさまじさは、竜馬が持つ陸奥守吉行の太刀
打
の部分から二十センチばかり鞘を割り、なかみの刀身を十センチばかり鐫
ってけずったことであった。
瞬間、半月形の鉄片が、飛んだ。敵のわざのすさまじさもさることながら、致命傷を受けつつも、なお鉄を鐫るまでの斬撃を受けえた竜馬の気魄は尋常ではない。
鐫ったいきおいで敵の太刀は流れ、流れて竜馬の前額部をさらに深く薙
ぎ斬った。
竜馬は、ようやく崩れた。くずれつつ、
「清
君、刀はないか」
と、叫んだ。清とは、中岡の変名石川清之助のことである。この場に至ってもなお中岡を変名で呼ぶ配慮をしたのは、竜馬の意識が明確であった証拠であろう。以上も以後も、すべて事件の翌々日に死んだ中岡の記憶による。
中岡にも刀を取る余裕がない。九寸の短刀しかない。信国在銘、白柄朱鞘で、鍔
はついているものの脇差というより匕首
の短さである。これをもって敵の大刀と渡り合ったが、十一ヶ所に傷を受け、ついに倒れ伏した。
わずか数分、気絶していたらしい。しかしすぐ息を吹きかえした。このとき敵が引きあげるところであった。
ほどなく竜馬も、よみがえった。この気丈な男は、全身にわが血を浴びながらすわりなおしたのである。
中岡は、顔をあげ、その竜馬を見た。竜馬は行燈を引き寄せ、わが佩刀の鞘を払って刀身をじっと見入った。
「残念だった」
思えばそうであろう。千葉門下の逸足として剣名を江都に轟かせた青春を持ちながら、鼠族
同然の刺客の不意を襲われ、しかも剣さえ使えなかった事を思うと、無念やるかたないに違いない。
「慎ノ字、手がきくか」
と、竜馬はたずねた。中岡は伏せながらうなずき、
「利く」 と答えた。
利くなら這って階下の近江屋の家族を呼べとでも竜馬は言いたかったのかも知れないが、中岡のほうが自分より重傷と見たらしい。
竜馬は自分で這い、隣室を這い進み、階段の口まで行った。
「新助、医者を呼べ」
と、階下に声をかけたが、その声はすでに力が失せ、下まで届かない。竜馬は欄干をつかみ、坐りなおした。
中岡も這って、竜馬の側に来た。
竜馬は外科医のような冷静さで自分の頭をおさえ、そこから流れる体液を掌につけてながめている。白い脳漿がまじっていた。
竜馬は突如、中岡を見て笑った。澄んだ、太虚
のようにあかるい微笑が、中岡の網膜にひろがった。
「慎ノ字、おれは脳をやられている。もう、いかぬ」
それが、竜馬の最後の言葉になった。言い終ると最後の息をつき、倒れ、なんの未練もなげにその霊は天に向かって駈けのぼった。
天に意思がある。
としか、この若者の場合、思えない。
天が、この国の歴史の混乱を収拾するためにこの若者を地上にくだし、その使命が終わった時惜しげもなく天へ召しかえした。
この夜、京の天は雨気が満ち、星がない。
しかし、時代は旋回している。若者は歴史の扉
をその手で押し、そして未来へ押しあげた。 |