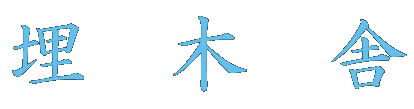寄せ手が三層にとりつくと、柴田勢は歯をむき出しにして追い払った。しかしそのたびに新手と入れ代って羽柴勢は押し返す。
城の四方を幾重にも取り巻いた寄せ手の喊声
は、つねに侵入勢をはげますのに引き替えて、柴田勢は七人減り十人減った。
中には寄せ手の中へ斬り込んでいったまま戻って来ない者もあった。討ち死にしたのではなくて、そのまま武器を捨てて捕虜
になったり、落ちていったりしたのに違いない。
勝家自身も、三度、敵を追いかけて、三度天守へ戻って来た。これは敵を斬り伏せるためというよりも、あり余ったわが力を使い尽くすためであり、死期を探していたのであった。
いつか陽
は傾きかけた。七ツ
(午後四時) に近いと思われる。
いったん天守へ引き揚げていった勝家のもとへ、中村文荷斎が、汗にまみれて上がって来た。
「殿、もはや、お予定の申
の刻
(四時) にござりまする」
「うむ。分った!」
勝家はその時、胴丸を脱いで、合掌したまま死んでいるお市の方の死骸から屏風をとりのけたところであった。
「文荷斎。下へ沙汰せよ。火を放ってよいぞ」
「かしこまりました」
文荷斎が、再び階下へ降りてゆくと、勝家は額
から玉の汗を滴
らしながら、黙ってお市の方のうしろに侍女たちの死骸を積んだ。そしてそれにお市の方の、今は苦痛の色もない、まっ白な死に顔を立てかけると、
「お方、見ておれッ」
ぽつんと言って、それから大きく息をした。
天守には三十幾つかのがばねはあったが、生きているのはそのとき、勝家ひとりであった。
しかし、勝家には、その屍体のどれもが死んでいるとは思えなかった。みな、勝家を凝視
し、勝家に話しかけている。
勝家は、そっとお市の方の冷たい頬にふれ、それからきりりと唇を結んで廻廊へ出ていった。
生き残った近侍はいずれも、いま、四層、五層で、勝家のそばへ敵を近寄せまいとして必死になっている。
今は最前線になったその四層から、濛々
とした白煙がまだきびしい烈日の中へ、雲のようにふくれ出した。
「やれ寄せ手の者ども・・・・」
その煙りの上へ現れた勝家の姿を見て、櫓をかこんでいる寄せ手の者はいっせいに小手をかざした。
「音にひびいた鬼柴田が腹の切りよう、よく見申して後学
にせよ!」
ワーッと下からどよめく声が噴きあげた。
勝家は、片足を欄干にかけて、しかし、下から見上げる幾千の眼よりも、うしろにあるお市の方の眼を抱きしめるように意識していた。
(この勝家は、こなたを裏切る男ではない。見ておれ、老武者の凄
まじさを・・・・)
きらりと白刃が陽をはじくと、バラバラと虹を描いて血が走った。左手の脇にがっちと刺したてた刀を、そのまま右手の背骨にひきつけ、返す刀で胸の下から臍下
まで一気に裂いた。とたんに勝家は最後の器量で眼をむいた。刀を投げて五臓
六腑
をつかみ出し、何か奇妙な声をあげて寄せ手の頭上へたたきつけた。
と、その瞬間だった。轟然
とした爆発音が一つ、二つ、三つと、続けざまに大地を揺すって、九重の天守が、木
っ葉
微塵
に火焔の中へ散りだしたのは・・・・
|