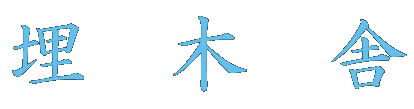権六郎勝久は、三たび眼を閉じて姿勢を正した。
彼の胸もまた錐を突き立てられたように切
なく痛んだ。
追いつめられて、鞭
打たれて、進退きわまった女の答えは、やはり 「死──」 であったのだ。
女性に男のような意地のあろうはずはなく、これはどこまでも絶望の死なのである。
「母上、そのご思案、父には一両日、打ち明けずにおきましょう」
「いいえ、その労
りはご無用に・・・・わらわの心は決まりました」
「父に打ち明けても、後悔はなされませぬか」
「若殿!」
ようやくお市の方は、まともに権六郎の顔をとらえた。権六郎はいぜん眼を閉じている。
「父上に、よくわらわの覚悟、取り次いで下されませ。わらわは柴田修理が妻、姫たちは浅井長政の遺児であったと悟りました」
権六郎はうなずきながら、
(それが悟りであるものか・・・・)
心できびしく首を振っていた。
(これは、この上なく哀れな諦
めの言葉ではないか・・・・)
「わらわは・・・・」
お市の方は、自分の決心の崩れゆくのを怖れる口調で、
「もはや悲運と縁の切れぬ女子。したが、姫たちは、どのような星を持って生まれいやるか分りませぬ。それゆえ・・・・それゆえ姫たちは・・・・」
「お案じなされまするな。姫たちのことならば、誓って生命は完
うさせまする」
「それで、殿はわらわの覚悟、お許しなされるであろうか」
「それは・・・・」
こんどは、権六郎がぐっと言葉に詰まっていった。
おそらく父は、素直に許すとは言うまい。
士道にこだわり、義理を想うて、離別を主張しつづけよう。
しかし、それはどこまでも表のことであった。
心の奥では、泣くであろう。よい妻が、わが最期
を飾ってくれたと泣くであろう・・・・
「母上!」
震える声をぐっと押えて、
「母上のご決意、この勝久によく分ってござりまする。頑
なな父なれど、・・・・私からよく説き伏せまする」
「何分ともに・・・・」
「心得ました。では・・・・」
丁寧
に一礼して、立ちかけて、
「風邪
を召されてはなりませぬ。誰ぞある、火をついであげるよう」
手を鳴らして侍女を呼んで、権六郎は、袴
のひだを正して廊下へ出た。
廊下を出ると、今までこらえていた涙がいちどに頬へ筋をひいた。
人情、義理、武士道、意地。
そうしたものが、きびしく五体を縛
っている人生が、何か滑稽
であり、おかしくもあるくせに、それがゆえに尊く、それがゆえに哀しい生き甲斐もまたありそうな気さえする。
「よし、これで決まった! 筑前、いずくからでも攻めて来るがよい」
権六郎は口の中でつぶやいて、それから静に歩き出した。
|