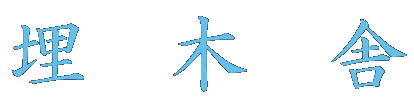「たわけ! 黙らぬか」
と、家康はまた叱った。叱りながらふといつかの本多作左衛門の言葉を思い出しておかしくなった。
口先で女子を労わるほど、無責任な遊びはないと言われたことを。
お愛は家康の理性にかなった。感情ではそれ以前、しきりに情火をかき立てている。
生涯お側へ・・・・と言った以上、たとえそれが勘違いであったにしても、見知らない男のもとへ再縁してゆくより、はるかに多く納得できるものを含んでいるはず。
(口先などで労わるものか・・・・)
「そなたに何を言うことがあるというのだ。控えておれッ」
「は・・・・はい」
「そなたは何と申した?
生涯お側へと申したであろう。その言葉は心にもない偽りではよもあるまい。十九で後家は通せぬ。また通すが神仏の意志にかのうたことでもない。予が子を産めと申したに言葉を返すとは不届きしごくじゃ。そちは立派に遺児を育てながら、それよりよい子を産んで育てる、女に課された大事な苦労をいとうてよいと思うてか。まだ広間にそなたの叔父、左衛門佐
清員 が残っているはずじゃ。呼んで参れ」
言いながら家康は妙にこそばゆくもあり、笑ってはならぬ気持ちでもあった。
男女の交わりとはかりそめの事ではなくて、そこから新しい生命を産むと、それは永遠に尾をひく無限の神秘を含んでいる。
百年後にも千年後にも。
そう思うと、どんなに厳粛
に言っても言い足りないほど厳粛なことであった。
お愛は度肝を抜かれて、しばらくぽかんとうずくまっていた。
おそらく彼女の想像の中にも、こんな妙な言い方の男女関係はあり得なかったのであろう。
「なぜ動かぬ。叔父を呼んで来いと申しているのだ」
「はい・・・・」
お愛はそっと立ち上がった。これを主君の立場を笠に着た暴言だとだけ感じ取ったら黙って立つお愛ではなかった。
柔らかい言葉のうちに祖父の強い烈
しさをしっかり受け継いでいるお愛であった。
が、ふしぎなことにお愛は腹が立たなかった。あるいは立派に遺児を育て、それに増した子を産むのが女のつとめ・・・・そう言われたことの中へ安心できる愛情を感じ取っていたからかも知れない。
やがてお愛は叔父の西郷左衛門佐清員をともなってあずまやへ戻って来た。
「殿、お呼びでござりますか」
「おお清員、こなたはな、この愛をこなたの養女にいたせ」
「は?
何と仰せられました」
「耳の悪い男だ。お愛をこなたの娘としてこなたに預ける。早々屋敷へ連れて戻れ」
「は・・・・するとお愛に何か不都合でもござりましたか」
「さよう、このまま召し使っていては不都合じゃ。改めて予が呼び出すまで、しかとこなたに預けておく、大切にいたせよ」
左衛門佐清員は解けない顔つきで首をかしげた。
お愛は真っ赤になって叔父のうしろにすくんでいる。
その一段下の庭石に腰をおろして、本多作左はコクリコクリと居眠りしていた。
|