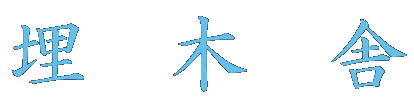第一の注進が届いた翌日、四月三十日、第二の注進は坂本城からやって来た。
信長の一行が無事に朽木谷を通過して京へ向ったというのであった。
徳川家康の先見のとおり、浅井父子は信長がそれほど早急に兵を返そうとは思いもよらず、完全に退路を断つに至らなかったのである。
注進を聞くと、濃姫ははじめて信忠のそばを離れて奥へもどった。
「お父上より何分のお指図あるまで、守備はお解きなさらぬよう」
今ごろは彼女の放った間諜どもが信長を逸した浅井勢をうろたえさせているに違いない
── そう思うとおかしさがこみあげた。
進撃の速さは電光にたとえられたが退き戦の速さもまた、見事に 「あ!」 と言わしめたのだ。おそらく朝倉勢の進撃も思うに任せなかったであろう。信長が岐阜へ戻らず、京へ引っ返したということはその間の余裕を雄弁に物語るものであった。
奥へ戻ると濃姫はさっそく三人の側室をわが居間へ呼び集めた。
三十日は朝から煙るような雨で、庭の梨花は甘い香りとともに溶けるように濡れていた。
「お呼びでござりまするか」
「お召しなされましたそうで」
お類の方をまっ先に、深雪、お奈々とつづいて来る三人の顔をうなずきながら眺めてゆくと、どれ一人も憎めなかった。
以前に寵を競うものとして、心に波を立たせたのが、かえっておかしく想い出された。
「揃いましtか」
「はい」
「さそおく、殿よりの注進申し聞かせましょう。殿はご無事に越前から京へお引き取りなされました。みなみなご安堵
ありますように」
「まあご無事で!」
「やっぱり弓矢八幡のご守護が殿にはございましたなあ」
以前に濃姫の侍女だった深雪は黙っていたが、お類の方とお奈々の方とは誰はばからず喜びあう。それが濃姫にはほほ笑ましかった。
この女たちは濃姫の敵ではなくて、無邪気な召使だった。
正妻という濃姫の立場を動かし難いものとして、それぞれの運命に何の疑いも持っていない。
「殿にハはなぜこのお城に帰らず、京へお出でなされたのでござりましょう」
お奈々の方がそう言うと、
「さあ・・・・?」
とお類の方は濃姫を仰いでいる。そうしたことの説明まで、素直に濃姫の言葉を聞く気の人々だった。
「殿は・・・・」
と濃姫は微笑を含んで、
「今では美濃、尾張二カ国の太守ではござりませぬ。まずもって天子様のご機嫌を伺い、それから戻るが道でござりましょう」
おだやかにそう言って、ふと胸が熱くなた。
すでに天下
人
、自分はその妻なのだと思うと、
(この人々も真昼の梟・・・・)
しみじみとわが身の幸福が感じられた。
側室たちは濃姫の説明に、おかしいほどの真顔でうなずきあっている。
|