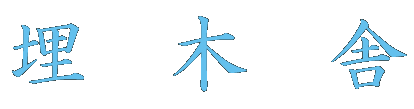紙面を作りながら、賀川自身が社会運動家へ脱皮しつつある自分を自覚した。
オグデンには日本人の農業労働者もいた。彼等は甜菜栽培の小作人にされて、資本家の土地を耕していた。オグデン地帯を開拓したインディアンのモルモン教徒も、土地は資本家に奪われ、日本人同様小作人に転落していた。
大正六年の春、甜菜農場で小作争議が発生した。生産した甜菜が資本家にあまりにも安く買い取られるので、小作人は値上げ要求をかかげ、小作人組合を結成したのだった。
さっそく賀川が小作人組合へ乗り込むと、小作人組合は日本人とモルモン教徒に分裂していた。
「もともとはおいらが拓いた土地だ。日本人のくせにでしゃばるな。資本化との交渉はおいらがやるぞ」
モルモン教徒は、そう叫んだ。
「甜菜の収量を上げたのは、おれたち日本人の技術だぞ。おれたちこそ資本家に言い分があるんだ」
日本人はそう主張してゆずらなかった。
「君たち、同じ小作人じゃないか。仲間で喧嘩していては、小作人の力はそれだけ弱くなる。固く手を握って、資本家に対する要求を貫徹するんだ!」
それには兎に角にも日本人とモルモン教徒が手を握り、統一要求にする必要があった。
「ぼくがこの地にとどまって、参謀の役を果たします。ぼくの指揮に従って下さい」
両者を説き、両者の言い分をきいて要求書をつくり、農場主にぶっつけた。小作人組合の分裂を策していた農場主の野望はくずれ、小作争議は小作人側の勝利となった。
しばらくすると日本人の小作人たちが、
<日本人会> の事務所にやって来た。
「賀川さん、あんたのおかげで、われわれは一年間に五万ドルも収入が増えました。これは我々のお礼のしるしです」
松の枝のようなガサガサした手が、百ドル紙幣を差し出した。喉から手が出るほど欲しいお金だった。
「ありがとう、ほんとうにありがとう・・・・。私も助かりました。おかげで日本に帰れます」
賀川豊彦は百ドル紙幣を押しいただいた。小作人の晴々した顔が、百ドル紙幣に勝る餞別であった。
賀川豊彦が二年九ヶ月ぶりで横浜港へ帰って来たのは大正六年五月四日であった。病院を建てる資金を稼いで帰るという約束は空手形になったが、
『労働者問題への開眼』 『小作人争議の体験』 という、日本の労働者と農民にはかけがえのないお土産を持参しての帰国であった。
埠頭で出迎えたのは、はる夫人だった。
「あなた、お帰りなさい・・・・」
「おお・・・・はるか。見違えるように、綺麗になったね」
たしかにはるは神戸で見送ったときとは、別人のように見えた。肌も瞳も輝いていた。香川がアメリカに留学中、はる夫人は横浜共立女子神学校で学生生活を送っていたのだった。 |