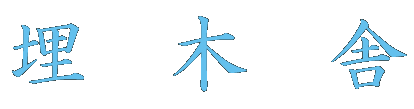やっと箸も終わって、
「美味
しかったねえ。・・・・蓬」
と、初めて、そこで声が聞かれた。
「ほんとに、夢の中で食べてるみたいに、食べてしまいました」
「ほら、鴬
が啼 いてるよ、あれも迦陵
頻伽 と聞こえる。極楽とか天国というのは、こんな日のことだろうな」
「ええ、わたくしたちの今が」
「何が人間の、幸福かといえば、つきつめたところ、まあこの辺が、人間のたどりつける、いちばんの幸福だろうよ。これなら人も許すし、神の咎めもあるわけはない。そして、たれにも望めることだから」
「それなのになんで、人は皆、位階や権力とかを、あんなにまで、血を流して争うのでしょう。もうもう、やめてくれればよいのに」
「やめれば、義経の君のようになる。そういう仕組みに出来ている世の中だから恐ろしい。また世の中は、そうしつつ進んでゆく。武家幕府とやらになっては、なおさら、烈
しくなるかもしれぬ」
「もし、義経さまがいたら、どうなすっていたでしょう」
「疑いもなく、きっと、思いを修羅
に断 って、わしたち夫婦のように、どこか都の隅で、仲よくお暮らしなされていたろうな」
「静
さまと?」
「むむ。・・・・それで思い出したが、静さまは、その後も生きていらっしゃるといううわさがある。うわさはありながら、たえて世間にお姿を見せぬのは、やはりお髪
を剃 されて、山の奥かどこかで、殿の御
菩提 を弔うてでもいるものか」
「そうかも知れません。女のわたしが、静さまのお心になってみても、今の世の中では、そうするしか・・・・」
「そうだな、ほかに女の途もない。男ならば、また生き方もあろうがの」
「けれど、うちの麻丸なども、あれで一体、どうなるんでしょう」
「鵜八どのも、よくい働くと言っているし、もう心配はあるまいよ」
「でも、あんな子ですもの。今は、おとなしくしていますが」
「そう案じてはきりがない。あれの放埓
は、親の落度だ。あのころ、わしの愛情も、あの子へ、ほんとに届いていなかった。老いてから、つくづく思う。これからは、親のわしが、心がける」
「それにしても、医師のあなたの子が、生涯、手を真っ黒にして、染屋の紺
掻 き男なぞで終わったら、世間も笑うじゃありませんか」
「ばかをおいい」
つい麻鳥は、口癖で、しかってしまった。
「笑う世間の方がおかしい。なぜ、紺掻き男では、恥ずかしいのかい。近ごろ、わしは親として、喜んでいるんだよ。
── 時おり、鵜八どのの染場へ寄ってみても、あれが、あきめもふらず、大勢の職子
に交じって、働いている。やれやれ、これでよかった。一人の悪徒を、真面目に返せば、世間の害が、それだけ減る。親のわしも、申し訳が立つ」
「・・・・・」
「むしろ、気の毒なのは、あの子だよ。せっかく学問すべき盛りの年ごろを、可惜
わしゆえ、暗闇で遊んでしまった。もう、今の年では間に合わぬし、頭もわしのようではない」
「・・・・・」
「だからといって、おまえもだが、何を世間に恥じるのか。まじめで、よく働く一個の紺掻き男と、もう亡きお方だが、頼朝殿や、梶原などという者と較
べれも、人として、どこに負
け目 がある院の殿上などで、よくない企みに日を偸
んでいる公卿 方よりは、なんぼう、ましな人間であるかしれぬ。・・・・結構だ。あれで結構。
── 人おのおのの天分と、それの一生が世間で果たす、職やら使命の違いはどうも是非がない。が、その職になりきっている者は、すべて立派だ。なんの、人間として変わりがあろう。・・・・あれもな、蓬
」
「・・・・はい」
「どうか、達者に働いてくれて、小さくても家を持ち、よい女房でも娶
って、やがて、わしとおまえの今日のような一日でも老後に見ることが出来たら、それで申し分ないではないか」
「・・・・ええ。・・・・」
「もともと、わしは、柳ノ水の水守
でもして、一生を終わろうとしたものを、あのような世の乱れになり、おまえという妻にも巡りあって、ついつい、似気
ない生涯をして来たが、さもなければ、紺掻き男ほどの能
もない水守で、井の縁の蛙
みたいな者だったろう。 ── それを思えば、麻丸は、真面目な職を持ってくれたし、円
は丈夫な孫を見せてくれるし、どれもよい子だ。不足を思うどころじゃない。そして、医の業
なら、婿の安成が継ぐだろうしさ。ハハハハ。・・・・。これやいけない。ここでは、こんな固苦しい話は、夢々
、おまえに聞かせるつもりじゃなかったのだよ。さあ、宿へ帰ろう。旅の宿だ、今夜はどんなわがままでもわしへおいい。たまには、わしを困らせて見せないか」
蓬は、はっと、若やいで笑った。
まだ、彼女にも、姥桜
ほどなものは、どこかに残っている。
めずらしい冗談がつい口に出て、自分の冗談に、麻鳥も笑いが止まらなかったが、ふと、妻の手を扶
けて起ちかけながら、起ちもやらず、後ろの方へ、眼を、見張ってしまった。
── そこには、麻丸がうっ伏していたのである。むかしの洟
たれ時代の子のように、いちめんな地の花屑
吹かれさまよう草むらに両手をついて、声もなくただ泣きじゃくっていた。 |