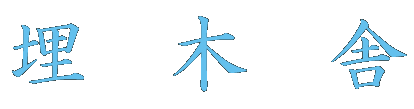いつか山ふところの襞
は紫ばんだ暮色を抱きはじめている。倶利伽羅の山の肩は、夕焼けに染め残され、山風は、急に冷たくなってきた。
すでに、中黒坂の登りだった。歩一歩と、足もとは暗くなる。
するとふもとの方から、しっ、しっ、しっ・・・・という妙な声が聞こえ、一団の鈍重な部隊が、山坂を追い上げて来た。何百頭か、数も知れないほどな牛だった。民家の農牛、牧場の野牛、隊の荷駄
牛 など、あらゆる所から狩り出してきたものに違いない。
不気味で鈍間
な牛の大群も、やがて山麓の平地に寄せられたり、山上に近い木立の中にかくされて、天地は依然、静かな雲のたたずまいと、うっすら、木の間もる宵月の影だけだった。
「音な立てそ」
将士は、戒
めあった。
義仲のいる位置さえ、今は、味方の者にさえ、よく分からなかった。
「なお、何を待たれるのか」
士卒には、それも、合点がゆかなかった。
後に思えば、このときなお、義仲は樋口次郎兼光の一隊が北黒坂の途中から、さらに別れて、遠く、矢田山、九折
、坂戸などの北の嶮路
を迂回 して、はるか平軍のうしろに出る時刻を、辛抱強く待っていたものらしい。
やがて、夜も二更
をすぎたころ、果たして、遠い遠い鼓
(ほら貝) と攻め鼓
が、山風のうちに聞こえてきた。
義仲は、草むらから突っ立って、耳をすまし、眸を、星にこらして、
「まぎれはない、あれは、樋口兼光、余田次郎が打つ攻め鼓
、合図の貝ぞ、者ども、今はよいぞ、木蔭からこぞり起
てやい」
おうっという答えが、山腹のやみをいちどに揺るがした。同時に、ここの陣でも、螺
を吹き、鼓 を打ち、武者声をあげた。
鼓螺
の谺 は、さらに、南黒坂にも、北黒坂にも起こった。呼び交
う嵐 と嵐のようである。そして、そのすさまじい旋風は、武器、よろい、馬具、人間のわめきを包んで、急速に、山上へと、馳せのぼっていった。
不覚にも、猿ケ馬場の平家の陣では、
「や、や、あれは」
と、降ってわいたことのように、四面の敵に仰天した。
昼の小ぜいあいに、やや優勢を示し、矢立山の木曾勢も、夜と共に、沈黙してしまったので、
「さしたる敵かは」 と、自陣も矛
をおさめて、気をゆるめていたものであった。 それに、矢田山、九折
などの嶮 は、踏み越えられる地形ではない。その方面は安全と、警固もしていなかったのだ。
「敵は、前後にあるぞ」
「いや、三方、四方」
「いたずらに、あわてふためくな、まず、卯の花山を前にとり、塔の橋をさかいに、撃って出よ」
十一日の月は雲間にあるが、物惑わしいほど、ほの暗く、ほの明るい。
たちまち、鷲尾山と卯ノ花山のあいだ、また塔ノ橋、天池のあたりで、黒い夜霧が巻いているような両軍の接戦が起こった。
「きたなし、返せ返せ」
「ここに敗れて、都の人びとに、何のかんばせやある」
「木曾は小勢ぞ、何を恐れて」
もう浮き足見せた平軍の中では、悲壮な叱咤が、しきりに叫ばれ、いたずらに多い大軍自体が、足場不足の不利に、その大兵力をもて余し、味方同士、ただ揉み合い、喚
きあいの無秩序をいよいよ加えてしまうに過ぎない。
およそ平家四万を超
える兵数に、二万弱の木曾勢がぶつかったことを想像すると、砥波山の三道、山頂、はほとんど人馬で埋まるばかりであったろう。暗さは暗し、道は狭いし、いかに戦ったかさえ、疑われるほどである。
そのうえ、やがて、機を見ていた義仲が、
「放て」
と、最後の一計を敵に加えた。
海野幸広と小諸忠兼に言い含めて、にわかに集めさせた数百頭の牛を、平軍へ向かって追い放したのだ。
一頭一頭、牛の角
には松明 がくくりつけられてあった。火をつけるやいな、その尻
を、兵がムチで撲りつける。牛は、焔
の角を振りたてながら、盲目的に、敵陣へ狂奔してゆく。
この光と怪物の影を見ただけでも、平軍は、 「何事か?」 と胆
をすくめた。猛牛の群れは人々が 「あれよ」 と、身の処置を取るひまなく、人馬の中に、割り込んできた。
牛は牛とも思えない迅
さと獰猛 をほしいっまにした。人間は踏みつぶされ跳ね飛ばされた。ただ動転
するだけで、それを支える一?の力もない。弓矢、長柄、太刀、甲冑
などは、すべて無用の長物だった。
東にも敵、西にも敵。
北は、嶮
しい岩山。
しかも、急鼓
の響きは、全山をゆるがし、不気味な陣貝の音
は、雲を裂くばかりである。平軍四万は、戦うことを知らなかった。ただ、どう走るか、どこに拠
るか、身を伏せる何かでもないか。岩につまずき、馬は人を踏み、矢風に追われ、火に吹かれ、恐怖の怒涛
を作って、さらにその恐怖の中に、全平家軍を巻き込んでしまった。
すると、一群の軽兵が、猿ケ馬場の東を指して、
「こなたぞ、こなたぞ。こなたは平地、足場も広い」
と、しきりにのどなっていた。
「さては、退き口」
「神の助け」
と平軍のなだれは、先を争って、東へ向いた・ひろたび、よい退き口と見るや、後から後から、全山の平家勢はみなその一所を目がけて集まった。
押しあいヘシあい揉
み重なってゆく、それは、吐け口をえた濁流の勢いに似ていた。
理性の片鱗
も働かしえない悲しい人間の渦だった。洪水
の中の鯉 、鮒
、どじょう、蛙、犬、猫、鳥の漂いとも、何の違いもない相
だった。
盲目なその激流は、絶え間なく、限りなく、いくらでの続いて、後を断たなかった。
行きつかえるはずもない、ゆくての先は巨大な奈落
の口だった。いわゆる倶梨伽羅谷 ── 後世呼んで “地獄谷” とも駆込谷とも言う深い谷底だったのである。
谷はそのころ、十余丈の滝があって、真下は、奔湍
が逆まき、途中の断崖
絶壁 には、一面、栃
の木が繁茂していたという。
「あっ、た、谷間だぞ」
「道はない、道は」
喚
けど、もがけど、この恐怖と狂奔の盲目が急に醒
めるはずもなかった。人も馬も山つなみの勢いをなして、谷底へ落ちころげ、人馬の死屍
は積んで栃 の断崖の半
ばを埋めたほどであったという。
古典平家では、このとき、倶梨伽羅谷に死す者、七万騎とあるが、それほどではないまでも、戦死一万以上はくだるまいとは後の史家もいっている。そして、その谷間から小矢部川へ落ちてゆく水を、里人は、膿川
と呼んだ。夏が来れば栃の若葉にも、秋来れば紅葉にも、地獄谷には四季、鬼哭
啾々 の声が聴かれると、後々まで言い伝えた。
|