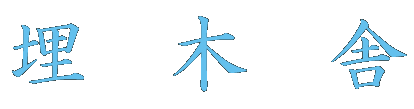蓬
は、のべつ立ったりすわったりしていた。足音を忍ばせては、細殿だの渡殿
のあたりを見張って来るのであった。
疲れ果てたかのようなあらしの夜も、こころもち白み初
めていた。遠い鶏の声もする。彼女は新たな胸騒ぎにせかれ出して、
「お名残は尽きますまいが、もし夜が明けては」
と、常盤の部屋の外に佇
んでいた。そして壁代
の内をうかがっていた。ひそとして、人声はあない。泣き絶えている様子でもない。
「・・・・おや、どう遊ばしたのかしら」
と、内の様子へ眸をこらすと、半蔀
から隙間 もある曉の光に、母子
の姿は、元の所に元のまま見えた。 ── いや、元のままともいえない。常盤は牛若をひざへ抱き上げ、牛若は母の胸深くに眠ってでもいるように、じっと、抱きすがっているのであった。
蓬には思い出された。
牛若がまだ嬰児
のころである。母の乏しい乳房に虫気を起こしては、泣き疲れるとやがてスヤスヤ寝入ってしまう。 ── あのころの母子
そのままな姿をである。蓬はそれを今、几帳
の陰に、再び見たような気がしたのであった。
なんという自然な人間の姿であろう。もう母子
の間に言葉は要らないのだ。十余年の思慕を語りつくして余りあるほどな満足に浸っているに違いない。
蓬は、声をかけるのも罪深い気がして、そのまま外に、しばらくの間佇
んでいたが、思い切って、
「・・・もし、おふた方様、夜も白みかけますぞえ」
と、内へ告げた。
牛若は、母のひざを離れて、急に、もとの眸に返った。
「お暇いたします。・・・・ふたたびわたくしが京へ来る日には、きっと、母君をお迎えに参りまする。源家の騎者
乗物 を従えて」
「いえ、それよりも・・・・」
「なんですか、母君」
「おからだを、大事にして給も、・・・・それだけです、母の願いは」
「身の大切なことは、よくわきまえております。母君にも、きっと、お達者でいてくださいまし。また、お会いできる日を楽しみに」
「おお、楽しみは、それしかありませぬ。だが、武門に立っても、御身は決して、驕
る人とはならないでくださいね。人の非道を憎み、人の権力や栄花をたおしても、また己
れが、前の権者 に代わって同じことを振る舞えば、さらに次の敵が起
って、討ちたおそうとするでしょう。百年、千年、そんな修羅
道 を繰り返してゆく恐ろしさと愚かさを思うたがよい。馬上の将とはおなりになっても、どうぞ、世を守り人を愛して、よい君よと、慕われるようなお方になってください」
「わかりました。・・・・母君もわたくしも、ちまたのさすらいを知っております。貧しい人たちの情けや辛さも見ております。いま仰っしゃったお言葉は、いつまでも、忘れはいたしません」
「せめて、あなたが、そういう武将になってくだされば、亡き頭
殿 にも、どんないよい御供養か知れますまい。・・・・おお、いつの間にやら。・・・・蓬、もう夜が明けたような」
「和子様」
と蓬はおろおろし出して 「ここをどうしてお落ち遊ばしますか」
「大丈夫だよ」 と牛若は、なお落ち着きすましていた。
「夕べの所を越えて帰るから、心配はない。母君もお案じなされますな」
「ま、それにしても、お肌着
まで、濡れたまま、そのお姿では」
「なんの、鞍馬にいるころは、こんないよい物は着ていません。雨も風も平気です。・・・・それよりも、おかあ様」
──
牛若は、急に甘えるような言葉で言った。
「あの、雛
を一つ、くださいませ。母君ぞと思って、持っています」
奈良仏師が手すさびに彫ったらしい小さな内裏
雛 の一つを指して、母の手からそれをもらうと、牛若はうれしそうに、すぐ起ちあがった。
妻戸を出て、裏の廊の欄から、外へとび降りると、もう振り返りもせぬわが子であった。常盤はわれを忘れて、子に名を呼んだ。
牛若の影は、木の間を走り抜け、すぐ加茂川の流れに臨んでいる築土のみねへ攀
じ上がっていた。
その上から牛若は初めて、後ろの古い大屋根の下を振り向いた。母の顔が、妻戸に見えた。永遠に、子の眸から消えることのない母の顔であった。
|