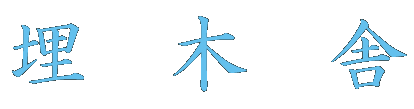袈裟の母は、衣川
の媼 といい、親しいほどではないが、盛遠とは、顔見知りであった。
媼の娘の袈裟が、上西門院の雑仕
をやめて、源ノ渡へ、嫁
ぐ前か、あるいは、その後かも知れないが ── 何にしても、、遠藤盛遠は、いつか深く、袈裟に恋していたものらしい。
盛遠は、夙
に勧学院でも、みとめられ、請来は、朝廷か学問料もたまわり、大学寮へ入って、文章
得業 生
たり得ようとまで ── 嘱望
されていたものであったが、近来の彼の素行は、それらの先輩や、同僚にまで、眉
をひそめさせ、
(盛遠は、近ごろ、どうかしておる)
と、見放されていた。
彼の性来は、ひたむきだった。徹しなければ止まぬのである。博学も、剛毅
も、雄弁も、ひとを群小輩と視
るくせも、その自負から生じている。まして、恋には、なおさらである。熱するに理性を伴わない血液と頑健
な肉体と ── 狂 にちかい情涙の持ち主ときている。
袈裟こそは、災難であった。盛遠にいいよられたときの、おののきも、思いやられる。
それは、執拗
をきわめていたろう。一徹
、わき見を知らない男の横恋慕である。
おそらく“いのちがけ”を示したろう。 ── が、彼女も、男の脅迫の言葉に暗示を得て、同時に、“女のいのちがけ”
を、胸に秘めたにちがいない。
盛遠は、ついに、死ぬか狂気するかの眼
ざしで、さいごの返辞を彼女に求めた。
── 袈裟は、それに、こういう誓いを与えた。前後を、しずかに、考え合えあせて、すでの用意していた答えだった。
(ぜひもありませぬ、十四日の戌刻
、良人 の寝屋
へ、、先に忍んでください。その宵、良人にふろをすすめ、髪の汚れも洗わせて、酒などをあげて寝
ませておきます。・・・・どう仰っても、良人が生きているうちはでは、あなたのお心に従えもいたしません。わたくしは、遠い部屋で、あなたが、ことをすませるのを、眼をつぶって待っておりましょう。
── 良人は、打物
取っては、強者ですから、そっと、枕に近づき、濡れ髪がお手に触れたら、さっそくの一太刀で、首打ち落としてしまうことです。ゆめ、打ち損じてくださいますな)
(──
よしっ)
と、盛遠は、血走った眼でうなずき、その宵、そのとおりに、実行したのである。
実に、何の苦もなく、濡れ髪の一首級を獲て、確かめるまでもない気がしながらも、小坪むかいの簀の子縁に出て、おりふしの月のあかりに、それを、かざして見たのだった。
(ちいっ!しまったっ!)
彼は、恋人の首を、持っていた。
生涯にわたる傷痕
の深手 ── 慙愧 と痛涙
と滅失 のうめきを、この時の一声にふり絞って、彼は、腰をぬかしてしまった。
──
獣すら、かなしむのか、人間の愚を、怒
るのか。
その時、厩
の馬 ── あの四白
の青毛が、異様な声を発し、ひづめをあがいて、いななき止まない。
盛遠は、突然、立ち上がって、何か、哭
きわめくがごとく、灯りのない屋内へものをいった。そして抱えていた、血と濡れ髪とにまみれた冷たいものを、いよいよ高く抱えなおしてかと思うと、ぱっと、籬
、萩 むらなど、おどり越えて、鬼影
のごとく、どこかへ、走り去ってしまった。
・・・・・・・・
以上、今までの調べで判明した内容を、忠盛は、衆に告げて ── さらに、人々へ言うには。
「これは、一女性
、一地下 人
の問題ではない。院の御德
を晦 うし、われら武者所の名にもかかわる。もし、刑部省の手にかかり、朝廷のおん裁
きをうけては、われらなんの面目やある洛内
十二門路、九条の道々の口、さそくに固
めて、きっと、狂者盛遠を、からめ捕
らえよ・・・・」
黒々
と、聞きひそまっていた無数の形は、寂然
と、うなずいた。清盛は、うなずく弾
みに、ポロリと、自分の涙を見た。 ── ひらかれた盲恋の瞼
から。 ── そして、袈裟の美しさに、光の違う美しさを見た。もし、一歩をかえて、自分が菖蒲小路にひかれていらた、自分も盛遠と同じことをやったにちがいないと思う。痴者
、狂者。どっちが自分で、どっちが彼やらわからない。清盛には、どうも逮捕の自信はなかった。しかし、やがて夜明けの門をわかれ立つ他家の手勢の気負いを見ると、彼にも、人に劣らぬ勇躍がわいた。朝霧をついて馳
け向かう鞍馬口へ、野性の眼はかがやいていた。 |