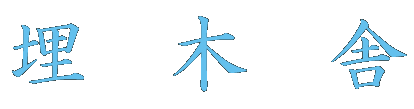「文覚というのは、むかし院の武者所にいて、遠藤盛遠という男だ。おれとは、勧め学院の同窓でもあった・・・・それが、どういうわけで、そなたへ、歌など、寄こしたのだろう」
──
この夜もである。
明かりもない部屋のおぼろな中に、男女
だけで、相寄っていたのに、かれはまたも自分から、さあらぬことなど、言い出してしまった。
「・・・・また、この歌は、どういう意味を、そなたへ、いおうとしているのか。
── すゑ知れぬ霞 の野辺の道とても分けゆくままにかぎりこそあれ、とは」
「分かりませぬ、文覚様とやらにもお会いしたことさえないのです」
「そうか、歌のこころは、おれにも解
ける気がするが」
「どういう意味でございましょう」
源氏は滅び、義朝の縁につながる女子どもも、つらい世を、果て知れずさまようであろうが、いつか、かならず果てはある、源氏の世となる日も来よう。・・・・そういって、そなたを力づけている歌だ」
「ま、そんな怖
ろしいことを」
「いや、世間の情だ、そう考える者が多いのは、ふしぎでない。ことに、文覚は、おれが信西
入道と親しい仲だったという点からも、清盛を、よく見ていないにきまっている」
「いえいえ、それは殿の思い過ごしでいらっしゃいます。わたくしの歌の解きようは、殿とは違いまする」
「どう、ちがう」
「霞の野べの道とは、常盤の心になぞらえて、女の道のかなしさを、歌っているのでございましょう。わたくしに、生きる励みを持つように」
「そうも、解けば、解ける」
「ありがたいお歌と、きょう一日、文机の上において、見ていました。・・・・もう死ぬまい、生きていよう、どうなっても、霞の道を歩こうと思い直して」
「死のうなどと、まだ、おりおりに思うのか」
「え、あまりの、さびしさに襲われると、さくらの花のささめきも、ふと、死の誘いに聞こえてきて」
「鞍馬
の子、醍醐 にある子など、子を見られぬ悲しさにか」
「勿体ない。助けて給わった和子たち、もう世にはいても、いないものと、あきらめておりまする」
「では、亡
き義朝 が恋しゅうてか」
「ア、むごい、おことばを」
常盤は、低く叫んで、白いおぼろな顔に、眼だけを、涙の坩堝
にしてみせた。その沸 りから、珠
を溶 いては、また、いくすじもの珠を、滂沱
と頬 にまろばせた。
「・・・・常盤」
清盛は、抱いた。ふるえる肩を。──
そしてこの夜にかぎって、その肩に、彼女の許容が感じられた。それは乳のみ子の声からも、義朝の亡霊からも、振りほどかれて、彼女がただ一個の女でしかない姿態
を不覚に示したことなのである。清盛の心炎が全身を火にしたのも、それを見た眸がとたんに口火をなしたからだった。
彼が、幾夜も心に飼いつないでいた野生の獣は、檻
の口を開けられたように、猛然と、常盤の唇を追いつめた。常盤は、自分が呼び出した爪牙
の勢いに恐怖して、身を弓なりに面
を反らした。哀訴とも、泣きむせぶともつかない、あやしいうめきも、もう男の思慮にかかるものではない。かえってそれはすでに彼女の肌
にまで迫っていた爪牙を盲目にさせるだけであった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
常盤は、死んだように、なお、いつまでも、袿衣
の下に黒髪を投げみだしたまま、泣いていた。
やがて、清盛が帰ってゆくのも、送らなかった。
白い花びらが、いつとはなく、部屋の中にまで、散り迷って来て、そこの黒髪や袿衣の上にまで、何か、生きものみたいに、白い斑
を置いていた。
こずゑを離れたばかりの花びらは、なおまだ呼吸していたが、彼女の姿は、嗚咽
の波をうちながら、もう、死んだもののようにしか見えなかった。
そしてなお、しゅくしゅくと、春の夜のかぎり、すすり泣いている常盤であった、それは、彼女が彼女を弔う悲涙の葬送楽ともいえるであろう。義朝と別れ、子たちと別れ、今また彼女は、昨日までの自分と別れた。 |