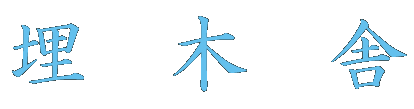たれか、うしろに、人が立ったような気
はいである。常盤はそれを感じないではないが、窓を離れるのは恐
かった。波にされわれまいとして岩にすがっている磯藻
のように、窓によっていた。
「常盤。・・・・何を見ているのか」
やはり、清盛の声であった。
「花を見ています」
と、そのまま答えた。
外の、花明かりに、そこはかとなく、部屋の内は、ほの明るい。清盛は、やがてすわって、ひとり黙りこくっていた。
常盤も、いつまでも窓にいた。
灯の消えていたことが、偶然、二人には倖せした。いつものように、身を硬
め合うて、涙をそむけたり、息をつめて、横顔と横顔と突き合わせている苦しさもない。
清盛が、おりおり、ここへ通い始めたのは、三人の子の処分を明らかにした後である。その前とても、べつに、なんの約束があったわけでもないから、常盤が、
(人目もあります。世間のうわさも、うるそうございます。どうか、ここへは来て下さいますな)
と、断
れば、断り得ないわけではない。
清盛の寛大な処置を、恩とは感じ、情けとはうけても、女の自由は、なお彼女の意志のものである。取りかえてもいなければ、奪われてもいないのである。
けれど常盤には、もうその人へ向って、その人の心を傷
つけるようなことは言えなくなっていた。厭
う気持ちよりは、心待ちに待つような心理が、いつか彼女を支配していた。
(あさましや、わが夫
、義朝殿を亡 ぼした仇人
を)
とみずから、おぞ気をふるって、自分へいい聞かせてはみても、運命の自然な歩みとその環境に伴って、新たな日に適応してゆく心の必然は、否みようもなく、彼女のうちに、彼女も気づかない、変わりかたをいつかしていた。
「・・・・お、夜風に、机の反古
が飛んでいる」
清盛は、壁代
の下へ手をのばした。そしてその紙片を、文机の上へもどす前に、ふと、おぼつかない花明かりをたよりに、読みかけた。 |
| すゑ知れぬ 霞
の野べの 道とても 分けゆくままに かぎりこそあれ |
|
やっと読み判じられた時、常盤も気づいて、
「あれ、それは」
と、あわてて、彼のそばへ、寄って来た。そして、返して欲しい表情をこめて、なお、すり寄った。
「見てはいけない物か」
「いいえ、べつに」
「これは、そなたの筆ではない、たれから来た消息なのか」
「・・・・・・・・・」
「男文字のようでもあるし」
「・・・・・・・・・」
常盤は、答えに困った。
消息ではない、ただの歌反古だといい抜けようにも、折り目が明かだし、また、たしかに、便りの主は男である。
「え、仰っしゃる通り、私の歌ではありません。なんですか、街を歩いていたおかしな僧侶
が、これを常盤御前に渡せといって、蓬子
の手にあずけて行ってしもうたとか」
「蓬子とは」
「以前、子たちの守
をさせていた召使の女童
です。大和の隠れ家に、わざと残して来ましたのに、なお、和子たちやわたくしを慕い、尋ね尋ねて、ここを訪うて参りました。 ── その蓬子が、道で逢うたお坊さまから預かったと申して持って来たのです」
「では、その僧侶は、たれなのか、分かっているはずではないか。そなたの女童
と知らぬ者が、そなたへ、歌の言を、頼むわけもないからな」
「親しくはありませんが、保元の合戦の時、柳ノ水の、あの焼き払われた御所の跡へ、小屋を掛けていた乞食
のようなお坊さまと申しました」
「・・・・名は」
「文覚
とか」
「あ、あの盛遠か」
清盛は、もいちど、文字を見直した。なんのこと、よく見れば、折り目の端に ── もんがく ── と墨うすく、しかし筆鋒
のあらい仮名文字も読まれるのであった。 |
|
| 『新・平家物語(三)』 著:吉川英治 発行所:株式会社講談社 ヨ
リ |