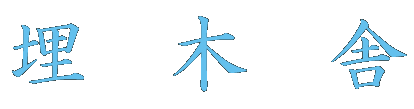|
清盛は気が弱い。
じつに気の弱い一面を、かれは、身近な者や弱い者には持っている。
っては、山王の神輿
振 りに、一矢
を射て、満都の人々を、震駭
させた彼。
熊野路からは、都の変
を聞き、快馬に一鞭 して、争乱の死地へ、馳せ戻ってきたほどの彼。
そして、乱後の内裏
に入って、殿上人
の簡 を手に納めた時には、
(きのうくれて、きょう取る。早いものだなあ)
と、大笑したというほど、人もなげな雄胆
と豪放 を持つ彼が
── おりには、じつに、彼らしからぬ、弱さを暴露
することがある。
頼朝野処分問題は、その好適例といってよい。
さきに、頼朝へは、 「二月十三日に、死罪の処置を取れ」 と内示してある。それなのに、期日が迫っても、官への手続きを取らないし、また清盛自身、何も言い出さないので、ついに、その十三日は、なんとなく、うやむやの裡
に、過ぎていた。
そして、やっと確定を見たのは、それからなお、一ヶ月の余も後で、正式な沙汰
ぶれには、次のように見えた。 |