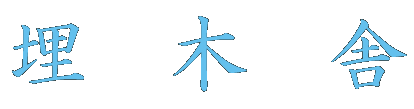夜の洛中は、夜々暗黒を濃くしてきた。
灯の数は、心細いほど、減ってゆく。
六波羅、西八条の中心さえも。
そして、おりおり、大きな火光が、どこかで揚がった。火事だけは、毎晩なのである。
なけなしの家財や乏しい食糧を抱え、病人を負い、老幼の手を引いて、山野へ非難して行く庶民の雑鬧
も、七月二十日ごろから先は、影も、まばらになって来た。
ほとんどと言ってよいほどな家々が、もう、空家あきや
となってしまい、そこに、うごめいている人影があれば、浮浪者か、捨てられた廃人か、でなければ、早くから撹乱に潜入していた堅田湖賊の手下だった。
彼らは、近江武士の源氏と称えて、六月下旬から洛中に姿を現し、活発な働きを起こし始めていた。
こうした非常時には、つきものの掠奪、放火、窃盗、流言、あらゆる現象が、彼らの影とともにあった。
「あの中には、食い物があるぞ」
と、宮廷の穀倉を指した一人の男の煽動で、暴民の一団が、禁門に迫った騒ぎなどもあったが、からくも、検非違使の兵が来て支え止め、そこは、蜘蛛くも
の子と、逃げ散ったが、以来、公卿土倉は、頻々ひんぴん
と、おびやかされた。
七月二十一日のこと。
市中のそんな物騒もよそに、平資盛が、手兵を率いて、近江へ出陣した。
いうまでもなく、木曾勢に当るためである。
六波羅の公称となえ
には、
「一万余騎をもって、近江口を拒ふせ
ぐ」
ということであったが、どこか、意気が上がらず、数も、さしてとは思えない。
富小路の九条兼実は、その日、家僕かぼく
にいいつけて、軍勢の通る辻に立たせ、めんみつに、近江発向の兵数をかぞえさせてみた。
その兼実が、日記 “玉葉” に書いたところでは、たった八千騎でしかないと誌している。そして、近ごろ、六波羅が何千騎とか、何万騎とか言っているのもどうも有名無実にすぎないようだと疑っている。
翌二十二日には、また、権中納言知盛とももり
、左中将重衡しげひら などが、二千余騎を引率して、勢田せた
へ向かった。
そのほか。
山科やましな
へは、池頼盛が。
丹波路へは忠度そのほか一千余騎が。
また、肥後守貞能は、摂津河尻方面へ。
それぞれ、防戦のため、発向したが、それまでの日時を、いったい何に手間取っていたのか。集議をかさねていたのか、いかにも遅い出動である。
──
とは、たれもが疑ったことであろうし、九条家の家僕が、ひそかに、数えてみた通り、各部隊の兵力も、余りに少ない。
「北陸の大敗が、これほどまで、こたえたのか。一門の気概も、再起の意気を失ったのか」
平家にゆかりのある者の眼には、それを路傍にながめても、心から嘆息されたにちがいない。
果たせるかな、二十三日は、もう各方面に、
「平氏の軍勢、利あらず」
という取沙汰が高かった。
日照り続きの空は、ゆうべあたりから真っ黒にかき雲っていたが、特にこの二十三日は、朝から蒸れるような暑さだった。そして午後から、じつに久しぶりな小雨を見たと思うと、加茂川の下流の方で、白電一閃びゃくでんいっせん
、石清水いわしみず 八幡宮はちまんぐう
の宝殿のうしろにある大樹に落雷して、廻廊の一端が炎上した。
やがて夕立となり、加茂川の瀬々に、赤く濁った水かさが見え出して来たころ、美しい夕虹ゆうにじ
が無数に立った。
夜空は、星を見せ、空もようやく、朝夕の変へん
を急きゅう にしてきた。
この夜、またたく星の下には、人思い思いに、人界の各所では、いろいろな動きがながめられたのである。
六波羅の灯の下では、
「もはや、これまでぞ、都をよしに遷うつ
し、西国へ赴いて、再度の計をめぐらさん」
と、都落が、密議されていたし、山科、近江、丹波などへ発向したばかりの軍勢は、ちりぢりに、洛中へ逃げ戻って来た。
また、宮中にも騒然たる気はうかがわれ、内大臣、皇后大夫、平大納言、堀河大納言、民部卿、右大将などの諸官が、うろたえ顔をよせ集めて、
「かくなっては、賢所かしこどころ
も、京の外へ、渡御とぎょ あるべきではないか」
「いや先例がない」
などと、明日の日も信じられないように、たち噪さわ
いでいた。
ところが、この非常時も知らぬように、後白河法皇の御所法住寺殿ほうじゅうじでん
の内外だけは、つねの通り、しいんとしていた。この静けさは、なぞであり、不気味なほどであった。そしてまだ宗盛は、法皇のお肚の中に、何か蔵ぞう
されていて、このような無風帯を呈しているのか、読みことも出来なかった。また、疑いもしてみなかった。 |