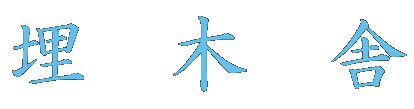お亡くなりになった高倉上皇は、御年二十一であった。 |
| ──
御在位のおん時、人の従ひつき奉ることは、延喜
、天暦てんりゃく
の帝みかど
と申すとも、いかで勝まさ
らせ給ふべきとぞ、人みな申しける。 |
|
と時人じじん
が頌たた
えたのをみても、この君に対する同情の思いは、たれもが、ひとしかったようである。
庭守にわもり
の仕丁しちょう
が、過って、御鍾愛ごしょうあい
の楓かえで
を伐き
って焚た
いてしまい、罪となるところを、助けておやりになった有名な御逸事。
また。
ある女房に仕えている女童めのわらべ
が、辻盗人のために、主人の仕立物の衣裳を奪と
られてしまったのを、あわれに思われて、それに衣裳をお与えになったうえ、近習に命じて、宿やど
の局つぼね
まで、送らせておやりになったというようなこともあった。
美しい御事歴は、なかなか多い。
そのうちにも、この君と小督こごう
の局つぼね
との悲恋は、琵琶びわ
や謡曲にも語り継がれ、また、大和絵やまとえ
などの好画題にもなっている。
そのあらましを、ここに誌しる
せば。
いつの年とも知れぬが、まだ、、この君が、天皇の御位みくらい
にあったころ。
中宮
(徳子) の御方から、小督こごう
という女房をお側へまいらせた。
小督は、桜町中納言の娘で、禁中に目立つほどな美貌びぼう
であったばかりでなく、琴を弾ひ
いては、無双な上手であったという。
この才媛さいえん
には、もちろん、ひく手あまたであった。中にも、冷泉少将れいぜいのしょうしょう
隆房朝臣たかふさあそん
とは、行く末を約した恋仲であった。けれど今は、天皇の御寝ぎょしん
に侍かしず
く身となったので、泣く泣く思い断つしかない。
入道相国は、そのもつれを、人づてに聞いて、
(怪け
しからぬことかな、中宮と申すも、わがむすめ、冷和泉の少将とて、わが婿むこ
(清盛の四女の婿) なれ、小督こごう
の局つぼね
に、婿むこ
二人まで取られたと聞こえて、世上のわらい草ぞ)
と、怒って、ひそかに、小督こごう
を人手にかけて失わせようと計ったことがある。
小督は、それを知って、内裏だいり
をまぎれ出で、どこかへ、姿を隠してしまった。
主上のおん嘆きは、ひとかたでない。夜よる
の御殿おとど
に入らせられても、おん涙に沈み明かしておられるし、月の光を見給うても、すぐお眼を曇らすのであった。
「ころは八月十日すぎのある夜。
弾正大弼だんじょうのだいひつ
仲国なかくに
という侍者じしゃ
があって、
(かかる夜は、小督こごうも君を偲しの
び奉って、月のことに、琴を弾ひ
いておりましょう。仲国が心あたりを尋ね歩き、小督の殿を召し連れて参りましょうず)
と、お慰め申し上げた。
主上のおよろこびはいうまでもなく、
(さらば、寮りょう
の馬に乗って行け)
と、御寮の馬を賜うたので、仲国は、名月に鞭むち
をあげて、嵯峨野さがの
のあたりへさして行った
月も更ふ
け、野末の草の露に、人も馬も、しとどに濡れながらも、なお、さまよっていると、小倉山のふもとの辺りで、ふと、琴の音が耳にふれた。
草屋の片折戸をうかがってみると、軒端の月影を、琴の上にうけて、想夫恋そうふれん
の曲を弾いている佳人がある。まぎれもない小督であった。
仲国は、不意の訪れに、小督を驚かして、さて、
(これこそ、恋い悩み給う君のお墨にて候なれ)
と、主上の御書を、手渡した。
(夢か?)
と、小督は、それを披ひら
く。
匂わしさ、麗うるわ
しさ、悩ましげな姿である。
(ぜひぜひ、禁中へもどり給われ)
と、仲国は、すすめたが、小督は、顔を振って、涙を垂るるばかりだった。
(さらば、この家や
のあるじよ。この女房を、ゆめ、家の外に出しまいらすな)
仲国は、宿の者にいいつけ、また、自分の従者を番において、いちど、宮中へ引っ返した。
ちょうど、夜はほのぼのと白みかけていた。
さだめし、主上には、まだ御寝ぎょしん
のころであろうにと察しながら、南殿なんでん
へ出てみると、主上は、ゆうべの御座ぎょざ
の所に、まだ、お姿もくずさず、そのまま坐っておいでになった。
仲国の報し
らせと、そして、小督の返し文ぶみ
を御覧になると、矢や
も楯たて
もないみけしくで、
(さらば、仲国、夕べをはばかって、ひそと連れて参れ)
と、仰っしゃった。
小督を乗せた女車は、やがて、嵯峨野の夕をあとにして、宮中にかくれた。
どれほどな月日が過ぎたろうか。
まもなく、入道の耳にこれが聞こえ、小督は、髪ををおろして、一庵をむび、もう二度とは、人の世の恋はしなかったというのである。
|
| ──
無下むげ
に憂う
たてき事どもなり、主上は、かようの事共に、御悩ごなう
(御病) づかせ給うて、やがてかくれさせ給ひけるとかや。 |
|
古典は、こう結んでいるが、この話は、元より真実を伝えたものではない。
似たような御事蹟も、じつは、あったかどうかも、疑問である。
唐朝とうちょう
の詩人白楽天はくらくてん
の
“長恨歌” に詠まれた玄宗皇帝と楊貴妃ようきひ
の恋をとって、平家物語の作者が、大和調な文体に移し、小督と天皇の事に書き直したものであると、説を立てる学究もある。
おそらく、そうであろう。そういう例は、ほかにも少なくない。
文学の上ばかりでなく、絵画にも、工芸にも、宗教にも、あらゆる部門に、多いのである。思想すらも、移植であった。
けれど、移植が移植のままではなかった。この国の風土による調和作用を経ると、ふしぎに、この国の国初くにはじ
めからもあるような開花と盛りを見せるのだった。
──
余談はおいて。
さて新しい治承五年も、正月中から、そんなふうで、百官は喪も
に服し、大葬は、東山の清閑寺ど行われた。
幼帝の安德は、ことしお四ツになられ、国母建礼門院は、故上皇より六つ年上であったから、二十七というお若さで、はやくも、孤婦となられたわけである。
それやこれやで、宮中でも、平家の門でも、管絃かんげん
の音ね
さえ聞かれなかったところへ、やがて、東風こち
吹くころに聞こえて来たのは、新宮十郎行家が、突如、美濃源氏を狩り集めて、尾張へ攻め入ったという報らせであり、また、木曾義仲が、信濃を出て、野火のび
のような勢いを伸ばして来たという早馬であった。
|